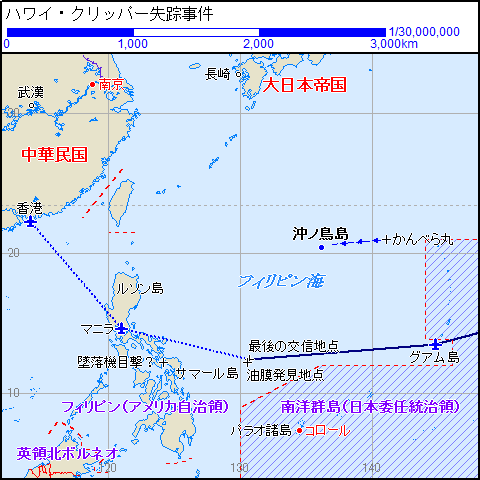
管見の限りでは、1931年(昭和6)7月の沖ノ鳥島の領土編入について直接報じた新聞記事は特に見当たらない。領土編入を示す内務省告示自体は『官報』に掲載されているのだが、特に政府からの記者発表などがあったわけでもなく、一般国民はほとんど気づかなかったものと思われる。
内閣統計局編纂の『日本帝国統計年鑑』(『日本統計年鑑』の前身)では、1932年(昭和7)12月発行の第51回から、「本州」の「極南」(南端)の地点が「小笠原島南鳥島南端」から「小笠原島沖ノ鳥島南端」に訂正されている(*)。これにともない、各社発行の年鑑類でも、1933年(昭和8)の版からは本州最南端の地点が訂正された。もっとも、確かに沖ノ鳥島は領土編入の時点で大日本帝国の領土の最南端となったのではあるが、当時はその南方に、国際連盟委任統治領として日本が統治していた南洋群島(**)の島々が、ほとんど赤道直下まで拡がっていた。
(*) この版では「帝国」の「極南」を「高雄州恒春郡恒春庄七星岩南端」(北緯21度45分35秒)としている。七星岩(台湾の南方海上にある岩礁、現在は台湾の屏東県恒春鎮に所属)は下関条約(1895年=明治28)以来「大日本帝国」の最南端となっていた。ただし、じつは沖ノ鳥島の方が南にあるので、ここも「沖ノ鳥島」とあるべきところである。この間違いは、2年後、1934年(昭和9)12月発行の第53回においてようやく訂正されている。
(**) 現在のマーシャル諸島共和国、ミクロネシア連邦、パラオ共和国およびアメリカ自治領北マリアナ諸島。その最南端はポナペ支庁区に属するグリーニッチ島(カピンガマランギ島。現在はミクロネシア連邦領)で、北緯1度1分30秒(第53回『日本帝国統計年鑑』による)に達する。なお、この島々の統治権は元来、ヴェルサイユ条約に基づいて国際連盟から日本政府に委任されたものであるが、日本は1933年3月に国際連盟に対して脱退を通告した(国際連盟規約第1条第3項の規定により、正式な脱退は2年後の1935年(昭和10)3月となる)のちも、日本がヴェルサイユ条約から脱退していない以上は依然として委任統治は有効だと主張し、この島々に居座り続けた。
それでは、「沖ノ鳥島」の名が最初に新聞の紙面に現れたのはいつなのか。
CD-ROM 版『朝日新聞戦前紙面データベース』によれば、『東京朝日新聞』紙上での「沖ノ鳥島」という語の初出は、1938年(昭和13)8月8日附朝刊の「沖ノ鳥島附近漂流か/遭難のクリツパー機」という記事である。これは、当時起こった、ある奇妙な航空事故に関連したものであった。
1938年夏。1年前に宣戦布告なき戦争として始まった日中戦争は、すでに収拾のつかぬ泥沼へと陥りつつあった。開戦当初、日本側は、中国(中華民国国民政府)は当時の首都であった南京が陥落すれば屈伏するはず、という甘い見通しを持っていた。だが、国民政府の指導者である蒋介石(蒋中正。1887-1975)は、拠点を南京から武漢、ついで内陸部の重慶に移し、徹底抗戦を唱えたのである。この年1月に日本政府は、「爾後(じご)国民政府を対手(あいて)とせず」と宣言し(第1次近衛声明)、自ら戦争収拾の道を閉ざしてしまった。さらに4月、日本政府は、持てる国力のすべてを戦争へと傾けるべく「国家総動員法」を制定する(同年5月施行)。7月には、1940年(昭和15)に開催が予定されていた東京オリンピックと日本万国博の中止が決まり、また同月末には日本の傀儡国家「満洲国」とソヴィエト連邦との国境地帯で軍事衝突(張鼓峰事件)が引き起こされている。いっぽう、ヨーロッパでは、3月にオーストリアを併合して領土拡大の野心をあらわにしていたナチス・ドイツが、ついでチェコスロヴァキア西部のズデーテン(スデーティ)地方に狙いを定めていた。そして内戦の続くスペインでは、ナチス・ドイツとファシスト・イタリアの支援を受けた叛乱軍に追い詰められつつあった人民戦線政府が、最後の反撃に打って出ようとしていた。
7月29日午前6時9分(グアム時間、日本時間午前5時9分)、パン・アメリカン航空(パンナム)のマーティン M-130 飛行艇「ハワイ・クリッパー」(NC14714 Hawaii Clipper)がグアム島(アメリカ領)を飛び立ち、フィリピン(当時アメリカ自治領)のマニラへと向かった。
ところが同機は、7月29日の午後0時3分から11分まで(マニラ時間、日本時間午後1時3分~11分)の無線交信を最後に、一切の消息を絶ってしまったのである。最後の連絡は次のようなものであったという。
「現在フイリツピン海岸から 565 マイル[海里、約 1050km]の位置にあり、雲深くコンデイシヨンやゝ悪く、乗組員九名、旅客六名」(『東京日日新聞』1938年7月30日付朝刊「ハワイクリツパー機憂慮さる」。なお、数字表記を一部改めた。以下同じ)
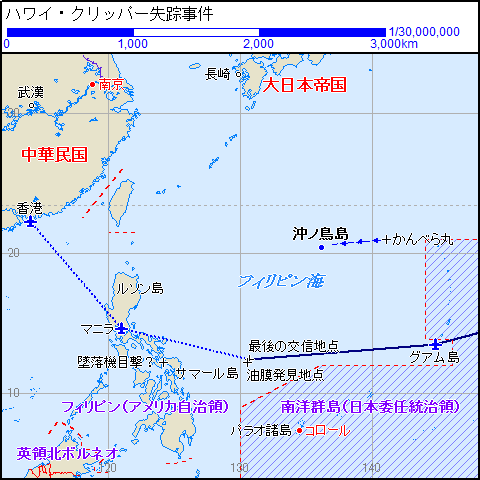
パンナムは1927年(昭和2)にアメリカで設立され、フロリダ州のキーウェストとキューバのハバナとをつなぐ郵便輸送から業務を開始した。同社の実質的な創立者であるジュアン・テリー・トリップ(Juan Terry Trippe, 1899-1981)は、若年ながらアメリカ政財界に太いパイプを持つ野心家で、その政治力を駆使して中南米各地に航空路を次々と開設し、さらに太平洋への進出をもくろんでいた。
1935年11月、パンナムは、サンフランシスコからマニラまでを島伝いに結ぶ、初の太平洋横断定期航空便を開設した。途中の経由地はホノルル、ミッドウェイ島、ウェーク島、グアム島で、全航程には4泊5日を要した。当初、この航路では郵便輸送のみが行われていたが、1936年(昭和11)10月から旅客営業も開始され、さらに1937年(昭和12)4月には香港まで延伸されている。そして、この航路のためにグレン・L・マーティン社(ロッキード=マーティン社の前身の一つ)が開発したのが、航続距離 5150km を誇る4発エンジンの大型飛行艇・マーティン M-130 ――通称「チャイナ・クリッパー」(Martin M-130 "China Clipper")であった。
当時、このような長距離海上航空路には、普通の飛行機ではなく飛行艇を用いることが一般的であった。理由はいくつかあるが、水面に離着するため滑走路を整備する必要がないことや、ランディングギアの強度に配慮する必要がなく大型化が容易であったこと、万一の事故でも着水できるので安心だと考えられていたこと、といったあたりが主なところである。 M-130 はわずか3機のみが製造され、1号機は「チャイナ・クリッパー」、2号機は「ハワイアン・クリッパー」(Hawaiian Clipper; のち「ハワイ・クリッパー」と改称)、そして3号機は「フィリピン・クリッパー」(Philippine Clipper)とそれぞれ名づけられていた。ちなみに「クリッパー」とは19世紀に活躍した快速帆船を指す呼び名で、パンナムではこれを飛行艇の愛称などに用いていた。なお、「チャイナ・クリッパー」は、本来は M-130 型1号機の愛称なのだが、この名が有名になりすぎたため、いつの間にか M-130 型の機体すべてがこの名で呼ばれるようになってしまった。1936年には宣伝映画『太平洋横断機』(China Clipper. レイモンド・エンライト監督。出演パット・オブライエン、ハンフリー・ボガート他)が製作されている。
1930年代の飛行艇での空の旅は、今日の、数百名もの乗客を音速に近い速度で大量輸送する、というジェット機での旅とは大きく異なるものだった。夜間の離着水は水面が見えず危険なため、飛行は昼間のみに限られ、夜は島に停泊することになっていた。そのため M-130 には寝台が設置されており、また、ラウンジや食堂なども整備されていた。こうしたせいもあって、全長 27.7m・翼幅 39.6m という大きさの割には乗客定員は少なく、太平洋航路は定員わずか12名で運航されていた(寝台は18人分が用意されていた。また、寝台を外せば40人以上が搭乗可能だった)。当然ながら運賃も高額で、一般人がおいそれと利用できるものではなかった。
パンナムの航空事業は重大な事故もなく順調に進んでいるかに見えたが、1938年になってはじめて大事故が発生した。1月12日、シコルスキー S-42 飛行艇「サモアン・クリッパー」(Samoan Clipper)が、南太平洋での調査飛行の途上、アメリカ領サモアの首都パゴパゴを飛び立った直後に空中爆発を起こしたのである。この事故で、初めてパンナムの太平洋横断空路を飛んだエド・ミュージック機長(Edwin C. Musick, 1894-1938)が犠牲となった。その衝撃も覚めやらぬうちに、さらなる大事故が発生してしまったのである。
行方不明になったハワイ・クリッパーの機長は、ロシア系アメリカ人でヴェテランのパイロットであるレオ・ターレツキー(Leo Terletzky)であった。また同機には、乗客として、ジョージ・ワシントン大学医学部長アール・ボールドウィン・マッキンリー(Earl Baldwin McKinley)、アメリカ農務省の植物病理学者フレッド・キャンベル・メイヤー(Fred Campbell Meier)、航空機メーカーのカーティス=ライト社副社長エドワード・E・ワイマン(Edward E. Wyman)といった名士たちが乗り込んでいた。
ハワイ・クリッパーが最後に無線交信を行った地点は、北緯12度27分・東経130度40分とされている。7月30日付『ニューヨーク・タイムズ』紙によれば、最後の交信まで同機の様子は順調そのものだったのだが、その1分後に管制側が再び交信しようとしたところ、連絡がつかなくなってしまったという。
失踪当時の同機の状況について、『東京朝日新聞』紙は以下のように報じている。
同機はグアム島で多量の食料及び飲料水を積載し原則的には乗客及び乗務員全部に対する二週間分のものがあるはずであり、かつ機体は着水しても浸水しない事になつてゐるが海上の風波荒き場合には必ずしも安全とはいへない、(『東京朝日新聞』7月31日付夕刊「クリツパーなほ不明/軍用金持参の支那人も搭乗」)
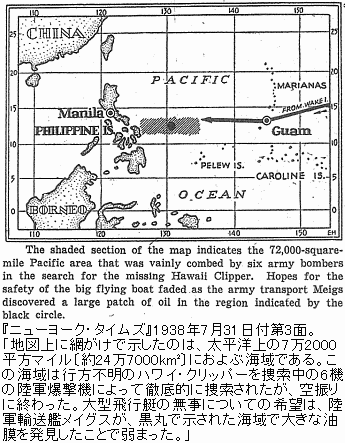
失踪の翌日、7月30日に行われた捜索で、アメリカ陸軍の輸送艦メイグス(USAT Meigs)は、北緯12度11分・東経130度32分附近の海域で、多量の油が周囲 1500 フィート(約 460m)にわたり海面に浮いているのを発見した。ハワイ・クリッパーが最後の交信を行った地点のすぐ近くである。分析の結果、この油は同機の用いていたものと一致したという(『東京朝日新聞』7月31日付朝刊「海面に多量の油/「クリツパー機」の捜査」、『読売新聞』同日付朝刊「ク号はグアム島マニラ間で遭難/海上で発見された油を分析/同機のものと確認」)。しかし、アメリカ陸海軍による大々的な捜索にもかかわらず、それ以外に同機の残骸らしきものは一切発見されなかった。失踪から1週間後の8月5日、海軍は捜索打ち切りを宣言する。
8月6日(日本時間7日早朝)、アメリカ国務省は駐日アメリカ大使館に対し、
「同号[ハワイ・クリッパー]は北緯20度25東経136度5ダグラスリーフ(沖ノ鳥島)付近に漂流してゐる模様につき捜索救助方日本側の御協力を乞ふ」(『読売新聞』8月8日付朝刊「クリツパー機漂流か/潮岬南方八百五十浬の洋上/かんべら丸現場へ急行」)
と打電してきた。アメリカ側では、何らかの形で着水したまま身動きがとれなくなった飛行艇が、潮流や貿易風などの関係で北へと流され、沖ノ鳥島附近を漂流しているのではないか、と考えたようである。新聞各紙はこの件をかなりの紙面を割いて報じており、その中で「沖ノ鳥島」の名前も取り上げられていた。日本の新聞に「沖ノ鳥島」という文字が掲載されたのは、どうやらこれが初めてのようである。
アメリカ大使館からの要請を受けた外務省では、ただちに海軍省・逓信(ていしん)省(交通・通信・電気行政全般を管轄していた中央省庁)・台湾総督府(台湾を管轄していた統治機関)・南洋庁(南洋群島を管轄していた統治機関)などの諸官庁に連絡し、附近を航行中の船舶に注意を促した。
このとき、オーストラリア産のヒツジを積んで日本に向かって航行していた大阪商船の貨物船「かんべら丸」(6477t。船名はオーストラリアの首都キャンベラにちなむ)が、たまたまこの近く(北緯21度・東経141度附近)にいた。海軍省は、同船に対して現場に赴き捜索するように命じている。
「かんべら丸」はただちに沖ノ鳥島へと向かい、8月8日午前1時、現場海域に到着した。しかし、同船は沖ノ鳥島の北東方約 30 海里(約 56km)四方を捜索したものの、それらしき痕跡は一切見つからなかった。しかも、翌9日朝には急速に天候が悪化したため、かんべら丸は捜索活動を中止せざるを得なくなる。9日午後1時半、「かんべら丸」は読売新聞本社に対して以下のような通信を送ってきている。
今早朝来の天候急激に悪化し驟雨[にわか雨]の襲来絶えず視界すこぶる狭し、中央気象台[気象庁の前身]の報告によつても付近に低気圧発生せること明らかにして上甲板の緬羊[ヒツジ]も気遣はる故、急遽長崎に向ふ、なほ途中厳重なる見張りを怠らざること勿論なり(『読売新聞』8月10日付第2夕刊「クリツパー捜査荒天で打切り/かんべら丸引返す」)
結局、何の消息もつかめないまま、「かんべら丸」は8月11日に長崎に入港した。かくて最後の頼みの綱も空振りに終わったのである。
その後1ヶ月ほどして、ヒトラーがいよいよズデーテン地方への野心をあらわにし、それを阻止しようとする英仏両国との間で戦争勃発の危機が高まっていた頃、『東京朝日新聞』は以下のような続報を載せた。
[9月]十八日マニラに達したマニラ・トリビユーン紙記者の報道によればフイリツピン群島中のサマル島西海岸マラガ附近の漁夫が[ハワイ・クリッパー失踪の]当時サマル沖十浬[約 18.5km]の海上で漁撈中白色の飛行機が火災を起し海中に墜落沈没したのを目撃したと云ひ、又同島住民はガソリンが海岸に多量浮流して居るのを発見した旨述べたと言はれる(『東京朝日新聞』9月20日付夕刊「発火墜落か/遭難のハワイクリツパー機」)
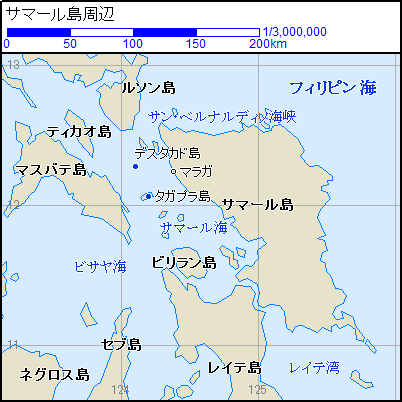
サマール島はフィリピンで3番目に大きな島で、ルソン島とはサン・ベルナルディノ海峡をはさんで向かい合っており、東はフィリピン海(太平洋のうち、小笠原群島・マリアナ諸島以西の海域)、西はサマール海(ルソン島・サマール島・レイテ島・マスバテ島などに囲まれた狭い内海)に面している。9月18日付『ニューヨーク・タイムズ』紙によれば、問題の海域はサマール海上、「タガプラ島とデントゥカド島」(Tagapula and Dentucado islands)から約 18 海里(約 33km)、サン・ベルナルディノ海峡の南西約 30 海里(約 56km)の地点であったという(*)。だが、9月20日付の同紙は、マニラの新聞記者からの報告として、この目撃証言は確認できなかったと報じている。結局のところ、単なる虚報であったようである。
(*) このように報じられているのだが、実際の地理と合わない。まず、サマール海の東西の幅は 50km ほどしかなく、サン・ベルナルディノ海峡から南西に 30 海里進むと、対岸のマスバテ島沿岸にたどりつくことになってしまう。また、デントゥカド島はおそらくデスタカド島(Destacado)のことかと思われるが、この島はタガプラ島から北に 25km ほど離れており、両島から 18 海里とはどの地点を指すのか曖昧である。
9月末、英仏独伊の4ヶ国はミュンヘン協定を締結し、チェコスロヴァキアはズデーテン地方をドイツに割譲させられることになった。
中国戦線では、日本軍が10月に広州(広東)と武漢を占領した。しかし、国民政府は依然として徹底抗戦の構えを解く様子がなく、戦線の拡大はこの段階で行き詰まってしまう。11月3日、日本政府は、日中戦争の目的は「東亜新秩序」の建設にある、として中国に協力を呼びかける声明(第2次近衛声明)を発表する。この声明は、それまで曖昧であった戦争目的を明らかにするとともに、第1次近衛声明を撤回し、国民政府内の和平派を切り崩す狙いに基づくものであったといわれている。しかし、結果的にはわずかに国民党副総理の汪兆銘が呼応しただけにとどまり、さらに、アメリカやイギリスの対日不信をかえって強めることになった。
チェコスロヴァキア一国を犠牲にする形であがなわれたヨーロッパの平和も、わずか半年で崩壊してしまう。翌1939年(昭和14)3月、ドイツはチェコスロヴァキアからスロヴァキア共和国を独立させるともに、残ったチェコ地方を併合し、ここにチェコスロヴァキアは解体した。ついで3月末にはスペイン人民戦線政府の首都マドリードが陥落、4月にはイタリアがアルバニアに侵攻する。そして9月にはドイツがポーランドに侵攻、これに対してイギリスとフランスがドイツに宣戦布告したことで、ついに第2次世界大戦の勃発を見るに至るのである。
こうした状況の中で、ハワイ・クリッパーの失踪は次第に忘れ去られていった。
ところで、同機の乗客の一人は中国人であったのだが、この男は蒋介石の軍資金を運んでいた、と噂されていた。『東京朝日新聞』は以下のように報じている。
尚[なお]六名の乗客中にはニユーヨーク附近で支那料理店を開いてゐる萬某といふ支那人があり同人は蒋介石宛の多額の軍資金を携帯してゐたと噂されてゐる
同人についてニユーヨークの支那人街では萬は蒋介石の心酔者で今回十数年振で帰国するに当り米国東部地方在住支那人より集めた数十万ドルの献金を携帯して居たと云つて居り、同人の遭難でこの金が太平洋の藻屑と消えはしまいかと大騒ぎをしてゐる(『東京朝日新聞』1938年7月31日付夕刊「クリツパーなほ不明/軍用金持参の支那人も搭乗」。「支那」については原文のママ)
この中国人は、ニュージャージー州ジャージー・シティ(ハドスン河をはさんでニューヨークの対岸にある)の中華料理店のオーナーであった、ワー・スン・チョイ(Wah Sun Choy; チョイが姓)という人物である(どのような漢字を当てるのかは不明。『東京朝日新聞』の「萬」は、 Wah を姓と誤解したものと思われる)。
ハワイ・クリッパーの航路は南洋群島委任統治領にほど近い。しかも、当時の日本政府は南洋群島への外国人の立ち入りを制限していたため、以前から、ひそかに軍事基地化を進めているのではないか、という疑惑を持たれていた(*)。そして、当時の日米関係は、日中戦争をめぐり悪化の一途をたどっており、アメリカ国内では反日感情が高まりつつあった。
(*) 委任統治領の軍事基地化は国際連盟規約第22条で禁止されおり、さらにワシントン海軍軍縮条約第19条では太平洋諸島における軍備体制の現状維持が取り決められていた。なお、じつはこの点に関しては日本側はいちおう律儀に条約を守っており、実際に軍事基地化に着手するのは、1936年末にワシントン海軍軍縮条約が失効して以後のことだといわれている。
こういった事情もあり、同機の失踪は、この軍資金運搬を狙った日本人による何らかの破壊行為だったのではないか、と示唆する説は、失踪当初からハースト系の新聞(*)で流されていたという("Clipper Down", TIME, Aug. 8, 1938)。いな、それどころか、パンナムのトリップ社長自身、この事件は日本側の破壊工作によるものだと主張していたという(J・C・ペリー『西へ!』)。
(*) 新聞王ウィリアム・ランドルフ・ハースト(William Randolph Hearst, 1867-1951)が経営を手がけていた新聞の総称。「イェロー・ジャーナリズム」と揶揄される過激な扇情的報道で知られ、また日系移民排斥問題などで排日的な論調を煽ったことでも知られる。
アメリカ人のロナルド・W・ジャクソン(Ronald W. Jackson)は、1980年(昭和55)に発表した著書『消された飛行艇』(China Clipper. 邦訳=小西昭之〔訳〕、毎日新聞社、1981年)の中で、この事件は、この軍資金と、ついでにアメリカの飛行艇の技術をも狙った日本海軍によるハイジャックだとする説を唱えた。もし仮にこれが事実だとすれば、世界史上初の民間旅客機ハイジャック(*)ということになる。
(*) D・ゲロー『航空テロ』によれば、記録に残る世界史上初の航空機ハイジャックは、1931年2月21日に、ペルーで革命家グループがパンナムの運航する郵便飛行機を宣伝ビラをばらまく目的で乗っ取った事件であり、また、史上初の旅客機ハイジャックは、1948年4月6日にチェコスロヴァキア航空の国内定期便が国外亡命目的で乗っ取られた事件だという。なお、M・テイラー+D・マンデイ『航空ギネスブック 日本語版』(イカロス出版、1998年)は、1948年7月16日に起こったキャセイパシフィック航空「ミス・マカオ」号のハイジャック事件を史上初とするが、誤りである。
ジャクソンは次のように推理する。失踪の原因として、超常現象などを排除した上で現実的に考えられるのは、(1)悪天候による空中分解または空中爆発、(2)構造欠陥または機構欠陥による空中分解、(3)時限爆弾による爆破、(4)撃墜、(5)ハイジャック、の5つだけである。だが、徹底的な捜索活動にもかかわらず何の残骸も発見されなかったことは、ハイジャック以外では説明できない。空中分解や爆発や撃墜などであれば、捜索で必ず残骸が発見されるはずだからである(なおジャクソンによれば、7月30日に発見された油膜は、検査の結果、ハワイ・クリッパーの使っていた油とは異なることが判明したという)。
そしてジャクソンは次のように想像する。実行犯は日本海軍の士官2人で、彼等はひそかにグアム島に潜入し、着水していたハワイ・クリッパーの荷物室に潜り込んだ。そして、マニラへの飛行中にハイジャックを決行し、南洋庁が置かれていたパラオ諸島(現在のパラオ共和国)のコロールに着水させた。撃墜や爆破ではなくハイジャックという方法を選んだのは、同機を技術上の参考材料とするためであった(ジャクソンによれば、 M-130 のライセンス生産はアメリカ海軍によって禁止されていたため、日本は正規ルートで技術を獲得することができなかったのだという)。そして、同機をモデルとして製造されたのが、日本海軍の傑作機のひとつとして知られる川西航空機(新明和工業の前身)の二式飛行艇(通称「二式大艇」)(*)である(ただし、再三にわたり改良が重ねられたため、結果的にはかなり違うものになった――と、ジャクソンは主張している)。また、この背景には、太平洋横断航路の運航に対する日本側の敵意があったという。
(*) 1938年8月に「十三試大型飛行艇」として海軍から試作を指示され、1940年12月に初飛行、1942年2月に「二式飛行艇」(H8K)として制式採用となった。ちなみに、当時の日本海軍では、試作機については試作年度の元号の数字(この場合は1938年=昭和13年の「13」)、制式採用機については採用年度の皇紀年号下2桁の数字(この場合は1942年=皇紀2602年の「02」)を、それぞれ呼称として用いていた。
しかし、ジャクソンの主張の根拠は状況証拠だけであり、はっきりとした物証や証言は何も示されていない。彼の主張通りなら、この事件は日本軍による組織的な犯行であり、しかも、今日に至るまで完璧に隠蔽され続けてきたことになる。それも、その間に、日本がアメリカとの戦争に敗れて軍事占領され、軍隊も解体されてしまったにもかかわらず、である。はたしてそんなことがありうるだろうか。
そもそも、通常の事故だとしても、残骸が必ず発見されるとは限らない。海上で事故が起こった場合、状況によっては、捜索が始まるまでに遺物が全て水没してしまうことも十分にありうる。じっさい、過去の航空事故の中には、事故の発生位置がほぼ特定できているにもかかわらず、残骸がついに発見されなかったという事例もいくつか存在しているのである。
たとえば、すでに1936年12月7日には、エールフランスのラテコエール300型郵便飛行艇「南十字星」(ラ・クロワ・デュ・シュド)号(Latécoère 300 La Croix du Sud)が、セネガル(当時フランス領)のダカールからブラジルのナタールに向かう途中、南大西洋上で行方不明になる、という事件が起こっている。同機は、フランスを代表する名パイロットとして知られたジャン・メルモーズ(Jean Mermoz, 1901-36)が操縦していたものだが、発動機故障を伝えてきたまま消息を絶っており、その行方はいまだにわかっていない。
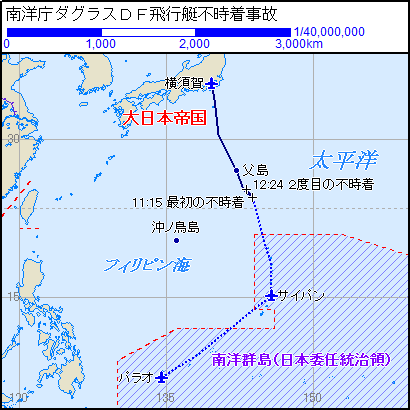
ハワイ・クリッパー失踪から約半月後のことである。1938年8月10日午前4時47分、勝畑清機長(南洋庁航空官)ら7名が乗り込んだ、南洋庁のダグラス DF 飛行艇(Douglas DF)が横須賀を飛び立った。同機はサイパン島を経由してパラオに向かう予定であった。当時、南洋庁では内地・サイパン・パラオをつなぐ定期航空便の開設を計画しており、同機はこの航路に利用されることになっていたのである。
ところが、11時20分、同機は、突如「不時着」と無線で伝えてきた。無線連絡によれば、同機は小笠原諸島近海を飛行中に右エンジンの故障を起こし、11時15分、北緯24度32分・東経143度45分の地点(父島の南南東約 320km)に不時着したのだという。その後、父島に引き返すことにしたと伝えてきた同機であったが、ついに途中で力尽きてしまったらしく、12時24分、北緯25度17分・東経143度10分の地点(父島の南南東約 220km)で不時着した、という無線連絡を最後に、同機は一切の消息を絶つ。
南洋庁では急遽救助活動を展開し、事故発生4時間後には、たまたま附近を航行していた日本郵船の貨客船パラオ丸が、早くも現場海域に到着している。だが、現場海域は台風の影響で時化模様であり、さらに不時着したはずの飛行艇は影も形も見当たらなかった。そして、その後の3週間にわたる大々的な捜索活動にもかかわらず、同機の機体はおろか、その痕跡すらついに一切発見されなかったのである。おそらく不時着に失敗したか、あるいは、着水後に荒波のため沈没してしまったものと思われる。ちなみに、この捜索に従事していた南洋庁の瑞鳳丸は、8月29日に沖ノ鳥島を訪れ、島とその周囲を捜索している(以上、主として野口正章『パラオ島夜話』により、新聞報道、および鳥養鶴雄『大空への挑戦・プロペラ機編』, pp. 69-70 等も参照した)。
ダグラス DF (双発エンジン、全長 21.6m、翼幅 29.0m)は M-130 よりも一回り小さいが、やはり旅客飛行艇として製造されたものである。この事故は、状況によっては、たとえ飛行艇といえども、不時着から短時間のうちに痕跡を残さず沈んでしまうこともありうることを物語っている。
なお、この事故により南洋庁は内地との航空便開設を断念した(『戦史叢書 中部太平洋方面海軍作戦〈1〉』, p. 17.)。もっともその後、1938年12月に国策会社として設立された大日本航空(戦後の日本航空とは無関係)の手によって、1939年4月から川西式四発型飛行艇(九七式飛行艇)(*)による南洋線(横浜・サイパン・パラオ間)の運航が開始されている。当初は郵便輸送のみであったが、1940年3月からは旅客営業も開始された。さらに1941年1月には南洋群島内各地をつなぐ航路の定期運行も開始され、同年11月にはパラオとポルトガル領ティモール(現在の東ティモール民主共和国)のディリとをつなぐ国際線の運航も開始されたのだが、12月の対米英開戦によりすべて水泡に帰すことになる。
(*) 1934年1月に「九試大型飛行艇」として海軍から発注され、1936年7月に初飛行、1938年1月に「九七式飛行艇」(H6K)として制式採用。通称「九七大艇」。民間輸送型は「川西式四発飛行艇」と呼ばれた。
もうひとつ、今度は戦後の事例を挙げよう。1962年(昭和37)3月16日、グアム島からクラーク空軍基地(マニラの北北西約 80km)へと向かっていた、フライング・タイガー・ラインのロッキード L-1049H スーパーコンステレーション旅客機(乗員11名・乗客96名)が、フィリピン海上で行方不明となった。同機は米軍航空輸送部(MATS)の委託を受けて運航されており、乗客はヴェトナム共和国(南ヴェトナム)の首都サイゴン(現在のホーチミン)へ向かうアメリカ兵と南ヴェトナム兵たちであった。このとき、同機が飛行していたと推定される位置および時間にたまたまいた船が、何かが空中爆発して落下するのを目撃した、と報告している。しかし、1週間以上にわたる大々的な捜索活動が行われたにもかかわらず、同機の痕跡はついに何一つ発見されずに終わったのである(D・ゲロー『航空事故』, pp. 48-49)。
この事故機の航路はハワイ・クリッパーのものとほとんど同じであり、飛行艇と普通の飛行機という違いこそあるものの、失踪の状況もよく似ている。この事故の場合、現場は水深数千mの深海であり、爆発がたまたま目撃されていなければ完全な謎となった可能性が高い。
要するに、残骸が発見されなかったからハイジャックに違いない、というジャクソンの議論は、その前提からして破綻しているのである。
二式大艇が盗まれたハワイ・クリッパーを参考に製造されたというジャクソンの説にしても、その根拠は、二式大艇の設計が行われたのが失踪事件とほぼ同時期であることや、設計に多少似たところがある、という程度のことにすぎない。おまけに、類似点としてジャクソンが挙げているのは、全体の輪郭やエンジンの数や主翼のデザインなどといった、どれをとっても、わざわざ機体を丸ごと盗むまでもなさそうな点ばかりである。また、当時の日本海軍は、欧米各国の航空機を技術的参考材料として輸入していた。先述したダグラス DF 飛行艇もその一つで、事故の前年、1937年1月に輸入されている。そして、他ならぬ同機こそが二式大艇の参考材料となったのだとしている文献もある(『別冊一億人の昭和史 日本航空史』, p. 62, 鳥養『大空への挑戦・プロペラ機編』, p. 69. もっとも、設計や性能の違いを考えると、せいぜい参考資料の一つという程度の扱いであったと思われる)。
なお、アメリカ製航空機の日本への輸入が難しくなるのは、ハワイ・クリッパー失踪の直前、1938年7月1日にアメリカ国務省が「モラル・エンバーゴー」(道義的禁輸)を宣言してからのことである。これは、アメリカ国内の航空機メーカーおよび輸出業者に対し、航空機やその部品、爆弾などを「航空機を用いて民間人を攻撃している国」に輸出しないよう要請する、というものであり、直接の名指しこそ避けているものの、日中戦争に関してアメリカが行った最初の対日輸出制限措置であった。
だいたい、万一日本軍の仕業であることが暴露された場合、いったいどういう対処をとるつもりだったというのだろうか。ジャクソンはパナイ号事件(*)が穏便に処理されたことを引き合いに出して、外交上のリスクはほとんどなかった、と主張する。さらに、1938年8月24日に起こった、中国航空公司(CNAC)の香港発重慶行きダグラス DC-2 旅客機「桂林号」が、日本海軍機の攻撃を受け珠江に不時着した事件(桂林号事件。乗員・乗客17名中14名が死亡ないし行方不明)(**)を傍証として取り上げ、日本軍はそのようなことを平然としかねない組織である、と主張している。しかし、パナイ号事件に関していえば、日本政府は「誤爆」だと釈明した上で公式な陳謝を行い、さらに賠償金を支払っている。戦場での撃墜などであれば、敵軍機と誤認したなどといった釈明もできるだろうが、平時に公海上の定期航路を飛行中の民間機を軍人がハイジャックした、というのでは、釈明の余地もなにもあったものではない。さすがにいきなり開戦ということはないだろうが、外交関係の致命的な悪化はまず避けられないだろう。
(*) 1937年12月12日、南京攻略作戦中の日本海軍機が、長江を航行中のアメリカ海軍砲艦パナイ号(当時の日本では「パネー号」と表記された)を撃沈した事件。日本側の陳謝により政治的には決着したが、以後の日米関係に深い傷跡を残す結果となった(笠原十九司『日中全面戦争と海軍――パナイ号事件の真相』青木書店、1997年、等を参照)。
(**) D・ゲロー『航空テロ』は、民間機撃墜事件の筆頭として本事件を挙げている。犠牲者の中には中国財界の大物であった徐新六(浙江興業銀行董事長兼総経理)と胡筆江(中南銀行総経理・交通銀行総行董事長)が含まれていた。不時着後も機銃掃射を続けたとか、徐新六の暗殺、あるいは搭乗を予定していた孫科(中華民国立法院院長、孫文の子)の暗殺を狙ったものではないか、といった報道もなされたが、日本側は、あくまで民間機だとは気付かずに攻撃したもので、非は危険空域を飛んでいた桂林号の側にある、と主張した。なお、中国航空はパンナムの関連会社であり、桂林号の機長もアメリカ人であったため、アメリカ側からも抗議があったが、日本側は、中国航空は中国法人だから第三国が介入する筋合いはない、として突っぱねている。また、このわずか12日後の9月5日には、欧亜航空公司(ルフトハンザドイツ航空と中国側の合弁企業)の香港発昆明行きユンカース旅客機「欧亜十五号」が、飛行中に日本海軍機の攻撃を受けて不時着する(乗員乗客は全員無事)、という事件も起こっている。
ところで、「太平洋上を飛行中のアメリカ航空機に対する日本軍の秘密工作」というジャクソンの仮説からは、ハワイ・クリッパー失踪の前年に起こった、アメリア・エアハート失踪事件に関するある噂が連想される。
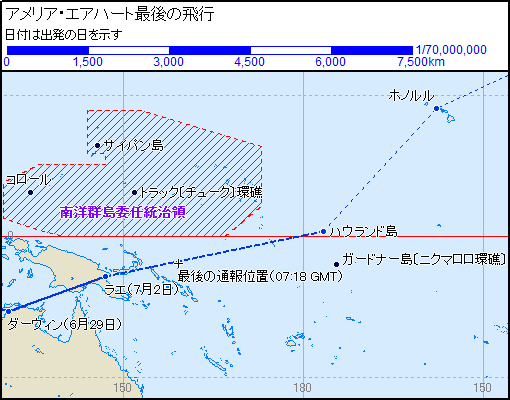
1937年、アメリカの女性飛行家アメリア・エアハート(Amelia Mary Earhart Putnam, 1897-1937? イヤハート、イアハートとも)は、ナヴィゲーターのフレッド・ヌーナン(Frederick Joseph Noonan, 1893-1937?)とともに、ロッキード L-10E エレクトラによる東回り世界一周飛行を試みた。ところが、その途中の7月2日、彼女たちは北東ニューギニア(当時オーストラリア委任統治領、現在はパプアニューギニア領)のラエから中部太平洋のハウランド島(アメリカ領)を目指して飛び立ったまま、消息を絶ってしまったのである。
アメリカ政府は、この世界一周飛行にあたって、ハウランド島に滑走路を整備するなど全面的な支援を行っていた。だが、失踪直後からアメリカ海軍による大々的な捜索が行われ、さらに日本海軍も捜索に協力したにもかかわらず、ついに何の手がかりも発見されなかった。アメリアは、1932年5月に女性としてはじめて大西洋単独横断飛行に成功、また1935年1月にはホノルルからカリフォルニア州オークランドまでの単独飛行に成功するなど、数々の業績を残している。だが、彼女が航空史上最も有名な女性パイロットとして不滅の地位を築くことになったのは、皮肉というべきか、この失敗に終わった最後の飛行によってであった。
戦争中の1943年(昭和18)、アメリアをモデルにしたプロパガンダ映画『自由への飛行』(Flight for Freedom. ロウター・メンディス監督)が公開された。この映画では、ロザリンド・ラッセルの演じるヒロインの女性パイロットが、海軍の密命を帯びて偵察飛行を試みる、という設定になっていた。この映画の影響などもあり、戦時中から戦後にかけ、アメリアについてのひとつの伝説が幅広く信じられるようになる。すなわち、彼女は南洋群島委任統治領偵察の密命をおびたスパイであったのだが、南洋群島附近を飛行中に日本軍に捕獲された、というのである。しかし、その確実な裏付けは何ひとつ存在しない(*)。
(*) そもそも、ラエから南洋群島委任統治領上空を飛んだのちにハウランド島に到達するには、十分な燃料と時間的余裕が必要なのだが、ラエでの出発時刻と搭載燃料の量から、そのような余裕はなかったことが判明している。また、当時の海図に記載されていたハウランド島の位置は不正確で、アメリアが島を見失う可能性は決して低いものではなかった。そうしたことから、実際には、島を見失ったまま燃料切れで海中に墜落したか、あるいは別の無人島に不時着したとする説が有力である。なお1992年には、アメリカの民間調査機関「TIGHAR」が、アメリアはフェニックス諸島(当時イギリス領、現在はキリバス領)の無人島ニクマロロ環礁(旧称ガードナー島)に不時着し、救助を待つうちに脱水症状で死亡したとする説を発表した。青木冨貴子『アメリアを探せ 増補改訂版――甦る女流飛行家伝説』(文春文庫、1995年)他を参照。
ジャクソン自身は、アメリアについては単なる事故として片づけているのだが、彼の説は、日本軍捕獲説を信奉する一部の研究家を刺激することになった。『消された飛行艇』の発行直後に、元アメリカ空軍将校でアメリア・エアハート研究家のジョー・ジャーヴェイス(Joseph L. "Joe" Gervais)が、ハワイ・クリッパーはハイジャックされたのちに(パラオではなく)トラック諸島(チューク環礁。現在はミクロネシア連邦領)に降ろされ、乗員・乗客は全員その場で殺害された、とする説を唱えはじめたのである。
ジャーヴェイスは、1964年11月にトラック諸島を訪れたときに、現地の住民から、15人のアメリカ人が日本人に殺害され、デュブロン島(Dublon. トノアス島 Tonoas. 委任統治領時代は「夏島」と呼ばれ、トラック支庁が置かれていた)の病院の下に埋められた、という話を聞いたのだという。『消された飛行艇』を読んだ彼は、この証言こそがハワイ・クリッパーとその乗員・乗客の最期を語ったものだと考えたのである。さらに彼は、トラック諸島の礁湖に沈んでいた航空機の残骸を撮影した写真を、ハワイ・クリッパーの機体ではないか、として公開した。もっとも、この残骸は M-130 ではないことがすぐに明らかとなった。じつは、彼はこのたぐいの誤認騒ぎをしばしば引き起こしており、その調査能力にはあまり信用のおけない人物なのである(*)。だいたい、トラック諸島はグアムの南東で、マニラとは全くの逆方向である。なぜそんな遠回りをする必要があるのだろうか。
(*) たとえば、1970年に、ニュージャージー州に住むある女性がアメリア本人だ、と主張する書籍(ジョー・クラース『アメリア・エアハートは生きている』 Joe Klaas, Amelia Earhart Lives. 未訳)が出版され、直後に名指しされた女性本人から訴えられるという騒ぎが引き起こされているが、この説の言いだしっぺこそが他ならぬジャーヴェイスなのである。また、彼は1991年9月にはロリン・ライネックと共同で「アメリアがサイパンに連行されてきたときの写真」なるものを発表したが、これも、実際には失踪前にハワイで撮影された写真であることが判明している(中島洋「イヤハート事件は解決した」『太平洋学会誌』第55・56号、1992年9月)。
さらに2000年(平成12)には、チャールズ・N・ヒル(Charles N. Hill, 1941-)というアメリア研究家がジャーヴェイスの説を推し進め、『日章旗の針路――1938年のクリッパー・ハイジャック、そして究極の戦闘中行方不明者たち』(Fix on the Rising Sun: The Clipper Hi-jacking of 1938 — and the Ultimate M.I.A.'s. 未訳)という著書を発表した。
ヒルは、ハイジャックの証拠としていくつかの証言を取り上げている。たとえば、ジョン・タワーズ提督(John Henry Towers, 1885-1955)がトリップ社長に伝えたという話によれば、ゼロ・ファイター、すなわち海軍零式艦上戦闘機(零戦)の発電機のハウジング(覆い)に、ハワイ・クリッパーの発電機のハウジングに刻印されたシリアル・ナンバーと同じものが刻印されていたという。また、リチャード・サザーランド中将(Richard Kerens Sutherland, 1893-1966)が、遺族の一人であるエドナ・ワイマン(Edna Wyman. エドワード・ワイマンの妻)に伝えたという話によれば、戦後、ハワイ・クリッパーのエンジンが日本で回収されたという。さらにヒル自身も、海兵隊の諜報員だったという人物から、1945年に横須賀でハワイ・クリッパーの機体を目撃した、という話を、1997年に聞いたという。いずれもあやふやな話で、写真などの物証があるわけでもないのだが、ともかく、こうした証言などをもとにして、ヒルは、ハワイ・クリッパーの機体はひそかに日本国内に運ばれて分析され、そのエンジンは零戦に流用されたのではないか、と推測している。
ヒルは実行犯も名指ししている。海軍軍人の源田実(げんだ・みのる)(1904-89)(*)である。機密保持の関係から、実行犯は現役軍人である必要があるが、その点、源田は優秀なパイロットであり、しかも西洋人のような体格と容貌の持ち主なので、グアム島への潜入も容易だった、というわけである。ヒルの主張によれば、アメリア・エアハートは源田実の手引きによって日本に亡命し、彼女のもたらしたヒューズ H-1 (**)の資料に基づいて、海軍は零戦を設計した。しかし、適切なエンジンがなかったので、ハワイ・クリッパーをハイジャックすることになったのだ、という。
(*) 1938年8月当時は横須賀海軍航空隊(横空)飛行隊長、海軍少佐。「源田サーカス」と呼ばれた曲芸飛行で人気を博した。のちに第1航空艦隊航空参謀として真珠湾攻撃・ミッドウェイ海戦などを指揮。特攻戦術の発案者の一人でもある。戦後は航空幕僚長、参議院議員を歴任した。ちなみに、 Fix on the Rising Sun はジャーヴェイスと源田実に捧げられている。
(**) Hughes H-1 Racer. ヒューズ・エアクラフト社が1935年に製造した航空機。ハワード・ヒューズ(Howard Hughes, 1905-76)自らの操縦による世界速度記録(566 km/h, 1935年)と北アメリカ大陸横断速度記録(7時間28分25秒、1937年)を樹立している。しばしば零戦との設計上の類似性を指摘されており、ヒューズ自身も零戦は H-1 のコピーだと主張していた。
1938年8月7日付『ニューヨーク・タイムズ』紙は、かんべら丸がアメリカ側の依頼に応じて沖ノ鳥島に向かったことを報じるとともに、「機体発見」「乗員乗客全員死亡」という東京発の誤報が、アメリカの一部のラジオや新聞で流されたことを報じている。この記事をもとに、ヒルは次のようなものすごい迷推理を展開する。ハワイ・クリッパーはトラック諸島で日本海軍機に偽装され、給油のためにいったんマリアナ諸島のパガン島に運ばれた。その後、伊勢湾に運ばれる手はずとなっていたが、台風が接近してきたために沖ノ鳥島で足止めを食らうことになった。アメリカ側は潜水艦によってこの事実をひそかに察知したが、戦争の準備が整っていなかったため、あえて真相を暴露することを避けた。しかし、日本側に対する警告のため、わざと沖ノ鳥島附近を捜索するように要請したのである。あわてた日本側は、機体と全員の遺体が発見されたと発表したが、これはアメリカ側によって「誤報」にすり替えられた……。
念のために書いておくが、沖ノ鳥島に飛行艇が離着水できる設備などない。だいいち、沖ノ鳥島は礁湖が浅く、着水には適さないのである。
そもそも、 M-130 のエンジンは、プラット・アンド・ホイットニー(P&W)社の「ツイン・ワスプ」(Pratt & Whitney R-1830 Twin Wasp)である。このエンジンはべつに特殊なものではなく、ベストセラー旅客機として知られるダグラス DC-3 をはじめ、コンソリデーテッド PBY カタリナ飛行艇やグラマン F4F ワイルドキャット戦闘機など、数多くの飛行機に用いられたものなのである。確かに、零戦のエンジンである中島飛行機(富士重工業の前身)の「栄」(さかえ)が、このツイン・ワスプと良く似ていることはしばしば指摘されている。しかし、先述したように、そもそも1938年前半まではアメリカ製航空エンジンの輸出制限は行われていなかったのである。飛行艇一機をさらってくる必要性などないのだ。ついでに言えば、「栄」が制式採用されたのは1939年だが、その設計が始まったのは1933年、原型となる「海軍10試空冷」が完成したのは1936年3月のことである(中川+水谷『中島飛行機エンジン史』)。
いずれにせよ、ハワイ・クリッパーの失踪に日本軍が関与したとする説は根拠薄弱な陰謀論にすぎない、と言ってよさそうである。
それでは実際のところ、ハワイ・クリッパーにいったい何が起こったのか?
異常事態を知らせる無線連絡が全く無かったことと、最後の交信の直後にとつぜん応答しなくなったことからみて、おそらく、最後の交信の直後に突発的かつ致命的な異常事態に襲われ、海中に墜落した、とみるのが妥当なところであろう。とはいうものの、飛行機が異常事態を伝えぬままとつぜん墜落してしまうのはさほど珍しいことではなく、これだけのことから何かを推測することは困難である。悲運の飛行艇の運命は、今日となっては永遠の謎というほかないのかもしれない。
M-130 の残りの2機も、のちに悲惨な運命をたどることになる。1941年(昭和16)12月に日本とアメリカの戦争が始まると、太平洋横断航路の運航は停止され、両機は海軍に軍事徴用された。フィリピン・クリッパーは、1943年(昭和18)1月21日、悪天候の中でサンフランシスコ北方の山に衝突。そしてチャイナ・クリッパーも、1945年(昭和20)1月8日、マイアミからベルギー領コンゴ(現在のコンゴ民主共和国)の首都レオポルドヴィル(現在のキンシャサ)へと向かう途中、カリブ海のトリニダード島(当時イギリス領、現在はトリニダード=トバゴ共和国領)のポート・オブ・スペインで、着水に失敗し墜落してしまう。
3機の M-130 がすべて失われたことは、旅客飛行艇時代の終わりを暗示するものでもあった。第2次世界大戦によって航空技術が飛躍的な進展を遂げ、陸上機の大型化が進んだことにより、飛行艇の有利さは失われ、むしろ、水上であればどこにでも離着水できるとはいっても、実際には水面が安定していないと難しいことや、機体のデザインが限定されるため高速化が難しいこと、といった短所の方が顕在化することになってしまったのである。パンナムは1940年代末までに飛行艇の運航を停止し、代わってダグラス DC-4 やロッキード L-049 コンステレーションなどの大型レシプロ旅客機を採用することになる。
ちなみに、かんべら丸は軍に徴用されたのち、1942年(昭和17)11月14日、第3次ソロモン海戦(ガダルカナル海戦)において空爆のため撃沈されている。また、メイグスは1942年2月19日のダーウィン(オーストラリア)空襲で日本軍に撃沈されている。
パンナムは、戦後もアメリカを代表する民間航空輸送の名門として君臨し続けたが、1980年代に経営が悪化し、ついに1991年(平成3)12月に破産、64年の歴史に幕を閉じた。その後、「パンナム」の商標はいくつかの小さな航空会社を転々としたが、2008年(平成20)2月を最後に航空界から姿を消している。
ダグラス DF について
関連して
※地図の作成にあたっては、世界地図描画ソフト PTOLEMY を使用させていただきました。