



7世紀初頭、メッカのアラブ商人ムハンマド(570頃-632)は、ユダヤ教・キリスト教の強い影響のもとに、唯一神(アッラー)に対する絶対の帰依をその信仰の柱とする新宗教、イスラームを創唱した(「イスラ(ー)ム」それ自体が宗教の名なので、「イスラム教」と表記するのは厳密には誤り)。彼の没後、ハリーファ(カリフ)と呼ばれたその後継者たちは、西アジアから北アフリカにかけて広大なイスラーム国家を築き上げることになる。また、アラビア語で書かれたイスラームの聖典『クルアーン』(コーラン)は、神の啓示ゆえに翻訳してはならないものとされた。このため、アラビア語はイスラーム世界の共通語として広まることになる。
初期のカリフはムハンマドの弟子筋から選ばれていたが、661年にカリフに即位したウマイヤ家のムアーウィヤ1世は、ダマスクスを首都とし、カリフの地位を世襲化させた(ウマイヤ朝、661-750)。その後、ムハンマドの叔父アッバースの子孫であるサッファーフ(アブー・アルアッバース)は、750年にウマイヤ朝を滅ぼして自らカリフの位に就き、バグダードを首都とするアッバース朝(750-1258)を築きあげる。
インド洋を中心としたイスラーム圏の交易ネットワークは、このアッバース朝において本格的に機能し始める。その範囲は、西はアフリカ南東岸、今日のタンザニア・モザンビーク一帯から、東は中国にまで及んでいた。唐代(618-907)や宋代(960-1279)の中国側史料では、アラビアやアラブ人は「大食」(たいしょく)と表記されている(ペルシア語でアラビア人を指すターズィーク Tāzīk [Tazik] ないしターズィー Tāzī [Tazi] の音訳と考えられている)。そして、イスラーム教徒(ムスリム)の船乗りたちや商人たちは、この交易圏の各地で見聞したことを、多くのアラビア語文献に書き残している。
ところで、9世紀以降のアラビア語文献には、アジアの東の果てにあるらしい、黄金を豊富に産出する「ワークワーク」(Wāqwāq [Waqwaq]; ワクワク、ワクワーク)ないし「ワーク」(Wāq [Waq]; ワク)、および「シーラ」(Shīla [Shila]; シラ)ないし「シーロ」(Shīlo [Shilo]; シロ)なる島についての記事が現れる。
ワークワークについて記された現存最古の文献は、9世紀半ば、アッバース朝の第15代カリフ、ムータミド(在位870-892)に仕えていたイブン・フルダーズビフ(Ibn Khurdādhbih [Ibn Khurdadhbih], 820頃-912頃。イブン・フルダーズベ Ibn Khurdādhbeh [Ibn Khurdadhbeh] などとも表記する)の記した地理書『諸道諸国誌(諸道路と諸国の書)』(Kitab al-Masalik wa I-mamalik)である。
シナ(al-Ṣīn [al-Sin])[中国]の東方にはワークワークの国(bilād al-wāqwāq [bilad al-waqwaq])がある。黄金に富むため、その住民は犬の鎖や猿の頸輪にまで黄金を用い、黄金で織った衣服をもってきて売るほどである。ワークワークではまた良質の黒檀[こくたん。インドや東南アジアに産するカキノキ科の木で、黒色の心材を持つ]を産する。
シナの果て、カーンスー(Qānṣū [Qansu])(杭州または揚州)に向き合って、シーラー(bilād al-shīlā [bilad al-shila])という山がちで多くの王のいる国があり、そこではあまたの黄金を産する。イスラム教徒でこの国に入った者は皆、その(環境の)良さのためそのまま住み着いてしまう。(杉田英明『日本人の中東発見』, p. 35)
ここでは、ワークワークとシーラはともに中国の東方海上にあり、いずれも黄金を豊かに産するとされている。特にワークワークでは、犬をつなぐ鎖や猿をつなぐ首輪まで金で造られているという。後世の文献ではさらにこれがエスカレートして、ワークワークでは金で作られたレンガで城や宮殿を建てるといい、あるいはワークワークでは鉄が採れないため、鉄は他国における金と同じくらい尊重される、などといわれるようになる。
また、10世紀後半にブズルク・イブン・シャフリヤール(Buzurk b. Shahriyār [Buzurk b. Shahriyar])という船主が、ムスリムの船乗りたちの語った物語を集めて記した『インドの不思議』(Kitāb ‘Ajā'ib al-Hind [Kitab Aja'ib al-Hind])という書物には、ワークワークに生えているという不思議な樹の話が載せられている。
ムハンマド・イブン・バービシャードがワクワークに入国したことのある者の話として語ってくれた話です。
――そこには長丸い葉をした大木が生えていますが,この木は瓢箪に似た,それより大きい実を結びます。その実は人間の形をしていて,風に揺れると,声を立てるのです。その中はウシャルの実のようにからっぽになっていて,木から切り離すと,たちまち気が抜け,しぼんで皮だけになってしまいます。ある水夫がその実を見て,気に入った形のものを選んで,持って行こうと木から切り取ったところ,気が抜けてカラスの死骸のようなものが後に残っただけでした。
この、人間そっくりな実のなる奇怪な樹は、「ワークワークの樹」(ワクワクの木)として広く知られている。
 |
| 『ブルハーンの書』第41葉。制作地バグダード、1399年。オクスフォード、ボードリアン図書館所蔵。小林一枝『『アラビアン・ナイト』の国の美術史』, p. 140. |
また同書によれば、ワークワークには火の中に入っても焼け死なず、土だけ食べて何日も生きていられる「サマンダル
」(samandal)という鳥や、性転換をする「兎に似た獣
」がいるという。またワークワークの住民は「工芸にかけては神の創造したもうた人間の中で最も器用
」だが、同時に「謀反,狡猾,嘘言の民で,しかも凶悪極まりなく,何事においても大胆不敵
」だという。もっとも、この書物は船乗りの自慢話やホラ話の集成みたいなものなので、その信憑性となるといささか眉唾物ではある。
ついでながらこの書物には、スヴァルナドヴィーパないしスヴァンナブーミと思しき「黄金の国」(Bilād al-dhahab [Bilad al-dhahab])という地名も登場する。
なお、「ウシャル」(‘ushar [ushar])というのは、アジア・アフリカの熱帯地域の乾燥地に広く分布するガガイモ科の低木で、学名をカロトロピス・プロケラ Calotropis procera という。この木の実はいっぷう変わっていて、大きさはミカンよりやや大きい程度だが、実はその中には綿毛のついた小さな種が入っているだけで、果肉などはなく、あとは空気しか入っていない。熟すると実が裂けて、中から種が出てくるのである。なお、ヨセフス『ユダヤ戦記』(第4巻第8章第4節)やタキトゥス『歴史』(第5巻第7章)などによれば、死海のほとり、神の怒りに触れて焼き滅ぼされたソドムの町(《創世記》19)があった土地に産する植物は、手で触れればたちまち煙を発して灰と化してしまうという。この「ソドムのリンゴ」の正体は、一説にこのカロトロピス・プロケラの実だといわれている。
この「ワークワークの樹」の伝承は、すでに9世紀のジャーヒズ(al-Jāḥiẓ [al-Jahiz], 776頃-868/9)の『動物の書』(Kitāb al-ḥyawḥn [Kitab al-hyawhn])に「ある種の植物と動物のあいの子」として記載されているという。また博物学者カズウィーニー(al-Qazwīnī [al-Qazwini], 1203-83)は、『諸国の遺跡』(Āthār al-Bilād [Athar al-Bilad])という書物の中で、「ワークワーク」という島名の由来について、
そこには女の形をした実のなる樹木があって、彼女たちは髪の毛で木にぶらさがっている。実が熟すると「ワークワーク」という声がそこから聞こえ、この国の住民はその声を不吉な前兆と受け取る。(杉田英明『日本人の中東発見』, p. 41)
と述べている。どうやらこの実は、古くは「人間の頭に似た実」とされていたものが、いつの間にか「人間そのものに似た実」ということになり、さらに「人間の女性に似た実」ということにされてしまったらしい。
動物を産む植物、ないし動物と植物の合体した生物についての伝説は、古来、世界各地に様々な形で伝えられている。この「ワークワークの樹」は、「マンドラゴラ」(*)や「スキタイの羊」(**)などとともに、その代表格として知られている。
(*) 学名 Mandragora officinarum. 英語名マンドレイク(mandrake)、ドイツ語名アルラウネ(Alraune)。実在するナス科の多年草で、有毒だが薬用にも用いられる。多肉質の根が二股に裂けた形が人間の姿を連想させることから、様々な伝説が生じた。野性のマンドラゴラを引き抜こうとすると悲鳴をあげ、それを聞いたものはたちどころに命を落とす、という話は有名。『旧約聖書』には「恋なすび」の名で、媚薬として登場する(《創世記》30:14-16、《雅歌》7:14)。なお「マンダラゲ」(曼陀羅華)と訳されることがあるが、本来、曼陀羅華とは仏典に現れる天界の花のことであり、また同じナス科の薬用植物チョウセンアサガオ Datura metel の別名でもあって、適切な訳名とはいえない。
(**) 「タタールの羊」「バロメッツ」(Barometz)などともいう。東洋に産する、子羊を実として産むという伝説上の植物。その正体については、ワタの木説、タイラギ(二枚貝の一種)説などがある。また、かつて、東アジア産のタカワラビ(一名ヒツジシダ) Cibotium barometz というシダ植物が、その根茎を加工すると羊そっくりになることから、この植物の正体だと考えられていたこともある。しかし、この説は今日では疑問視されている。ヘンリー・リー+ベルトルト・ラウファー/尾形希和子+武田雅哉〔訳〕『スキタイの子羊』(博品社、1996)に詳しい。
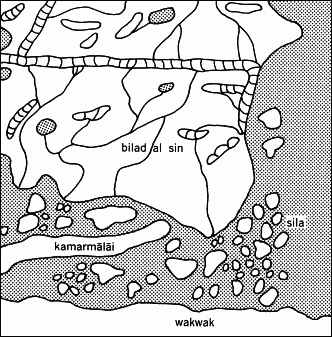 |
| 織田武雄『古地図の博物誌』, p. 69 より引用。南側(下)の陸地がワークワーク。 |
また、ワークワークは地図にも描かれている。ノルマン朝シチリア王国(イタリア半島南部およびシチリア島を支配したノルマン系の王国。1130-94)の国王ロゲリウス(ルッジェーロ)2世(在位1130-54)に仕えていた地理学者イドリーシー(al-Idrīsī [al-Idrisi], 1100-65/6)は、王のために作った地理書『世界横断を望む者の慰みの書』(Nuzhat al-Mushtāq fī Ikhtirāq al-āfāq [Nuzhat al-Mushtaq fi Ikhtiraq al-afaq], 1154。通称『ルッジェーロの書』 Kitāb al-Rujāri [Kitab al-Rujari])に収録した世界図の中で、「シンの国」(bilād al-Sin [bilad al-Sin])すなわち中国の南方にワークワークを描いている。
イドリーシーの地理観では、アフリカ大陸の東海岸は途中で大きく東へと曲がっており、その先端は中国と多島海を挟んで対峙していることになっている。シーラはこの多島海の中の島々として、そしてワークワークはアフリカの延長である陸地の中にある国として描かれているのである。ワークワークは島だとされることが多いが、他にも様々な見解があったようである。
なお、アフリカ大陸の東海岸が中国の近くまで来ているのは、プトレマイオスの影響だといわれている。プトレマイオスは、アフリカの南端とアジアの東端は接続しており、インド洋は内海になっていて他の海とは接続していないと考えていた。この重大な誤りは、イスラーム世界においては、9世紀の数学・天文学・地理学者フワーリズミー(al-Khwārizmī [al-Khwarizmi], 800?-47?)によって訂正されている。しかし、その影響はしぶとく残り続けたのである。
このワークワークと、そこに産する不思議な樹は、かの『千一夜物語(アラビアン・ナイト)』(Alf Layla wa Layla)(*)にも登場している。一般に「バスラのハサン」として知られる物語の後半がそれである(**)。
(*) 『千一夜物語』のアラビア語原典の刊本としては、ブレスラウ版(1825-43)、ブーラーク版(1835)、カルカッタ第2版(1839-42)などがある。また仏訳としてガラン版(1704-17。最初のヨーロッパ語訳。一部出典不明の物語を含む)、マルドリュス版(1899-1904。ブーラーク版を底本としていると称するが、実際はかなりの歪曲や創作を含んだ翻案)、英訳としてペイン版(1882-89。カルカッタ第2版による最初の英語完訳)、バートン版(1885-88。カルカッタ第2版の完訳、実はペイン版の剽窃)などが有名である。前嶋信次+池田修〔訳〕『アラビアン・ナイト』(平凡社東洋文庫、1966-92)はカルカッタ第2版の完訳。また豊島与志雄+他〔訳〕『千一夜物語』(岩波文庫)・佐藤正彰〔訳〕『千一夜物語』(ちくま文庫)はマルドリュス版、大場正史〔訳〕『バートン版 千夜一夜物語』(ちくま文庫)はバートン版の訳。
(**) 東洋文庫版では「商人と金細工師と銅細工師を営むふたりの息子、および金細工師の息子ハサンとペルシア人の詐欺師にまつわる物語」という題で第15~16巻に収録、第778~831夜。以下の引用は同書による。なお、マルドリュス版では第576~615夜となっており、「ワークワーク」を鳥の鳴き声とするなどの差異がある。
――バスラ(シャット=アル=アラブ河の河口近くにある港町。現・イラク領)の金細工師ハサンは、あるとき、魔界から鳥の羽根の衣をまとった十人の美女たちが飛んできて、衣を脱いで水浴びをしているところをのぞき見てしまう。その中の長をつとめる乙女に一目惚れしてしまったハサンは、彼女の衣を盗んで魔界に帰れないようにし、自分の妻としてしまった。ハサンは妻や母とともにバグダードに移り住み、妻はハサンのこどもを二人もうける。ところがあるとき、ハサンがたまたま家を留守にしていたところへ、時のカリフの正室であるズバイダ妃(*)が、ハサンの妻の美貌の噂を聞きつけ、彼女を宮廷に呼び出した。すると彼女は、ズバイダ妃を巧みに言いくるめて、ハサンの母から衣を取り返し、こどもたちを連れて魔界へと飛び去ってしまう。このとき彼女は姑に向かって、
「私に親しく会いたくなられたなら、恋にあこがれるそよ風に誘われて、ワークの島じま[jazā'ir wāq [jaza'ir waq]]に私をお訪ね下さるよう[ハサンに]お伝え下さい」
と言い残した。ワークは七つの島からなる魔境で、彼女はワークの大王の娘だったのである。ワークという名は、この国に生える、「アダムの子ら(人間)そっくりの枝
」を持ち、日の出と日没の際に「ワーク、ワーク、まことに創造主にして主権者たる神は讃うべきおかたなり
」と叫ぶ樹に由来するという。また、ワークの住民はそのほとんどが女人という。ハサンは妻とこどもたちを取り戻すため、命がけでワークの島々へと乗り込む――
(*) Zubayda. 実在の人物(762/3-831)。アッバース朝第5代カリフ、ハールーン=アッラシード(在位786-809)の正妃で従姉。夫のハールーンはアッバース朝の最盛期を築き上げたとされる人物で、『千一夜』の登場人物としても有名。彼女も夫とともに何度も登場する。
ここでは、ワーク(ワークワーク)は女たちの棲む魔境とされており、この話はある種の女人国譚ともなっている。なお、ここでは話を簡単にするためにかなり省略したが、実際には話の筋はもっと複雑で、『千一夜』の中でも有数の異界冒険譚のひとつである。ついでながら、お気づきかと思われるが、この話は日本の羽衣伝説(天人女房譚)と同工異曲である。この形の説話は「白鳥処女説話」と呼ばれ、ほとんど全世界に分布している。
なお、同じ『千一夜』中の、有名な「船乗りシンドバッド」――正確には「海のシンドバードと陸のシンドバード」――のこども向けの翻訳の中には、その冒頭、シンドバードがインド洋の広さについて述べているくだりで、「アビシニア(エチオピア)からヴァクヴァク(Vakvak)諸島まで」云々、と語っているものがある。この「ヴァクヴァク」はワークワークのことである。これは、『千一夜』を最初にヨーロッパに紹介したアントワーヌ・ガラン(Antoine Galland, 1646-1715)のフランス語訳(1704-17)の中に、そのような記述があることに由来するようである(*)。
(*) カルカッタ第2版を底本とする東洋文庫版やバートン版などには、この記述はない。
それでは、このワークワーク、及びシーラの実体は何だろうか。
フランスの東洋学者ジョゼフ・トゥサン・レイノー(Joseph Toussaint Reinaud, 1795-1867)やイギリスの東洋学者ヘンリ・ユール(Henry Yule, 1820-89)など、比較的早い時期の研究者たちは、シーラは日本列島だと考えていた。しかし、「シルクロード」の命名者として有名なドイツの地理学者フェルディナント・フォン・リヒトホーフェン男爵(Ferdinand Freiherr von Richthhofen, 1833-1905)はこの説を否定し、シーラは朝鮮半島だとする説を唱えている。なお、アラビア語では「島」も「半島」もどちらも「ジャズィーラ」である(余談ながら、有名なカタールの衛星テレビ局「アルジャジーラ」(アル・ジャズィーラ)の名は、アラビア半島にちなんだものである)。
いっぽう、ドイツの東洋学者マクシミリアン・ハビヒト(Maximilian Habicht, 1775-1839)は、1825年に刊行した『千一夜』ドイツ語訳の註釈において、ワークワークは日本だ、とする説に触れている。また、その後に刊行された『千一夜』の註でも、この説を紹介しているものが少なくない。日本でも、井上勤〔訳〕『全世界一大奇書――原名アラビヤンナイト』(1883)(『千一夜』の邦訳としては、永峰秀樹〔訳〕『開巻驚奇 暴夜[あらびや]物語』(1875)に次ぐもの)の「船乗清土婆奴の話説」(「海のシンドバード」の本邦初訳)に、
ウパクウパク群島(此等の群島は亜良比亜[アラビア]人の説に依るに遠く支那の東にあり其の斯[かゝ]る名を負ひたる所以は同名の木実[このみ]を生ずる樹木より斯くは呼び来りしなりと云ふ今考がふれば即はち日本群島なること疑がひなし)
という記述がある。これは底本の註をそのまま写したもののようである。
1880年、オランダの東洋学者ミヒール・ヤン・ド・フーイェ(Michael Jan de Goeje, 1836-1909)は、以上の議論を整理した上で、ワークワークとは「倭国(わこく)」すなわち日本であり、シーラは「新羅(しんら)」すなわち朝鮮である、とする説をあらためて提唱した。
「倭」(わ)とは、もともと中国において、現在の日本列島一帯とその地に住む人々を指して呼んだ名である(現在の日本国や日本列島の範囲とは完全には一致せず、朝鮮半島南部の住民なども含まれていたとする説もある)。「倭」の王朝(ヤマト王権)は7世紀に自国のことを「日本」と名乗るようになるが、それまでは「倭国」を対外向けの正式な国号として用いていた。「日本」がいつ正式な国号として定められたのかについては諸説あるが、近年では天武・持統朝(673-97)だとする説が有力となっている。また本来、「日本」とは地名でもなければ民族名でもなく、「倭」の王朝(つまり天皇の王朝)の名であったと考えられている(吉田孝『日本の誕生』(岩波新書、1997)等を参照)。その後も「倭」は、日本・日本人の異称として長く用いられ続けた。
また、新羅(韓国語ではシルラ Silla。日本では「しらぎ」と呼びならわしている)は朝鮮半島に栄えた王朝(356?-935)である。朝鮮半島では、4世紀に北部に高句麗(コグリョ/こうくり)(前37?-668)、西南部に百済(ペクチェ/ひゃくさい/くだら)(4世紀~660)、東南部に新羅の三国が分立し、抗争を繰り広げた。7世紀半ばに唐が朝鮮半島に侵攻すると、新羅は唐といったん同盟して、百済と高句麗をあいついで滅亡に追い込んでいる。しかしその後、新羅と唐とは対立関係に転じ(羅唐戦争、670-76)、676年に唐は半島から撤退、百済の旧領と高句麗の旧領の一部が新羅の支配下に入った。これ以後の新羅は「統一新羅」と呼ばれる。ただし、その支配範囲は大同江以南にとどまっており、またその北方には、高句麗の遺民により建国された渤海(バルヘ/ボーハイ/ぼっかい)(698-926)があった。
余談ながら、新羅の首都は「金城」(クムソン)という。現在の慶州(キョンジュ)である。また、新羅の王室も金氏である。新羅時代の古墳からは純金製の金冠をはじめ、金製品が多く出土している。一説に、「シルラ」という国名自体も古代韓国語で「金」を意味するという。
桑原隲蔵(くわばら・じつぞう)(1870-1931)など日本の東洋史家の多くもこのフーイェ説を採用しており、今日ではこの説がいちおう通説とみなされている。また、経済史家の内田銀蔵(1872-1919)はこの説を修正して、シーラは本来新羅のことだが、のちにワークワーク=日本と混同されたとする説を唱えている。
確かに、日本や新羅に関する情報が、直接ではないにしても中国を経由してイスラーム世界に伝わっていたことは十分に考えられる。
また、「大食」すなわちアラビアの使節が、日本の遣唐使や新羅の使節と唐の宮殿で同席したことも記録に残されている。すなわち、『続日本紀』(天平勝宝六年正月丙寅条)によれば、唐天宝十二載(753)正月、長安(現在の西安)の大明宮含元殿で、玄宗皇帝(在位712-56)を前にして朝賀の儀が行なわれた。このときの席次は、西側の第一が吐蕃(とばん)(現在のチベットにあった国。620年代~843)、第二が日本、東側の第一が新羅、そして第二が「大食国」という順序であったという。この「大食」の使節とは、おそらくアッバース朝の使節と思われる。「大食」の語は、日本の文献記録においてはこの記事が初出とされる。ちなみに、この件が記録に残されているのは、この際に、新羅が日本より上席となっていることに対して遣唐副使の大伴古麻呂(?-757)が抗議し、日本が東側の第一となるよう席次を変更させた(と、少なくとも古麻呂は帰国後に朝廷に報告している)からである。
なお、この説が正しいとすれば、イドリーシーの地図は、西方世界の地図としては日本の描かれた現存最古の地図ということになる。
ちなみに、イブン・フルダーズビフが『諸道諸国誌』を記したのは、日本史でいえば平安時代前期にあたる。ちょうど、藤原良房(804-72)とその養子の基経(836-91)が摂関政治の基礎を築き、また菅原道真(845-903)が活躍をはじめた時期である。また、イドリーシーの地図が製作されたのは平安時代末期、ちょうど保元の乱(1156)の直前である。
しかし、シーラが新羅だとする説についてはあまり異論はないものの、ワークワークが日本だとする説については異論も少なくない。特に、フランスの東洋学者ガブリエル・フェラン(Gabriel Ferrand, 1864-1935)は、ワークワーク=日本説を否定して、アラビア語文献によればワークワークは東方と南方に二つあると指摘し、東のワークワークはスマトラ島、南のワークワークはマダガスカル島だとする説を主張している。なお、スマトラ・ジャワ両島(この二つの島は、この時代にもなおはっきりとは区別されていなかったらしい)は、アラビア語では「ザーバジュ」(Zābaj [Zabaj]. 語源は不明)という名で知られていた。
フェランは「ワークワーク」の語源として、スマトラ島北部のトバ湖周辺に住むバタク族(Batak)の中の一グループである「パクパク」(Pakpak)、マダガスカル語で「人々・臣民・国民・部族・氏族などの全体」を意味する「ヴァフアク」(vahwák)という言葉、それにマダガスカルに自生する「ヴァクワ」(vakua, vakwá)というタコノキ(パンダヌス)属 Pandanus の植物の名を挙げている。
タコノキ属の植物は、マダガスカル島やスマトラ島を含め、熱帯の海岸に広く分布しており、日本でも南西諸島にアダン P. odoratissimus、小笠原諸島にタコノキ P. boninensis が自生している。この果実はパイナップルに似た楕円形で、枝からぶら下がり、人間の頭くらいの大きさになる。この果実は、小さな果実がいくつも集まってできた集合果で、熟すると小果実がばらばらになって落ちる。フェランはこの果実が伝説上のワークワークの樹を連想させる、としている。
ちなみに、マダガスカル島民は言語的にも文化的にもインドネシアやマレーシアの住民と多くの共通点が指摘されており、もともと、ある時期に東南アジアから移住してきたものと考えられている(なおフェランは、このことも自説の根拠として挙げている)。ただし、それがいつのことであったか、ということになると、1世紀頃とする説から10世紀頃とする説まで諸説紛々であって、いまだ定説がない。また、東南アジアからは 6000km ないし 8000km も離れたこの島に、彼らはいったいどのようにして、どのような経路で渡ってきたのか、ということも大きな謎とされている。
確かに、諸文献中のワークワークを全て日本だと考えると、あちこちに矛盾が生じてしまう。そもそも最初のイブン・フルダーズビフの記事にしてからがすでに問題があって、彼がワークワークの特産品として挙げている黒檀は熱帯産の樹であり、日本には産しないのである。
また、『インドの不思議』にはこのような記事もある。
イブン・ラーキースはワクワークの住民が引き起した驚くべき事件について語ってくれましたが,この話は彼や他の者たちも目撃している事件なのです。
――334年〔AD. 945/946〕ワクワークの住民が千艘あまりもの小舟に分乗してカンバルフの町[Qanbaluh; アフリカ東海岸の港町。ザンジバル島説とマダガスカル島説がある]に押し寄せて来ると,そこの住民に激しい攻撃を仕掛けましたが,その町を攻め落すことはできませんでした。[…]捕虜になったワクワークの住民を尋問し,彼らが他の国を襲わず,特にこの土地に攻め込んだ訳を問いただしました。彼らの言うには,この土地でとれる象牙や鼈甲や豹皮や龍涎香のように自分の国やシナで持てはやされる物資や,苦役に堪える強靭なザンジュ[Zanj; アフリカ東海岸の黒人]奴隷を求め,航海に一年をついやして来たのだとのことでした。彼らはカンバルフから6日行程はど離れた島々を荒しまわり,ザンジュのスファーラ[Sufāla [Sufala]; アフリカ東海岸、現在のモザンビーク共和国にあたる地域]の村や町を幾つも欲しいままに略奪し尽したのでした。[…]
ワクワーク人の捕虜が一年かかってやって来たと語った話が事実なら,ワクワークの島々はシナの真向かいに位置しているとのイブン・ラーキースの情報には信憑性があると言うことになります。真実を知りたまうには,ただ神のみです。
確かに「驚くべき事件」ではある。このワークワークは明らかに日本ではありえない。945-46年といえば日本では天慶8-9年、平安時代中期、ちょうど関東で平将門(?-940)、瀬戸内海で藤原純友(?-941)がそれぞれ叛乱(承平・天慶の乱)を起こし、相次いで鎮圧された直後の時期である。アフリカ遠征などあり得るはずがないではないか(ちなみにフーイェは黒檀を日本に産するものと誤解した上、この遠征は日本側の記録にはないが、おそらく商人か大名が計画したものだろう、という無茶な主張をしている。いくら日本研究がまだそれほど進んでいなかった時代とはいえ……)。また同書には、ザーバジュに向けて出航した船がワークワークに漂着したとか、あるいはワークワークはディーバジャート(インド南西海上のラカディーヴ諸島・モルディヴ諸島)の近くにあると思える記述もある。どうも『インドの不思議』の編纂者自身、ワークワークの正確な位置についてはよくわからず、混乱していたようである。
もっとも、フェランの主張にもいささかこじつけめいた部分があることは否めない。スマトラ島内陸部に住む一グループの名にすぎない「パクパク」が、なぜスマトラ島を代表する呼び名となったのかがうまく説明できていないし、フェランによれば同一地域名であるはずの「ザーバジュ」と「ワークワーク」をどう使い分けていたのか、という点も疑問の残るところである。
ワークワークの比定地については、この倭国=日本説とスマトラ説が有名であるが、他にも様々な説が出されている。ナイル河の水源調査や『千一夜』の英訳などで有名なイギリスの探検家・東洋学者リチャード・フラシンス・バートン(Richard Francis Burton, 1821-90)が、その『千一夜』の訳註の中で述べているところによれば、ワークワークの比定地についてはセイシェル諸島説、マダガスカル説、マラッカ説、スンダ(ジャワ)説、中国説、日本説、ニューギニア説、果てはペルー説すら出されているという。
また近年、的場節子氏は、ワークワークとシーラをともにフィリピン諸島だとする説を提唱している(的場「南海のワクワク,シーラと古地図に見る極東黄金島再考」)。的場氏は、フィリピン諸島に「ワク」と「シーラ」に該当する地名があること、また、フィリピン諸島全域で純度の高い金を産することなどをその根拠としている。的場氏は、「シーラ」はサンスクリット語で「輝く光」を意味する「シーラ」(ṡila [sila])という語、また「ワークワーク」はフィリピン諸島諸言語で「翼」を意味する「ファファク」「パヤク」「パクパク」などといった語に由来するのではないか、としている。ただし、的場氏は「ワークワークの樹」には言及していない。
そもそもワークワークは多分に伝説的な要素を含んでおり、はっきりどこか実在の土地に比定できるのか、という疑問も起こる。小葉田淳は、「ワクワクの記事を日本やスマトラの事実と比較説明することには無理があり、古代インドの史詩[『ラーマーヤナ』のこと]以来の金島が東方のはてにあるという思想が根底に作用していよう」(『国史大事典』の「金銀島探検」の項)と指摘している。確かに、ワークワークの樹の実在性もさることながら、「犬の鎖や猿の頸輪にまで黄金を用い、黄金で織った衣服をもってきて売る」という光景も、現実のものとは考えにくい。
ワークワークは完全に架空の土地というわけではなく、おそらくは実在の土地なのだろう。だが、その実体が日本であるとする決定的な根拠はない。少なくとも、アラビア語文献に登場するワークワークを、全て日本と結びつけることは、とうていできそうにないのである。かといって、全く無関係と言い切ることにも躊躇を覚えるのであるが。
スマトラ島の話が出たついでに、前章で触れた時期以後、7世紀から10世紀あたりにかけてのスマトラ・ジャワ一帯の歴史について簡単に触れておく。
1918年、先に名を出したフランスの東洋学者ジョルジュ・セデスは、7世紀から14世紀にかけて、スマトラ島東部のパレンバンを中心とする「シュリーヴィジャヤ」(スリウィジャヤ)という国が存在していた、とする説を唱えた。中国語史料によれば、7世紀半ばから742年にかけて、「室利仏逝」(「尸利仏誓」などとも表記される)という国が唐に朝貢を行っており、その後、904年から14世紀ごろまで、「三仏斉」という国が中国(唐、宋など)に朝貢を行っている。セデスはこの事実と、碑文に現れる「シュリーヴィジャヤ」という固有名詞(それまで王名だと思われていた)を根拠に、それまでまったく忘れられていたこの国の存在を明らかにしたのである。
シュリーヴィジャヤはマラッカ海峡周辺に初めて出現した大国であり、東西交易の重要な拠点として繁栄したらしい。671年、法顕や玄奘(602-64)にあこがれて海路インドへと渡った唐僧の義浄(635-715)は、その帰路、685年から694年にかけてこの国に滞在しており、この地では大乗仏教が盛んであることを記録に残している。なお、彼の『大唐西域求法高僧伝』(692)の附録「重帰南海伝」(697頃)には「金洲」という地名が記されている(貞固律師伝・道宏伝)。これはスヴァルナドヴィーパ、すなわちシュリーヴィジャヤの雅称だと考えられている(小葉田『日本と金銀島』。ただし、金洲はインドだとする説(足立喜六〔訳註〕『大唐西域求法高僧伝』)もある)。
しかし、セデスの説については、その後、これだけ長期間にわたって存続した国にしては考古学的遺物が極端に乏しいことや、「室利仏逝」と「三仏斉」が同一の政権であるとする根拠が薄弱なこと、その他史料上の様々な矛盾などが指摘されるようになり、近年では、シュリーヴィジャヤはいったん8世紀に崩壊しており、その後の「三仏斉」は中央集権的な統一政権ではなく、マラッカ海峡一帯の港市国家の連合体だとする説が有力となりつつある。この説に基づけば、「三仏斉」はシュリーヴィジャヤではなく、アラビア語史料に現れる「ザーバジュ」と同じものとなる。
また、ジャワ島では、7世紀から「訶陵」という国が唐に朝貢を始めている。訶陵は、8世紀後半から9世紀前半にかけてジャワ島中部に仏教遺跡ボロブドゥールを建設したシャイレーンドラ王国と同じものだと考えられている。いっぽう8世紀初頭、同じジャワ島中部にマタラム(古マタラム、サンジャヤ朝)という国が出現しており、この国は9世紀半ばにヒンドゥー教遺跡プランバナンを建設している。ただし、訶陵とシャイレーンドラ、マタラム、それにシュリーヴィジャヤ四者の関係については不明な点が多い。なにぶん、この時代のことについては系統的な文献史料が残されているわけではなく、碑文や断片的な史料に頼らざるを得ないため、はっきりしたことがなかなかいえないのである。
いずれにせよ、もしワークワークがスマトラ方面だとすれば、これら諸国がその候補となりうるだろう。
 |
ところで、妖怪画で知られる狩野派の絵師(喜多川歌麿の師でもある)・鳥山石燕(とりやま・せきえん)(1712-88)の妖怪図譜『今昔百鬼拾遺』(安永9=1780)に、「人面樹」(にんめんじゅ)という妖怪が記載されている。石燕によれば、この妖怪は次のようなものである。
山谷にあり。その花人の首のごとし。ものいはずしてたゞ笑ふ事しきりなり。しきりにわらへば、そのまま落花すといふ。
「花」と「実」の違いこそあるものの、「ワークワークの樹」伝説と極めてよく似た話である。石燕の描いた妖怪の中には、素性のはっきりしないものや、明らかに創作と見られるものも少なくないが、この人面樹の場合はその典拠が明らかになっている。すなわち、漢方医の寺島良安の編纂した百科事典『和漢三才図会』(正徳2=1712頃)巻14「外夷人物」(ここでの「外夷」とは、良安の説明によれば、漢字と箸を用いない諸国のこと)にある、以下の記事である。
大食[だいし/ダアシツ]
三才図会ニ云フ、海ノ西南一千里ニ在リ、山谷ノ間ニ居ル。樹有リ、枝ノ上花ヲ生ズ。人首ノ如ク、語ヲ解セズ、人借問スレバ惟ダ笑フノミ。頻リニ笑ハバタチマチ凋ミ落ツル。 [『三才図会』(人物十三巻)によれば、海の西南一千里にあり、山谷の間にある。枝上に人の首のような花を生じる樹がある。人の首のような花は人語を解せず、問いかけるとただ笑うのみで、あまりに笑うと凋[しぼ]み落ちる。]
 |
なお、三坂春編(みさか・はるよし)(1704?-65)が記した、会津地方を中心とする奇談集『老媼茶話(ろうおうさわ)』(寛保2=1742序)巻1にも、『和漢三才図会』とほとんど同じ記事が見られる。
ワークワークが日本であるとすれば、「ワークワークの樹」もまた日本に実在するのではないか――そう考えたフーイェは、横浜司薬場のオランダ人教師アントン・ヨハネス・コルネリス・ヘールツ(Anton Johannes Cornelis Geerts, 1843-83)にわざわざ問い合わせている。ヘールツの回答は、当然ながら日本にはそんな植物は実在しないし、それに類する伝承などもない、というものであったが、ただし彼は『和漢三才図会』の記事を見つけ出している。ヘールツはこの記事について、日本における近代植物学の草分けであった伊藤圭介(1803-1901)に問い合わせたが、伊藤もこの記事の存在は知らなかったという。
してみると、やはり日本にも「ワークワークの樹」に類する伝説があったのか――と早合点してしまう前に、『和漢三才図会』の記事をもう一度注意深く見ていただきたい。まず、この記事の出典は『三才図会』とされている。『三才図会』(1607序)は明の王圻(おうき)が編纂した百科事典で、『和漢三才図会』はその名からもわかるようにこの本を下敷きにしている。つまり、この伝説はもともと中国から輸入されたものなのだ(『老媼茶話』にも、出典は『三才図会』であることが明記されている)。そして、この樹が存在するとされているのは「大食」、すなわちアラビアなのである。実はこの樹、正史である『旧唐書』(945)・『新唐書』(1060)をはじめ、杜佑『通典(つてん)』(801)・段成式『酉陽雑俎(ゆうようざっそ)』(860頃)・馬端臨『文献通考』(1317)など、極めて多くの中国文献が、「大食」にある樹として記載しているのである。
このうち、最も古い『通典』巻第193(辺防9・西戎5・大食)には以下のようにある(『旧唐書』『文献通考』などもほぼ同じ)。
又云、其王常遣人乗船、将衣糧入海、経渉八年、未極西岸。於海中見一方石、石上有樹、枝赤葉青、樹上総生小児、長六七寸、見人不語而皆能笑、動其手脚、頭著樹枝、人摘取、入手即乾黒。其使得一枝還、今在大食王処。
――大食の王[アッバース朝のカリフであろう]は使者を船に載せて遣わした。使者は衣服や食糧を積んで航海に出た。八年経っても西岸に着かなかった。海中に一つの四角い石を見た。石の上には樹が生えており、枝は赤く葉は青い。樹の上には小児がたくさん生えていた。その長さは六~七寸で、人を見ると物は言わないがみなよく笑い、手足を動かす。頭は樹の枝にくっついている。人が小児を摘み取ると、たちまち乾いて黒ずんでしまう。その使者は枝を一本持って帰った。今、それは大食王のところにある。
先述したように、「ワークワークの樹」に関するイスラーム圏での最も古い記録は、9世紀半ばのジャーヒズ『動物の書』であるが、この記述はそれよりも遡る。
なお、『通典』は百科全書的な政治制度史の書である。著者の杜佑(735-812)は唐の宰相をつとめたこともある政治家で、詩人・杜牧(803-52/3)の祖父にあたる。その杜佑の「族子」(同族の兄弟の子)に、751年の「タラス河畔の戦い」(*)に参加してアッバース朝の捕虜となった、杜環という男がいた。彼は約10年間をアラビアで過ごしたのち、762年に中国へと帰国し、その後、自らの体験を記した『経行記』という書物を書き残した。『経行記』自体は残念ながら現存していないが、『通典』にその一部が引用されている。ということは、どうやらこの「大食の人木」の伝説は、杜環がアラビアから中国へと伝えたものらしい。
(*) 現在のキルギス共和国北西部のタラス河附近で、高仙芝率いる唐軍とアッバース朝軍が衝突した戦い。唐側の敗北に終わった。このとき、唐軍の捕虜の中に製紙技術を持った者がおり、製紙技術が西方世界へと伝わるきっかけを作ったことでも名高い。
いっぽう、『酉陽雑俎』巻10には以下のようにあって(『新唐書』もほぼ同じ)、『通典』の伝えるところとは多少異なっている。
人木。タジク〔大食〕の西南二千里のところに、国がある。その山や谷あいの樹木の枝に、人の首が花のようにはえている。言葉は理解しない。人が問いかけると、笑顔をみせるだけだ。頻繁に笑うと、かならず落ちる。(今村与志雄〔訳注〕『酉陽雑俎』(2))
こちらの話が『通典』から派生したものなのか、それとも別のルートで伝わった話なのかは明らかでない。なお『三才図会』の記事は、明らかにこちらの記事を参照したものである。ただし、『酉陽雑俎』では人木は「大食」の西南にある国に生えているとされていたのに、『三才図会』では「大食」に人木があることになってしまっている。
いずれにせよ、この伝説は「ワークワークの樹」伝説と非常に似通っており、全く無関係とは考えにくい。それにしても、アラビアでは東の果てのとされるこの樹が、中国や日本では全く逆方向、西方、大食(アラビア)のさらに西ないしは西南にある、とされているのは興味深い。
さて、この植物が中国ではアラビアと結び付けられていることを知ったフーイェは、今度はアラビアに目を向けた。そして彼は、「ワークワークの樹」のモデルとなったのはウシャル(カロトロピス・プロケラ)(*)だ、と断定したのである。例の、『インドの不思議』でワークワークの樹の引き合いに出されていた実在の植物である。フーイェは、アラビアの地におけるウシャルについての知識が、中国に伝わって「大食の人木」の伝説となり、それがアラビアに逆輸入されて「ワークワークの樹」の伝説となった、と推測している。
(*) フーイェは学名を Asclepias procera ないし A. gigantea としているが、この種は現在ではトウワタ属 Asclepias ではなくカイガンタバコ(カロトロピス)属 Calotropis に分類されている。なお、 C. gigantea は C. procera とは別種で、和名をカイガンタバコないしアコンという。
この推定は面白いが、いささか問題がある。まず、ウシャルの実がなぜ人間(の頭)そっくりだとされるようになったのか、全く説明ができていない。それにフーイェは、中国ではこの植物が大食その地ではなく、その西方の地に産するとされていることを見落としている。全体として彼はワークワーク=倭国=日本説に必要以上にこだわりすぎている感がある。むしろ「大食の人木」の伝説は、アラビアにおける「ワークワークの樹」伝説そのものか、あるいはそのヴァリエーションが中国に伝わったもの、と考えた方が妥当であろう。ただし、確かにウシャルがワークワークの樹の原型のひとつになったという可能性は否定できない。
「ワークワークの樹」の正体に関するそれ以外の説も見ておくことにしよう。
まずフェランは、先述した通りワークワークの樹はタコノキの一種だとしている。
バートンは、この植物は「ひょうたんの木 Calabash-tree (Adansonia digitata)」だとしているが、これはアフリカバオバブのことである。バオバブ類 Adansonia はアフリカやマダガスカル、それにオーストラリア北部などのサバンナ林地帯に分布している。高さは 10数m にも達し、その特異な樹形は、よく「巨人が根っこから引き抜いてさかさまにしたよう」と形容される。また、その実は長さが 25~45cm ほどの長楕円形で、サルが好んで食べることから「モンキー・ブレッド」とも呼ばれる。
イスラーム史家の杉田英明氏(1956-)は、ココヤシ Cocos nucifera の実が実際に人間の頭を連想させること、歴史家イブン・サイード(Ibn Sa‘īd [Ibn Said], 1213-86)がワークワークの樹の実をヤシの実に喩えていることなどから、ヤシの実がワークワークの樹の伝説の起源(の少なくともひとつ)ではないか、と推定している。
なお、中国文学者の磯部彰氏(1950-)は、宋代の占術書に人面樹の趣向が見えることや、唐代の密教で「樹木の葉上に菩薩像を描いて曼荼羅とし、尊宗していた」ことを挙げ、これはおそらくインドの密教にまで遡るものではないか、とし、「アラビア人はワークワークを東方にあると考え、中國人は人面樹をアラブのものとすることは、人面樹の發祥地が中間のインド方面であったことを暗示する」「インド方面の密教、もしくはインド古来の土俗説話によるものが、東西に分派して波及したものと考えて差支えないのではなかろうか」と述べている(磯部『『西遊記』形成史の研究』, pp. 130-133)。しかし、磯部氏はインドに実際にこの種の伝承が存在するかどうかを示していないし、また、中国文学者の中野美代子氏(1933-)も指摘しているように、「葉上に菩薩像を描いただけでは、「人間のなる木」のモチーフには直結しない」(中野『孫悟空の誕生』, p. 251)。したがって、この説は思いつきの域を出ていない。
ついでながら、『西遊記』(明刊本第24~26回)には「生まれて三日もたっていない赤んぼそっくり」の仙果「人参果」が登場する。これは「三千年に一回だけ花が咲き、三千年に一回だけ実をつけ、その実は三千年たってから、やっと熟す」という植物で、しかも一度になる実は三十個だけ。それを一個丸々食べれば、4万7000年も生きられるという。とある道観(道教の寺)を訪れた三蔵法師一行は、そこのもてなしで人参果を出される。が、三蔵はそれが赤ん坊でないとは信じられず、どうしても食べようとしない。一方、孫悟空・猪八戒・沙悟浄の三人は、こっそり人参果を盗み食いしてひと騒動を引き起こすのである。この話の原型は、『西遊記』の原型である13世紀の『大唐三蔵取経詩話』にもすでに見える。中野美代子氏は、この「人参果」は、「人参」すなわちチョウセンニンジン Panax ginseng と仙桃、大食の人木(=ワークワークの樹)、それにマンドラゴラなどが混ざり合って作られたものだ、としている(中野『中国の青い鳥』、同『孫悟空の誕生』)。
話はいささか脱線するが、人間と植物の融合した存在である「ワークワークの樹」は、やがてアレクサンドロス(アレキサンダー)大王伝説などとも混同され、様々な図像を生み出すことになる。
一代にしてギリシアからペルシア・インドにまで至る大帝国を築き上げた大王として、生前からすでに伝説的な存在であったマケドニア王アレクサンドロス3世(在位前336-前323)の事績は、やがて「アレクサンドロス・ロマンス」と総称される様々な伝説を生み出す。その原典となったのが、3世紀頃、おそらくエジプトのアレクサンドリアにおいてギリシア語で書かれた『マケドニアのアレクサンドロスの生涯』という書物である。その中では、アレクサンドロスは実はエジプトの王子で、食人馬ブケパロスを乗りこなし、世界の果てと人間の生命の限界を確かめるため、文字通り海に陸に空にと大冒険を繰り広げ、最後は部下の裏切りにあって毒殺されたことになっている。この書物は虚実ないまぜの荒唐無稽かつ支離滅裂な伝奇小説であるが、アレクサンドロスに仕えた歴史家カリステネス(*)が書いたものだということにされ、様々な言語に翻訳されて広まった。その分布範囲は、北はアイスランドから南はエチオピアまで、西はイベリア半島から東はインドネシアにまで及んでいる。
(*) アリストテレスの甥。東方遠征に従軍中、アレクサンドロスに対する叛乱をもくろんだ容疑で逮捕され、処刑されたとも病死したとも伝えられる。ということは、彼がアレクサンドロスの死について書けるはずなどないのだが……。
さて、この『マケドニアのアレクサンドロスの生涯』の中(第3巻第17節)に、次のような一挿話がある。ちなみにこの場面は、写本のヴァージョンによっては、アレクサンドロス自身が、自らの家庭教師でもあった哲学者アリストテレス(前384-前322)に宛てて書いた(ことになっている)手紙の一部とされていることもある。
――インドにやってきたアレクサンドロスは、「太陽の樹」と「月の樹」と呼ばれる二本の樹を祀った聖域を訪れた。「太陽の樹」は男の声で、「月の樹」は女の声で、それぞれ神託を告げるという。このとき二本の樹はいずれも、アレクサンドロスは、近いうちにバビロンで身内の者の手によって暗殺されるであろう、と予言した――
このとき太陽の樹は、アレクサンドロスの母と妻もまた殺されると予言したともいう。
アレクサンドロスは紀元前327年に実際に西北インドに侵攻しているが、途中で部下たちが進撃を拒否したため、やむをえず引き返している。紀元前323年、彼はバビロン(現・イラク領)で突然倒れ、数日間にわたって高熱に苦しんだあげく、32歳の若さで急逝した。没後に毒殺の噂が流れたのも事実であるが、実際にはおそらく病死であったろうと推定されている。なおその後、部下の将軍たちは約半世紀にわたり、血で血を洗う陰惨な後継者争い――ディアドコイ(後継者)戦争――を繰り広げることになる。この過程で、アレクサンドロスの母后オリュンピアスと王妃ロクサネ、それに王の死後に生まれた子であるアレクサンドロス4世もまた命を落としている。
この話はワークワーク伝説とは直接何の関係もないのだが、「人間の言葉を解する樹」というモティーフが共通することから、後世、「ワークワークの樹」の伝説と結び付けられることになった。
例えば、イランの国民的大叙事詩であるフィルドゥーシー(Firdawsī [Firdawsi], 934?-1025?)の『シャー・ナーメ(王書)』(Shāh nāma [Shah nama], 1010)の14世紀の写本の挿絵には、イスカンダル(Iskandar; アラビア語・ペルシア語でアレクサンドロスのこと。『シャー・ナーメ』では古代ペルシアの大王の一人とされている)が、人間や様々な動物の頭をつけた樹と会話している場面が描かれている。これは、「ワークワークの樹」と「太陽と月の樹」とが混同された結果として生じた図像である。
なお、イスラーム美術の唐草文様の中には、枝の先端に人間や動物の頭をくっつけたものがあり、この文様は「ワークワーク文様」と呼ばれている。
さらに、中世フランスにおけるアレクサンドロス・ロマンスの中には、「ワークワークの樹」がより深く取り込まれたものもある。例えば、仏文学者の澁澤龍彦(1928-87)は、「十二世紀末のフランス人アレクサンドル・ド・ベルネエの叙事詩『アレクサンドロス大王物語』
」(Alexandre de Bernay, Li romans d'Alixandre)中の一挿話として、次のような物語を紹介している。
アレクサンドロス大王の兵士たちが、インドに近い土地で、とある魔法の森に入ってゆくと、どの樹の下にも、うら若い処女が一人ずつ立っているのを発見する。美しい姿態、小さな胸、明るく澄んだ眼、みずみずしい肌の処女たちである。彼女たちは、この魔法の森の奥で、春が来るたびに、豊かな液汁に潤された大地から萌え出るのである。[…]
処女たちは、べつに恥ずかしがりもせず、みんなの見ている前で、一人ずつ自分の相手を選ぶ。彼女たちを自由にしようと思えば、造作もない。むしろ彼女たちの方から男を誘うような塩梅でさえある。しかし、人間と植物との交情には、必らず悲劇的な結末が待っているという。
魔法の森で、かの純潔の誉れ高きアレクサンドロス大王もまた、ひとりの処女に夢中になってしまった。雪のような純白の肌の処女であった。大王は、彼女を連れて帰ろうと思い、彼女の頭を王冠で飾り、抱き上げて馬の鞍にのせようとした。すると処女が悲しげな、おびえた声で、次のように訴えたのである。「やさしい大王さま、あたしを殺さないでくださいまし。一歩でも森の外に出れば、あたしはすぐ死んでしまうのです。それがあたしの運命なのです」と。
彼女たちは、生まれ故郷の大地にしっかり結びついていて、無理にそこから引き離せば、ただちに死ぬ運命だったのである。のみならず、寒い冬が近づけば地中にもぐり、地面の下で姿を変え、ふたたび夏がめぐってくると、今度は白い花の形になって、地上に顔を出す。そういう運命の植物だったのである。アレクサンドロス大王とその家来たちは、ひどく落胆して、魔法の森を立ち去ったという。(澁澤龍彦「マンドラゴラについて」)
なお、ヨーロッパ中世のキリスト教図像学では、「生命の樹」(*)や「エッサイの樹」(**)の図像に人頭樹のモティーフが用いられており、これらと「ワークワークの樹」の関連性を指摘する説もある(バルトルシャイティス『幻想の中世』)。が、まあ、脱線はこの程度にしておこう。
(*) 「命の木」(生命の樹)は、エデンの園の中央に「善悪の知識の木」(知恵の樹)と並べで植えられた樹。「知恵の樹」の実を食べた者が知恵を得るのに対し、「生命の樹」の実を食べた者は永遠の生命を得る(《創世記》2:9, 3:22)。また中世には、イエス・キリストがかけられた十字架は、この生命の樹の種から生えた樹で作られたという「十字架伝説」が広まった。イタリアの神学者ボナヴェントゥラ(Bonaventura, 1221?-74)は、キリストが磔に処せられている木の幹から左右に12本の枝が出て、その枝に48のメダイヨンが配置され、そこにキリストの生涯が表される、という図像を創案している。
(**) エッサイはイスラエル王ダヴィデの父。ユダヤ教の教義ではダヴィデの子孫からメシア(救世主)が生まれるとされており、《イザヤ書》はそのことを「エッサイの株からひとつの芽が萌えいで/その根からひとつの若枝が育ち/その上に主の霊がとどまる」(11:1-2)と預言している。この信仰は、イエスを神の子にしてキリスト(救世主、メシア)だとするキリスト教にも受け継がれており、イエスの養父(聖母マリアの夫)ヨセフはダヴィデの子孫とされている(《マタイによる福音書》1-2)。後世のキリスト教美術では、《イザヤ書》の比喩表現に基づき、横たわったエッサイの胸(または口)から枝(または蔓)が伸び、その枝に歴代のユダヤの王たちが描かれ、そしてその頂上にマリアとイエスが描かれる、という図像が描かれることになった。この図像はフランスのサン=ドニ修道院長シュジェール(Suger, 1080頃-1151)が流布させたものという。