



最初にも述べたように、アジアの東の果てに金や銀を豊かに産する島がある、という言い伝えは、べつにマルコ・ポーロに始まるものではない。
1~2世紀ごろにローマ帝国で書かれたギリシア語やラテン語の文献には、インドの東方海上、世界の東の果ての近くに「クリュセ」(Chryse)と「アルギュレ」(Argyre)と呼ばれる島がある、という記事が現れ始める。古典ギリシア語で「クリュソス」(chrysos)は「金」、「アルギュロス」(argyros)は「銀」を意味する。すなわち、クリュセは「金島」、アルギュレは「銀島」という意味である。
1世紀半ば頃に書かれたポンポニウス・メラ(Pomponius Mela)の地理書『世界地理』(De Chorographia; 一名 De Situ Orbis)には、このような記述が見られる。
タムス岬そばにクリュセ島、ガンゲス河そばにアルギュレ島があって、古人の伝えるところでは島の土壌が、一方は黄金(クリュソス)、他方が銀(アルギュロス)という。しかし、どう見ても、実際の状況から島の名が付いたのでなければ、島の名からこの作り話が出来たのであろう。
「タムス岬」というのはアジアの最東端の岬だとされている。メラの地理認識では、アジアの中央をタウロス山脈(アナトリアのトロス山脈。ここではヒマラヤまで至るアジアの中央山脈を漠然と指す)が東西に貫いており、この山脈がエオウス海(東方の海)に接するところにタムス岬がある。この岬の北にはセレス(中国)があり、南にはインドがあってガンジス河(ガンガー河)がエオウス海に注いでいる、とされている。したがって、この岬は多分に空想的な存在ではあるが、おおむね東南アジアあたりということになるだろうか。いずれにせよ、ここではクリュセとアルギュレはともにアジアの東の果て、エオウス海の中にある、とされているわけである。
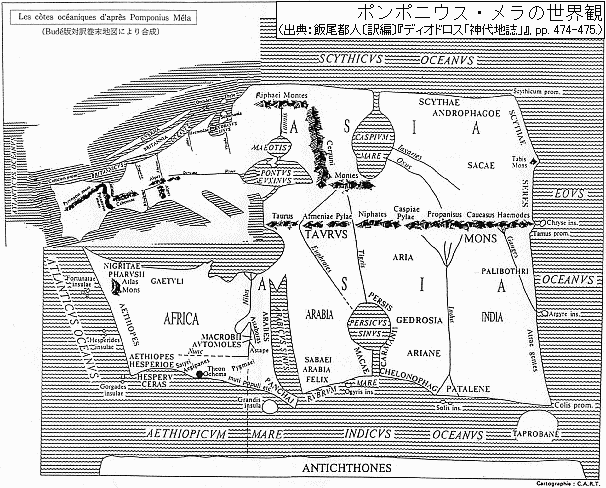
また、古代ローマの大博物学者・大プリニウス(Gaius Plinius Secundus, 23頃-79)の有名な『博物誌』(Naturalis historia, 77)の中にも、クリュセとアルギュレについて触れた一節がある。
インダス河口の外側にはクリュセとアルギュレの両島、いずれもわたしの信ずるところでは各種の鉱物に富んでいる。というのは、ある著作者たちの、そこには金銀鉱しかないという記述には信をおき難いから。
ここでは両島はインダス河の河口附近にあることになっている。メラもプリニウスも否定的にしか言及していないが、当時の著作者たちの中には、クリュセとアルギュレはその名の通り、金と銀から出来ている、と書いていた者もいたようである。
さらに、おそらく1世紀後半か2世紀初めに書かれたと見られる、ローマ帝国と東方世界との海上貿易の状況を記した貴重な記録『エリュトラ海案内記』(Periplus maris Erythraei)(エリュトラ海とは紅海のことだが、ここでは漠然とインド洋一帯を指す)にも、このような記述がある。
その次には東に向かって,右方に大洋を見て,左方は(陸地の)残りの部分の沖合を航行していくと,ガンゲース[ガンジス河口の港町だが、正確な比定地は不明]に到達する。そしてその近くに,東方の最果ての陸地であるクリューセーがある。その辺りにこれもガンゲースと呼ばれる河があり,インドにおける最大の河で,ナイル河のように減水と増水がある。[略]またここら辺りには金坑があって,カルティスと呼ばれる金貨があると言われる。この河を下ると大洋の中に島があり,人が住む世界の東に向いた部分が果てるところで,朝日の真下に位置し,クリューセーと呼ばれてエリュトラー海のあらゆる場所の中で最も上等の亀甲を産する。
ここではクリュセはガンジス河口附近、世界の東の果てにある島とされている。しかしここでは、ガンジス河口近くに金鉱があるとは記されてはいるものの、クリュセ自体の黄金については特に記されていない。また、アルギュレについての記載もない。
なお、プリニウスがメラの記事を見ていることは、『博物誌』の参考文献の中にメラの名が挙げられていることからも明らかである。しかし、プリニウスと『エリュトラ海案内記』との先後関係については、『博物誌』が『エリュトラ海案内記』を参考にして書かれているとする説もあるものの、これを否定する説も有力であり、はっきりしていない。
いっぽう、古典古代地理学の集大成であり、西方世界では長期間にわたって非常に強い影響力を持ち続けたプトレマイオス(Klaudios Ptolemaios)の『世界地理便覧』(Geographike Hyphegesis, 2世紀)には、「ガンジス河の外側のインド」(ガンジス河以東、セリカ(中国)以南。すなわち現在の東南アジア)の地名として、クリュセ島ではなくクリュセ半島(Chryse Chersonesos)すなわち黄金半島(ラテン語では Aurea Chersonesus)が挙げられている。この黄金半島は、その位置関係などからマレー半島に比定されている。プトレマイオス自身はこの地名の由来については特に何も言っていないが、マレー半島では実際に砂金を産する。
クリュセ島はこの黄金半島、すなわちマレー半島が誤って島とされたものである、とする説もある。島と半島を取り違えること自体はそれほど珍しいことではない。ただしプリニウスは、クリュセ島とはべつに、「クリュセ岬」(Promunturium Chryse)をセレス人の領土(中国)にある岬として挙げている(『博物誌』第6巻第20章)。とすると、クリュセ島とクリュセ(黄金)半島とは別のものとして考えられていた可能性も否定はできない。
またプトレマイオスは、「アルギュレ」を島の名前としてではなく、「イアバディウ」(Iabadiou)という島の首都の名として記載している。
イアバディウ島,これは「大麦の島」を意味する。すなわち,この島は極めて肥沃で,夥しい金を産し,西端部にアルギュレ(銀の都)という名の首邑をもつと言われる。
イアバディウ島もやはり金を豊富に産するとされている。この島はクリュセ半島の南方海上とされているから、位置関係からすると大スンダ列島のどこか、おそらく現在のインドネシア共和国のスマトラ島かジャワ島ということになる。「イアバディウ」という名前からはジャワ島(Jawa)が連想される。確かにジャワ島は極めて肥沃だし、金鉱もないわけではない。しかし、古くから金が豊富に採れることで有名なのは、ジャワ島ではなくスマトラ島のほうなのである。
さらにプトレマイオスは、ガンジス湾(ベンガル湾)の東岸に「銀鉱が極めて多いと言われる銀の国」(Argyre Chora)、その北方に「金鉱が極めて多」い「金の国」(Chryse Chora)がある、とも述べている。このうち「銀の国」はアラカン(ビルマ(ミャンマー)(*)南西、ベンガル湾岸の地域)に比定されているが、実際には金銀が豊富に採れるビルマ地方との混同があるらしい。
(*) 1989年6月18日、ビルマ連邦の軍事政権は、国名の英語表記を「バーマ」(Burma; ビルマ)から「ミャンマー」(Myanmar)に改めた。ただし、軍事政権の正統性を認めない側などは、依然として「バーマ」を用い続けている。現地名としては「ミャンマー」「バマー」がともに用いられる。ここでは、歴史的地域名・民族名として「ビルマ」を用いることとする。
さて、これらクリュセ・アルギュレ両島に関する記事は、もともと古代インドの伝承に由来するものではないかと考えられている。その根拠の一つとなっているのが、古典サンスクリット語(梵語)で書かれたインドの古典的大叙事詩『ラーマーヤナ』(Rāmāyaṇa [Ramayana])である。
コーサラ国の王子ラーマの冒険譚である『ラーマーヤナ』は、伝説では詩聖ヴァールミーキ(Vālmīki [Valmiki])の作とされているが、実際には、数百年間にわたって語り伝えられてきたものが、最終的に2~3世紀頃になって現在伝わるような形にまとめられた、と考えられている。その第4巻「キシュキンダーの巻」は以下のような物語である。
――ラーマの妃シーターが、ラークシャサ(羅刹=悪鬼)の王ラーヴァナにさらわれてしまった。ラーマは、弟のラクシュマナとともにシーターを探すための旅に出る。彼女の行方についての手がかりは、猿族の都キシュキンダーに君臨する猿王スグリーヴァが握っているという。だがスグリーヴァは、兄のヴァーリンに王位を奪われていた。ラーマの手助けで王位に復帰したスグリーヴァは、ラーマに協力して、世界中の猿たちに対し、世界中をくまなくかき分けてシーターとラーヴァナの行方を探し当てるよう命じる(余談だが、このときその居所を探し当て、さらにシーター救出のため活躍するのが、有名な神猿ハヌマーン――正確にはハヌマット――である)――
このスグリーヴァの命令は、そのまま一種の世界地理案内となっているのだが、その中にこのような一節がある。
七個の王国に分割されたヤヴァ島[ヤヴァドヴィーパ Yavadvīpa [Yavadvipa]]および、金銀の島々[スヴァルナ・ルーピャカ・ドヴィーパ Suvarṇarūpyakadvīpa [Suvarnarupyakadvipa]、あるいはスヴァルナドヴィーパ Suvarṇadvīpa [Suvarnadvipa] とルーピャカドヴィーパ Rūpyakadvīpa [Rupyakadvipa]]におもむけ。
この島々はインドの東方に位置するとされている。「ドヴィーパ」(dvīpa [dvipa])とはサンスクリット語で「島」を意味する語である。「ヤヴァ」(yava)は「穀物」、特に「大麦」という意味なので、ヤヴァドヴィーパは「穀物(大麦)の島」という意味になる。お気づきになられたかと思うが、プトレマイオスの触れているイアバディウ島とは、このヤヴァドヴィーパのことである。また、「スヴァルナ」(suvarṇa [suvarna])は「金の」、「ルーピャカ」(rūpyaka [rupyaka])は「銀の」という意味なので、スヴァルナドヴィーパは「金島」、ルーピャカドヴィーパは「銀島」という意味になる。
また、中国側の文献にも、ヤヴァドヴィーパについて記述しているものがある。399年、齢60余にして仏典を求めインドへと旅立った東晋の僧・法顕(337?-422?)は、411年、インドから海路で中国へと戻る途上、風に流されて「耶婆提(ヤバデイ)国」に立ち寄ることになり、この地で五ヶ月間を過ごしている。「耶婆提国」の比定地についてはいくつかの説があるが、ヤヴァドヴィーパの音訳と見るのが妥当と思われる。もっとも、法顕自身はこの地にさして興味を持たなかったらしく、その旅行記(『法顕伝』、一名『仏国記』)の中では、「外道、バラモンが盛んで、仏法は言うに足らない」とたったひとこと述べているだけである。
現在のジャワ島の名は、この「ヤヴァ」に由来するとする説が有力である。ただし、かといってヤヴァドヴィーパと現在のジャワ島が全く同じものだと言えるかというと、少々問題がある。実は、ヤヴァドヴィーパとはジャワ島のみを指した名ではなく、ジャワ・スマトラ両島を漠然と総称したものではないか、という有力な説があるのである。先にも少し触れたように、スマトラ島では古くから金銀が採れることが知られており、プトレマイオスの記述にはより符合する。またマルコ・ポーロは、ジャワ島を「大ジャヴァ」(Java major)、スマトラ島を「小ジャヴァ」(Java minor)と、同じ「ジャヴァ」(ジャワ)の名で呼んでいる(実際には、ジャワ島(面積約12万6500km2)よりもスマトラ島(面積約47万3600km2)の方がはるかに大きいのだが、そのことはさておく)。このことも、古い時代には両島が同じ名で呼ばれていたことを裏付けている。
ついでながら、ジャワ島は古くから稲作の盛んな島である。「ヤヴァ」というのは、ここでは大麦そのものではなく、穀物一般を指しているものと解すべきだろう。
スヴァルナドヴィーパの方は、ほぼ確実にスマトラ島と考えてよさそうである。「クリュセ」が「スヴァルナドヴィーパ」の訳だとすれば、クリュセもまたスマトラ島だということになる。もっとも、先述したようにクリュセはマレー半島だとする説も有力である。あるいはむしろ、地理的な認識が曖昧なまま、スマトラ島とマレー半島を漠然と混同して同じような名で呼んでいる、と考えたほうがよいのかもしれない。
少し時代が下るが、11世紀後半にカシミールの詩人・ソーマデーヴァ(Somadeva)が編纂したサンスクリット語の説話集『カターサリット・サーガラ』(Kathāsaritsāgara [Kathasaritsagara]; 「物語の川が注ぐ大海」の意)にも、やはりスヴァルナドヴィーパが登場する。同書に収められている説話の中には、カターハ・ドヴィーパ(マレー半島西海岸のクダー)の王女グナヴァティーが、インドへ向かう途中、スヴァルナドヴィーパの近海で遭難した物語(第123章)や、サムドラ・シューラなる商人がスヴァルナドヴィーパの首都カラシャ・プラに到達した物語(第54章)、チャンドラ・スヴァーミンというバラモンが、生き別れとなったこどもたちを追って、ジャラ・プラ(不詳)からナーリケーラ・ドヴィーパ(ニコバル諸島)、カターハ・ドヴィーパ、カルプーラ・ドヴィーパ(スマトラ島西海岸)、スヴァルナドヴィーパ、シンハラ・ドヴィーパ(スリランカ)を巡った物語(第56章)などがある(岩本裕〔訳〕『カター・サリット・サーガラ』(2)の「解説」)。また、『カターサリット・サーガラ』の挿話である『屍鬼二十五話』(Vetālapañcaviṃśatikā [Vetalapancavimsatika])の中にも、アンガ国の宰相ディールガダルシンが、聖地巡礼の途中でスヴァルナドヴィーパと往復する船に乗りこむ話がある(上村勝彦〔訳〕『屍鬼二十五話』第11話「海中都市(二)」)。彼は航海の途中、海中から突然如意樹が現われ、その木の上で美しい少女が歌を歌い、そして再び木もろとも海中に消える、という怪異に遭遇する。この話を伝え聞いたアンガ国王のヤシャハケートゥは、少女に逢うために自ら旅に出るのである。 こうした物語を見ると、どうやらスヴァルナドヴィーパは、インドの東方海上にある豊かな島国として認識されていたらしい。
ちなみに、『カターサリット・サーガラ』はそれ自体が全18巻2万1388頌よりなる大部の説話集だが、もともとは、『ブリハット・カター』(Bṛhat-kathā [Brhat-katha])という、今日では失われた全10万頌よりなる膨大な説話集を要約したものとされている。
ところで、このスヴァルナドヴィーパと非常にまぎらわしいものに、仏典やインドの説話集の中に登場する「スヴァルナブーミ」(Suvarṇabhūmi [Suvarnabhumi])ないし「スヴァンナブーミ」(Suvaṇṇabhūmi [Suvannabhumi])という地名がある。「スヴァルナブーミ」はサンスクリット語、「スヴァンナブーミ」はパーリ語(上座部仏教の経典に使われた文語)で、それぞれ「黄金の土地」という意味であり、漢訳仏典では「金地国(こんじこく)」と訳されている。プトレマイオスのいう「金の国」とは、おそらくこのスヴァンナブーミのことであろう。
紀元前3世紀頃に成立した『ジャータカ』(Jātaka [Jataka]; 本生(ほんじょう)譚。釈迦の前世についての物語集)の一つ、「マハージャナカ・ジャータカ」(Mahājanaka-jātaka [Mahajanaka-jataka]. パーリ・ジャータカ第539話)では、スヴァンナブーミは海の彼方、豊かな財宝の地として登場している。
――ヴィデーハ国のアリッタジャナカ王は、弟のポーラジャナカ副王が王位を奪おうとしているのではないかという疑いを抱き、弟を除こうとして、かえって返り討ちにあって殺されてしまう。このとき王妃はすでに王の子を身ごもっていた。彼女は王都ミティラーを逃れて生き延び、王子を生む。マハージャナカと名付けられた王子は、やがて成長し、父の王国を奪い返すことを決意する。彼はそのためには財産を作らなければならないと考え、豊かな財宝を誇るスヴァンナブーミへと旅立つことを決意する。だが、彼の乗り込んだスヴァンナブーミへと向かう船は、途中で遭難してしまう。彼は海に投げ出されたところを女神マニメーカラーに救助され、命からがらミティラーにたどりつく。
いっぽうその頃、ミティラーでは王となっていたポーラジャナカが病に倒れ、自らの課した課題を解いたものに王位を譲る、という遺言を残して世を去った。マハージャナカはこの条件を見事にクリアして王国を手に入れ、ポーラジャナカの一人娘シーヴァリ王女と結婚する。が、彼はあるとき悟りを得て出家することを決意し、王妃が引き止めるのも聞かずに王都を去る――
あえて説明するまでもないと思うが、主人公のマハージャナカは釈迦の前世とされている。ここでは、スヴァンナブーミは海の彼方にある豊かな土地とされている。
また、釈迦の弟子の一人で、天文学に通じ「知星宿第一」とされるマハーカッピナ(Mahākappina [Mahakappina]; 摩訶劫賓那(まかこうひんな))は、一説によれば、もとは三万六千の属国を従える金地国の大王であったという。彼はインドを征服しようとして、コーサラ国王のパセーナディ(波斯匿(はしのく)。サンスクリット語ではプラセーナジット。釈迦の保護者として知られる)に降伏勧告を送りつけた。だが、彼は転輪聖王(てんりんじょうおう)(インド神話上の理想的帝王)に変身した釈迦によっておのれの力量のほどを思い知らされ、仏教に帰依して出家したのだという(「賢愚経(けんぐきょう)」巻7・第36話「大劫賓寧品」、「撰集百縁経(せんじゅうひゃくえんきょう)」巻9・第88話「罽[ケイ]賓寧王縁」。なお、『今昔物語集』巻2「金地国ノ王、仏所ニ詣ヅル語」はこの話の翻案)。もっとも彼については、クックタというの町の王だった、とする異説もある。
さらに、スリランカのパーリ語仏教史書『ディーパヴァンサ』(Dīpavaṃsa [Dipavamsa]; 『島史』の意、『島王統史』とも。4世紀後半~5世紀初め成立)や『マハーヴァンサ』(Mahāvaṃsa [Mahavamsa]; 『大史』の意、『大王統史』とも。5世紀後半~6世紀初め成立)などによれば、インド統一の覇者で、仏教の保護者として知られるマウリヤ朝のアショーカ王(在位前268頃-前232頃)は、仏教を広めるために伝道師を周辺各国に派遣することを手助けしたという。このとき、ソーナ(Sona; 須那)とウッタラ(Uttara; 鬱多羅)の二人の僧が、金地国に派遣されて仏教を伝えたという。この話が事実だとすれば、金地国=スヴァンナブーミは紀元前3世紀頃からインドと交流があり、その文化の影響を受けていたことになる。
ちなみに『マハーヴァンサ』によれば、その頃、金地国では王子が生まれるたび、羅刹女がやってきて王子を食べてしまっていたという。ソーナとウッタラが金地国にやってきたのは、ちょうど新しい王子が生まれたときだった。二人は神通力で羅刹女を退治し、仏教を広めた。その後、新しく生まれた王子たちは、二人の名をとって「ソーヌッタラ」(Sonuttara)と名づけられるようになったという。
ただし、この各地への伝道師派遣の話は、アショーカ王の時代から6世紀も後になって書かれた『ディーパヴァンサ』に初めて現れるもので、そのまま史実と受け取ることはできない。もっとも、アショーカ王が「ダルマ」(ここでは、万人の守るべき行為の規範のことで、仏教そのものではない)を普及させるための使者を各地に派遣したのは歴史的事実であり、王の残した碑文によれば、その範囲はセレウコス朝シリアやプトレマイオス朝エジプト、アンティゴノス朝マケドニアなどのヘレニズム諸国にまで及んでいるという(山崎元一『アショーカ王伝説の研究』)。
金地国=スヴァンナブーミが実在の土地であり、現在の東南アジアのいずこかであることはほぼ間違いない。しかし、その正確な位置については様々な説があり、はっきりしていない。
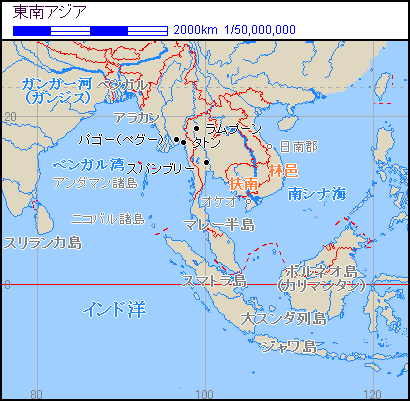
ビルマで19世紀半ばにまとめられたパーリ語の仏教史書『サーサナヴァンサ』(Paññāsāmi [Pannasami], Sāsanavaṃsa [Sasanavamsa], 1861. 『教史』の意)によれば、スヴァンナブーミ(ビルマ語読みでスワンナブーミ)とは、ビルマ南部の港町タトン(Thaton)にあったモン人(Mon)の王国、ラーマンニャデーサ(Rāmaññadesa [Ramannadesa])のことだとされている。モン人(*)は、現在のタイ西部からビルマ南部にかけて居住している人々である。彼らは古くからインドシナ半島に住んでおり、インドシナ半島中・南部にドヴァーラヴァティ(6~11世紀頃)、ハリプンチャイ(ハリプンジャヤ。7世紀?~1292)、バゴー(ペグー)朝(ハンターワディー朝。1287-1539)などいくつもの王国を建国してきた。タトンの王国は港町として栄えていたが、1057年にパガン朝(ビルマ最初の統一王朝。1044-1299)の創始者アノーヤター(在位1044-77)によって征服され、マヌハ王や僧侶500名などが首都パガンに連行されたという(ただし、この事件については、その史実性を疑問視する説もある)。
(*) 中国西南部からインドシナ半島にかけて居住するモン人(Hmong. ミャオ(苗) Miao ともいう)とは、日本語表記では同じだがまったく別の集団である。混同しないよう注意。
『サーサナヴァンサ』によれば、ソーナとウッタラは仏滅紀元235年(紀元前310年。年代が合わないが原文のママ)にスワンナブーミ王国にやって来たとされる。また、15世紀後半にバゴー朝のダンマゼーディー王(在位1459-92)が建てた碑文(1467年のバゴー郊外のカルヤーニ碑文、1485年のヤンゴンのシュエダゴン・パゴダ碑文)には、「釈尊入滅後二三六年を経て、ソーナテーラとウッタラテーラの二僧正が、スワンナブーミ国にご来訪され、仏教が確立した」と刻まれているという(綾部+石井〔編〕『もっと知りたいミャンマー』)。
なお、『後漢書』(432)には、1世紀末から2世紀前半にかけ、現在のビルマ領のあたりに「撣[てへん+單]」(タン、あるいはセン)という国があった、という記事が見える。この国はタトンに比定されている。ただし、この国はビルマ中部にあったピュー人の国「驃」(832年に雲南地方にあった南詔国に征服され、以後ピュー人は歴史から姿を消す)と同じものだとする説もある。
『後漢書』によれば、永元9年(97)と永寧元年(120)に「撣国王」の「雍由調」が陸路経由で後漢に朝貢を行っており、また永建6年(131)には、撣国の朝貢使が海路を経て日南郡(現在のヴェトナムのフエ付近)に来たという(「西南夷伝」及び「和帝紀」「安帝紀」「順帝紀」「陳禅伝」)。特に120年の朝貢では、「幻人」が献上され、安帝(在位106-25)を愉しませたという。この「幻人」は「能(よ)く変化して火を吐き、自ら支解し(自分の身体をばらばらにし)、牛と馬の頭を易(とりか)う」というから、どうやら今日でいうマジシャン、イリュージョニストのようなものであったらしい。この「幻人」は「海西人」と称していたが、この「海西」とは「大秦」、すなわちローマ帝国のことだという。実際にこの「幻人」がローマ帝国から来たかどうかはともかく、この地域が当時、すでに西方世界と盛んに交易していたことをうかがわせる記述である。
スヴァンナブーミの比定地については、このタトン説がいちおう最も有力視されてはいるのだが、いまのところ考古学的に確実な裏付けがあるわけではなく、また異論も決して少なくはない。例えば、タイ国王ラーマ5世チュラロンコン(在位1868-1910)の異母弟で、近代タイ歴史学の父とも呼ばれるダムロン親王(Damrong Rajanubhab, 1862-1943)は、タイ中西部、スパンブリー県のウートーン遺跡(U Thong; 「黄金のゆりかご」の意)がスヴァンナブーミ(タイ語ではスワンナプーム)だと主張したという(『タイの事典』。もっとも、今日ではウートーン遺跡自体はドヴァーラヴァティ時代のものだと考えられている)。このあたり、ビルマもタイも、のちに上座部仏教(南伝仏教。「小乗仏教」は大乗仏教側による蔑称)を盛んに受け入れた国であることを考えると、いずれも自国における仏教の歴史を権威づけるため、ソーナとウッタラの伝説を持ち出しているのではないか、という気がしないでもない。
この他にも、『サーサナヴァンサ』はハリプンジャヤ(現在のタイ北西部のラムプーンにあった)がスワンナブーミだとする異説があることを載せているし、また、インドのベンガル地方だとする説などもある。さらに、先述したようにスヴァンナブーミとスヴァルナドヴィーパは非常にまぎらわしく、よく混同される。
なお、タイの首都クルンテープ(バンコク)の近くにある「スワンナプーム国際空港」(2006年9月開港)は、この伝説の黄金郷の名をとってつけられたものである。
このあたりで、この地域――東南アジアの古代史についてひととおり見ておくことにしよう。
紀元前214年、秦の始皇帝(在位前222-前210)は嶺南地方(南嶺山脈の南。現在の広東省・広西チワン族自治区一帯)に出兵し、この地に南海・桂林・象の3郡を置いた。秦帝国の崩壊後、紀元前207年、南海郡尉(長官)の趙佗(ちょうた)(?-前137)は自立し南越国を興した。その版図は現在のヴェトナム北部にまで及んでいた。
前漢の元鼎9年(紀元前111)、武帝(在位前156-前87)はこの南越国を滅ぼし、その故地に7つの郡を設置した。そのうち、交趾・九真・日南の3郡は現在のヴェトナム北部(交趾郡がハノイ付近、九真郡がタインホア付近、日南郡がフエ付近)にあたる。この後、北ヴェトナムは、10世紀まで中国歴代王朝の支配下に置かれることになる。そして、このあたりから、中国の文献に東南アジア・インド方面の記録が現れはじめる。『漢書』(1世紀後半)の「地理志」には、日南郡から「黄支国」(南インドのカーンチープラムとする説が有力)に至るルートが記されている。
一方、紀元前1世紀頃から、季節風(モンスーン)を用いてアラビア海を横断することによって、アラビア半島南西部とインド南部とを直接つなぐ航路が広く利用されるようになる。この季節風は「ヒッパロスの風」と呼ばれていた。『エリュトラ海案内記』(第57節)によれば、この名は、この航路を開発したヒッパロスという操舵手にちなむものだという。
中国から東南アジアを経てインド洋に入り、紅海に至る国際海上交易ルート――「海のシルクロード」「南海路」「陶磁の道」「香料の道」など様々な呼び名を持つ――は、このようにして歴史にその姿を現し始める。そして、この交易ルートの要衝である東南アジアでは、やがて各地に、交易港を中心とする、「港市国家」と呼ばれるタイプの都市国家が次第に出現し始める。しかし、この地域の古代史については、断片的な中国語史料や碑文、それに考古学的資料などにたよるほかなく、今日なおよくわかっていない点が少なくない。
紀元前後から、インドの商人たちは交易のため盛んに東南アジアを訪れるようになる。彼らが主に求めていたのは、東南アジアで採れる砂金だった。フランスの東洋学者ジョルジュ・セデス(George Coedès, 1886-1969)は、その原因として、それまでシベリアから中央アジア経由でインドにもたらされていた金が、紀元前2世紀頃から遊牧民族の活動が活発化したためにインドまで来なくなってしまい、金不足が生じたことを挙げている(セデス『東南アジア文化史』)。スヴァルナドヴィーパやスヴァンナブーミといった地名は、おそらくはこのような状況を背景にして生まれたのだろう。そして、彼らの活動が刺激となって、インド文化が東南アジア各地に浸透してゆくことになる。
中国語史料によれば、1世紀末頃、インドシナ半島の南東部、現在のヴェトナム南部からカンボジアにかけての一帯に、「扶南」(ふなん)(1世紀末~7世紀前半?)という港市国家が出現する。メコン・デルタにあるオケオ遺跡(Oc-èo. 現在はヴェトナム領)は、この扶南の交易港であったと考えられている。この遺跡からはローマ皇帝アントニヌス・ピウス(在位138-61)やマルクス・アウレリウス・アントニヌス(在位161-80)時代の金貨なども出土しており、西方世界との活発な交易が行われていたことをうかがわせる。
ちなみに、後漢延熹9年(166)には有名な「大秦王安敦」の使節が日南郡を訪れている。「安敦」はマルクス・アウレリウス・アントニヌスに比定されているが、この使節が実際にローマ帝国から来たのかどうかについては、意見が分かれている。
また、2世紀末には、ヴェトナム中部に「林邑」(りんゆう)という港市国家が出現する。この国はその後「チャンパ」と呼ばれるようになり、国際交易の拠点として、崩壊と再建を繰り返しつつ1835年まで存続している。
『南斉書』東南夷伝(6世紀前半)や『梁書』諸夷伝(636)などによれば、3世紀前半、扶南国王の「范師蔓」(『南斉書』による。『梁書』では「范蔓」)は近隣諸国を次々と征服して「扶南大王」を名乗り、最後に「金隣国」を討とうとして果たさず没したという。この「金隣国」はスヴァルナドヴィーパもしくはスヴァンナブーミのいずれかだと考えられているが、どちらかは明らかでない。なお、これら中国語史料も、扶南国やその周辺では金銀を産することを記している。
いっぽう、ヤヴァドヴィーパないしスヴァルナドヴィーパ――マレー半島やスマトラ・ジャワ一帯の古代史となると、さらに不明な点が多い。『漢書』などにもマレー半島らしい地名はいくつか挙げられているが、その比定地については様々な説があってはっきりしない。
『後漢書』には、永建6年(131)、「葉調国」の王が、先述した撣[てへん+單]国と同時に日南郡に使者を送ってきた、という記事がある。この「葉調」は「耶婆提」同様、ヤヴァドヴィーパの音訳であるらしい(ただし、シンハラドヴィーパすなわちスリランカだとする説もある)。
後漢帝国は3世紀初頭に崩壊し、魏・蜀(蜀漢)・呉の三国に分裂する。このうち、中国南東部を支配し、東南アジアとも関係が深かったのが、孫権(182-252)の建てた呉(222-80)であった。229年頃、呉の交・広州刺史(長官)呂岱(161-256)は、朱応と康泰という二人の使者を扶南へと派遣している。朱応は『扶南異物志』、康泰は『扶南土俗』『呉時外国伝』という見聞録を書き残したとされるが、いずれも散逸して今日に伝わっておらず、他の書物に引用された断片的な記事が知られているのみである。
それによれば、扶南の南東には「漲海」(南シナ海の古称)があり、その海中に大きな島があって、その島に「諸薄国」があるという。この「諸薄」もヤヴァドヴィーパの音訳だとする説がある。
『宋書』夷蛮伝(488)には、「闍婆」(ジャバ)という地名が登場する。同書によれば、元嘉7年(430)から29年(452)にかけて、「闍婆洲」の「呵羅単(カラタン)国」から宋(南朝宋、420-79)への朝貢があったという。「闍婆」はのちの時代には明らかにジャワ島そのものを指すようになるが、この時代においてもそうであったか、ということとなると、意見は分かれている。
この他にも、『梁書』諸夷伝(朱応・康泰の報告を下敷きにして書かれている)には「盤盤(ばんばん)国」「丹丹(たんたん)国」「狼牙脩(ろうがしゅう)国」「婆利(ばり)国」など様々な国名が見える。これらはいずれもマレー半島ないし大スンダ列島にのいずこかにあった国だと考えられているが、その比定地は、「狼牙脩」(ランカスカ Langkasuka)がマレー半島のパタニ付近と推定されているほかは、様々な説があってはっきりしないのが実情である。
なお、ジャワ島西部では、5世紀半ばごろに建てられたと推定される、「タルマヌガラ国」(タルマ)のサンスクリット語碑文が発見されている。これは、インドネシアにおいては、ボルネオ(カリマンタン)東部の「クタイ国」のサンスクリット語碑文(4世紀末頃)についで古い碑文である。この国と「呵羅単」を結びつける説もある。
とりあえず整理してみると、東南アジア、とりわけマレー・スマトラ一帯における産金の事実が、インドに伝わってヤヴァドヴィーパやスヴァルナドヴィーパの話となり、これがさらにローマ帝国に伝わってクリュセとアルギュレになった、ということになる。
しかし、だからといって、クリュセとはすなわちマレー半島ないしスマトラである、などと単純に言ってしまっては、問題の半面を見落としてしまうことになるだろう。
メラやプリニウスが否定的な形で記しているように、すでに1世紀には、クリュセ・アルギュレ両島は単に金銀を豊富に産出するというだけでなく、その名の通り島自体が金銀で出来ている、という伝説が生じていた。「金島」という抽象的な名前が人々の想像力を刺激し、理想化された黄金郷のイメージが作り出され、それが一人歩きを始めているのである。
クリュセとアルギュレに関する記事は、その後のヨーロッパ世界では、ローマの著述家ガイウス・ユリウス・ソリヌス(Gaius Julius Solinus, 3世紀)の『著名事物集成』(Collectanea rerum memorabilium)、カルタゴの著述家マルティアヌス・カペラ(Martianus Capella, 365頃-440頃)の『メルクリウスとフィロロギア(文献学)の結婚』(De nuptiis Mercurii et Philologiae)、セビリャ大司教イシドルス(Isidorus episcopus Hispalensis, 560頃-636)の『語源』(Etymologiae)など、多くの書物に受け継がれてゆく。
中世ヨーロッパでは、キリスト教的世界観の影響により、大地は平たい円盤になっている、というイメージが一般化する。大地はオケアノス(Ōkeanos [Okeanos]; ギリシア神話で世界を取り囲むとされた大河。英語のオーシャン ocean の語源)によって丸く囲まれており、世界の中心には聖地イェルサレムが位置する、と考えられていた。そして、アジアやアフリカなどの辺境の地には、単脚族(スキアポデス)や無頭族(ブレミュアエ)、あるいはモノケロス(ユニコーン)やグリュプス(グリフォン)、フォイニクス(フェニックス、不死鳥)などといった、様々な怪物が住んでいると考えられていた。
こうした中世キリスト教的世界観を示す世界図に、「マッパ・ムンディ」(Mappa mundi)と呼ばれる世界絵図がある。マッパ・ムンディとはラテン語で「世界の布」という意味で、英語で地図を意味する「マップ」(map)の語源ともなっている。そして、これらマッパ・ムンディの中にも、クリュセ・アルギュレを描いたものがある。
たとえば、代表的なマッパ・ムンディに、1300年頃に作成されたと推定されている「ヘレフォード図」と呼ばれる世界図がある。この呼び名はイングランド西部のヘレフォード市にあるヘレフォード大聖堂(Hereford Cathedral)に所蔵されていることに由来するもので、作者は、同寺院の僧侶であったリカルドゥス・ド・ベロー(Ricardus de Bello)だと推定されている。大きさは 1.65×1.34m で、現存するマッパ・ムンディの中では最大である。
中世ヨーロッパの多くの地図と同じように、この地図は東を上とし、中心に聖地イェルサレムを、そしていちばん上(つまり世界の東の果て)にエデンの園をそれぞれ配置している。そしてこの地図では、インド洋中に浮かぶタファナ島(Taphana)とアラビア半島との間に、「クリュセ」(Chryse)「アルギュラ」(Argyra)「オフィル」(Ophir)「フロンディシア」(Frondisia)の四つの島が描かれている。タファナ島は、ギリシア人やローマ人が「タプロバネ」(Taprobane)と呼んだスリランカ島のことである。またオフィルは『旧約聖書』に登場する地名で、黄金の産地として知られている。その正確な位置は不明であるが、紅海かインド洋沿岸のどこかであったらしい。なおフロンディシアは何に由来するものかよくわからない(織田武雄『古地図の世界』)。
なお、余談ではあるが、火星には「クリュセ平原」(Chryse Planitia. 英語読みではクライシー)と「アルギュレ平原」(Argyre Planitia. 英語読みではアージャイル)という地名がある。この地名は、イタリアの天文学者ジョヴァンニ・ヴィルジニオ・スキャパレリ(Giovanni Virginio Schiaparelli, 1835-1910)が、1877年の火星大接近の際に作成した火星図(*)の中で、この伝説上の金銀島の名にちなんで名付けたものである。クリュセ平原は、1976年7月20日にNASAの無人火星探査機ヴァイキング1号(Viking I)が軟着陸した場所でもある。
(*) 火星の「カナレ」(canale; 複数形はカナリ canali. 溝、水路)が記載されたことで有名。この「カナレ」が「カナル」(canal; 運河、人工水路)と英訳され、火星の知的生命が大規模な潅漑水路を作っている、という「火星の運河」説を広めることになった。今日では、運河の存在自体が錯覚によるものとして否定されている。