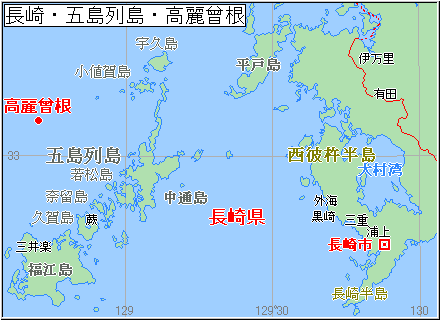
まんりがしま
1865年3月17日(元治2年=慶応元年二月二十日)金曜日、12時半頃。
長崎に建設されたばかりのカトリック教会堂「日本二十六聖人教会」――通称「大浦天主堂」――を、老若男女15名ほどの近隣の住民が訪れた。
大浦天主堂は、開港後の長崎に設置された居留地に住むフランス人のために、パリ外国宣教会のフランス人宣教師ルイ=テオドール・フューレ(Louis-Théodore Furet, 1816-1900)、ベルナール・タデー・プティジャン(Bernard Thadée Petitjean, 1829-84)らによって建設されたもので、前年の末に落成した。正式名称の「日本二十六聖人教会」(「二十六聖殉教者堂」「日本二十六聖殉教者天主堂」等とも表記される)は、1597年2月5日(慶長元年十二月十九日)に豊臣秀吉の命により長崎で処刑され、1862年になってローマ教皇ピウス9世(在位1846-78)により列聖された26名の殉教者、いわゆる「日本26聖人」を記念してつけられたものである。この天主堂は当時、「フランス寺」と呼ばれ、ものめずらしさから見物に訪れる者が多かったという。もっとも、開国したとはいうものの、依然としてキリシタン禁教政策を取り続けていた幕府は、宣教師たちが日本人に布教活動を行うことに対する警戒をとり続けていた。
プティジャン神父は彼らを招き入れたのち、祭壇の前にひざまずいて祈りを捧げ始めた。と、その時、彼らの中から女性が三人、神父に近づいてきた。そして、そのうち50代の女性がひとり、胸に手を当てて日本語でささやきかけた。
――ワレラノムネ、アナタノムネトオナジ。(warera no moune Anata no moune to onaji.)
プティジャンは、この言葉を「ここにおります私共は、全部あなた様と同じ心でございます」と解している。「本当ですか?」と問いただしたプティジャンに対し、彼女はさらに、自分たちは近くの浦上(うらかみ)村(現在は長崎市の一部)から来たことを告げ、そしてこう言った。
――さんた・まりあノゴゾーワドコ? (Santa Maria gozo wa doko?)
彼らは、幕府による苛烈なキリシタン弾圧の中で、浦上村で仏教に偽装しながらキリシタンの信仰を密かに伝えてきた者たち――すなわち、潜伏キリシタン(いわゆる「かくれキリシタン」)だったのである。キリシタン研究者の片岡彌吉(1908-80)は、この女性は、イサベリナ(杉本)ゆり(1815-93)という熱心なキリシタンだったと推定している。
この後、潜伏キリシタンの大部分は、仏教への偽装をかなぐり捨ててカトリックへと復帰してゆく。だが、あまりに長きに及んだ潜伏と偽装、そして外部世界との断絶のために、彼らの信仰は、本来のカトリックの教義とは大きく異なるものに変質していた。このため、彼らの一部は、自分たちの信仰はカトリックとは異なるとして、独自の信仰を守り続けた。現在、学問的には、「かくれキリシタン」とはこの後者のグループのみを指して用いられている(ただし、研究者によっても若干意味合いが異なる)。
カトリックに復帰した人々にとっても、しばらくは苦難が続いた。大浦天主堂と結びつくことによって、自分たちの信仰を公然と明らかにし始めた浦上のキリシタンたちを、幕府は慶応3年(1867)に摘発する。この直後に幕府は倒壊するが、代わって登場した明治新政府も依然として禁教政策を維持し続けたばかりでなく、浦上村民約3400名全員を流罪に処す、という強硬手段に出た。世に言う「浦上四番崩れ」(浦上教徒事件)である。神道イデオロギーに基づく「王政復古」により成立し、「祭政一致」を掲げた明治政府にとって、キリスト教徒は排除されるべき存在にすぎなかったのだ。さらに、明治元年(1868)には五島列島で激しい迫害(五島崩れ)が始まり、続いて明治4年(1871)には深堀(現在は長崎市の一部)一帯のキリシタンが摘発される(深堀一件、伊万里県キリシタン事件)。しかし、これら一連の迫害は、欧米諸国の厳しい批判を浴びることになった。このため1873年(明治6)2月、政府はキリシタン禁制の高札を撤去、浦上の信徒を釈放した。以後、キリスト教はなし崩し的に黙認されることになる。
話を「キリシタンの復活」の時点に戻そう。1865年4月18日(三月二三日)に浦上を訪れたプティジャン神父は、当時、浦上でただひとりの水方(洗礼を授ける役)であったドミニコ又市(Dominique Mataitchi, 1820?-70)というキリシタンから、『天地始之事』(てんちはじまりのこと)と題された書物を手渡されている。これは、潜伏キリシタンたちが、密かに口伝として伝えてきた『聖書』の物語を書きとめたものであった。
もっとも教会側ではその後、この書物は真実の信仰とはかけ離れた、取るに足らぬものと判断して打ち捨ててしまったらしい。のちにこの書物は、1931年(昭和6)になって、かくれキリシタン研究の先駆者であった田北耕也(1896-1994)によって、長崎県西彼杵(にしそのぎ)郡黒崎村(現在は長崎市の一部)で再発見されている。この書物は今日までに長崎および外海(そとめ)地方(西彼杵半島の西岸部)と五島列島で10本ほど発見されているが、いずれも文政(1818-30)から大正(1912-26)にかけて作られた写本で、原本の成立年代は明らかにはなっていない。
確かにこの書物は、奇妙といえばずいぶん奇妙なものである。この書物には、『聖書』でいえばおおむね天地創造、人類の誕生と堕落、ノアの洪水(以上《創世記》)、イエス・キリストの誕生と受難(《四福音書》)、そして世界の終末(《ヨハネの黙示録》)にあたる物語が収められているのだが、その内容は、日本の土着信仰と融合したりするなどして大きく変質している。例えば、「あだん」(アダム)と「ゑわ」(エヴァ)の子は「ちころう」「たんほう」という兄妹で、この兄妹二人が結婚して子孫を増やしたことになっていたり、「丸や」(聖母マリア)が「ろそん」(ルソン)の帝王「さんぜんぜ十す」の求婚をしりぞけるために、夏に雪を降らせるという奇蹟を起こす、という『聖書』のどこにもない話が延々と語られたり、「御身」(イエス・キリスト)の受難は、「べれん」(ベツレヘム)の帝王「よろうてつ」(ヘロデ)によって、身代わりとして殺された44444人の幼児の死をつぐなうためのものとされていたり、「御身」が仏僧に対して、仏とは実は「でうす」(唯一神)なのだ、と説く場面があったりする。
ところで、この『天地始之事』では、《創世記》(6:5-9:17)の「ノアの洪水」にあたる物語もやはり日本化されており、九州各地に伝わる、津波により海に沈んだ島の伝説と結びつけられて語られている。
ここでは、同書の最も優れた写本とされている下村善三郎旧蔵本(善本、文政本)(*)をもとに、その内容を見ていくことにしよう。この写本は田北耕也が西彼杵郡三重村(現在は長崎市の一部)で入手したもので、その筆記年代は不確かではあるものの、文政年間(1818-30)と推定されている。
(*) この写本は田北『昭和時代の潜伏キリシタン』、『日本思想大系』、中城忠〔写真〕/谷川健一〔編〕『かくれキリシタンの聖画』などに翻刻されている。ここでは主として『かくれキリシタンの聖画』から引用した。また、強調は引用者による。以下同じ。
――世の中に人間が次第に増えてくるにしたがい、悪事も次第にひどくなってきた。これを悲しんだ「でうす」は、「ぱつぱ丸じ」という帝王にお告げを下した。
「此寺の獅子駒(ししごま)の目、赤色になるときは、津浪にて世は滅亡」
田北耕也によれば、「ぱつぱ」とはローマ教皇(パパ Papa)、また「丸じ」とは殉教者(マルチル màrtir)のこと。つまり「ぱつぱ丸じ」とは「殉教した教皇」というほどの意味になる。初期の教皇の大部分は殉教したとされているが、ここでは特にそのうちの誰かを指しているというわけではないようである。《創世記》のノアにあたるのがこの人物である。また「獅子駒」というのは狛犬のこと。「此寺」というのは、ここで何の説明も無く唐突に出てくるもので、どこの寺かは明らかではない。キリシタン時代には教会堂のことも「寺」(南蛮寺)といったが、「獅子駒」があることを考えると、ここではおそらく仏寺がイメージされているのだろう。
さて、「でうす」のお告げを受けた「ぱつぱ丸じ」は、日ごとに寺に通って獅子駒の目を確かめる。寺に手習いに来たこどもたちがその様子を見る。そのうちひとりがいぶかしんで、
「いかゞにて、獅子駒は拝(おがま)るゝ哉(や)」
と言うと、別のこどもが
「獅子の目、赤色になる時は、此世界は、波にて滅亡する」
と答える。するとまた別のこどもが笑って、
「さても、おかしき事、塗りたら、すぐに赤くなるが、滅亡はおもいもよらぬ」
と言って、目を赤く塗ってしまった。
「ぱつぱ丸じ」がいつもの通り参詣すると、獅子の目が赤くなっている。これに驚いた「ぱつぱ丸じ」は、かねて用意しておいたくり舟(丸木舟)に自分のこどもたちを乗せた。「ぱつぱ丸じ」には七人のこどもがいたが、兄一人だけは足が弱かったので、残さざるをえなかった。するとたちまち、「でうす」の予言通りに大波が天地を驚かし、あっという間にあたりはただ一面の大海になってしまった。
ここで原文を引用しよう。
右の獅子駒、海の上を走り、乗り遅れたる壱人の兄、背に負ふてぞたすけける。其汐三時にさつとひき、ありおふ嶋にぞ、やすらい居る。然る所に、おくれし兄を、獅子乗せ負ふて来りけり。
異本(松尾久市本、1926年(大正15)筆写)では、この場面はより詳細かつ劇的に描写されている。(田北『昭和時代の潜伏キリシタン』より引用。)
右の獅子駒うみの上をはしり、のり送[ママ]れたる兄を、せおい来たりて船にのする。夫れより板やしやくしにてかく、万里が島の見えろがな。あり王島の見えろがなとかく。さすればかすかに見ゆるあり王島。そのしまたよりに、かきつくる。今にぺーろんそのときのまねとなり。
「ペーロン」というのは長崎の伝統行事で、一種のボートレースである。ここでは、それが「ぱつぱ丸じ」が「あり王島」を目指して丸木舟を漕いでいく様子を真似したものだとされているわけである。これについては、後ほど詳しく説明する。
こうして「ぱつぱ丸じ」の一家は一命をとりとめたが、波に呑まれて溺死した数万の人々は、「べんぼう」(リンボ Limbo。「辺獄」「地獄の辺土」「古聖所」などと訳される。地獄と天国の中間で、キリスト出現以前に死んだ善人や、洗礼を受ける前に死んだ幼児などの霊魂が住むところ。ここでは地獄と混同されている)に墜ちてしまった。――
「ありおふ島」ないし「あり王島」は《創世記》のアララト山にあたる。この島は文政本では単独で現れるが、松尾久市本では「万里が島」とセットになっている。また松尾久市本では、「獅子駒」の目を赤く塗ったこどもの科白が「ぬりたらすぐに赤くなるが、万里もある島のめつぼうは、おもいもよらぬ」となっている。
それでは、この「ありおふ島」とは何か。これについてはいくつかの説が出されているが、はっきりしたことはわかっていない。
まず田北耕也は、「有り合う島」つまり「たまたま有り合わせた島」とする解釈と、「有王島」とする解釈の二つを示している。
「有王」(ありおう)というのは『平家物語』の登場人物で、俊寛僧都に仕えた侍童とされている。俊寛(1143?-79?)は後白河院の近臣で、治承元年(安元3年、1177)の平氏打倒クーデタ未遂事件(鹿ヶ谷の陰謀)に連座し、平康頼・藤原成経とともに薩摩国の「鬼界ヶ島」(薩摩硫黄島説、喜界島説などがあるが未詳)に流罪になった人物である。康頼と成経は翌年恩赦となったが、ひとり俊寛だけは赦されず、島で没したという。『平家物語』によれば、鬼界ヶ島を訪ねてきた有王がその最期を看取り、そして俊寛の遺骨を高野山奥の院に納め、自ら出家して菩提を弔ったという。ただし、俊寛が亡くなった時期は明らかではなく(赦免されなかっのたはその時点ですでに死去していたから、とする説もある)、そもそも有王なる人物が実在したかどうかも定かではない。とはいうものの、確かに九州の島とかかわりのある人名ではある。
また民俗学者の谷川健一(1921-)は、「有王島」を沖縄の「ニライ・カナイ」伝承と結びつけている(谷川「三井楽紀行・常世幻想」、同『わたしの「天地始之事」』)。「ニライ・カナイ」とは海の彼方にあるとされる異界で、神々がこの島からやってくるとされている。この伝承は、『古事記』『日本書紀』『風土記』『万葉集』などに見える「常世国(とこよのくに)」とのとの関連性が指摘されており、またその常世国は、中国の「蓬莱」伝承との関連性が指摘されている。
「ニライ・カナイ」とは「ニライ」と「カナイ」の対語であるが、この呼び名には「ニルヤ・カナヤ」「ニライスク」などいくつかのヴァリエーションがあり、そのうちひとつに「ニライ島」と「アロウ島」というものがある。この「アロウ島」に「有王島」という字が当てられたのではないか、という。
かつて柳田國男(1875-1962)は、「根の国の話」(1955、のち『海上の道』(1961)に収録)の中で、五島列島の福江島(長崎県五島市)西端の「三井楽」(みいらく)という地名は古くは「みみらく」であったが、これは「ニライ」に由来するものではないか、と主張した。谷川氏はこの説を援用して、ニライ・カナイの伝承は北九州にまで及んでいたのではないか、としている。しかし、文政期に「アロウ島」という言葉が北九州でも使われていた、という根拠はない。
さて、この物語がノアの洪水の物語を原型としていることは、『天地始之事』という書物の性格からいっても動かしがたいところである。しかし、細かく見ていくと、話の展開はかなり異なっている。例えば、ノアの洪水は「四十日四十夜地上に降り続いた」雨によって引き起こされたものだとされているが、ここでは一瞬の大津波ということになっているし、「くり舟」というのも、巨大な「方舟」とはだいぶ異なる。
特に大きな違いは、「獅子駒」が登場してくることである。この「獅子駒」の目が赤くなると津波が起きる、という神託が下され、それを信じなかったこどもがわざと目を赤く塗ったところ、本当に津波が起きてしまった――という話の展開は、《創世記》とは何の関係もなく、むしろ東アジア各地に伝わる洪水伝承と共通して見られるものである。
この種の伝承は、古くは後漢末の学者・高誘による『淮南子(えなんじ)』(淮南(わいなん)王劉安(?-前122)の編纂させた書物)の註釈書、『淮南鴻烈解』(後漢建安17年=212)に見られる(なお、『淮南鴻烈解』を『淮南子』の正式な題名とする説があるが、誤り)。
歴陽(現在の安徽省和県)は淮南国の県名である。今は江都に属する。昔、老婆がいて、常に仁義を行っていた。あるとき、二人の書生が訪れて言った。「この国は沈没して湖になるはずだ。」二人は老婆に「東の城門の敷居に血がついているのを見たら、すぐに北の山に走って登りなさい。振り返ってはならない」と告げた。このときから老婆はことごとに行って門の敷居を見るようになった。すると門番がその理由を尋ねたので、老婆はこの話をした。その晩、門番はわざとニワトリを殺して、その血を門の敷居に塗った。翌朝、老婆は早くに出かけて門を見て、血がついているのを見てすぐに北の山に登った。するとその国は沈没して湖となった。老婆が門番にそのことを語ってから、わずか一晩のことであった。
(『淮南子』俶真訓・高誘註、現代語訳。服部宇之吉〔校訂〕『淮南子 孔子家語』(冨山房、1915)を参照した。)
いわゆる歴陽湖の伝説である。なお、この一文には出てこないが、この話には本来、最後に老婆がうっかり振り返ってしまい、石と化してしまう、という結末が含まれていたらしい。
このたぐいの筋の沈没伝承は、干宝『捜神記』(4世紀)、祖沖之『述異記』(5世紀)など多くの文献に記されており、また中国各地に様々な形で伝説として残っている(*)。さらに、朝鮮半島でも咸鏡北道明川郡の「長淵湖」伝説、咸鏡南道定平郡の「広浦」伝説などが知られており(**)、そして日本でも、『今昔物語集』(12世紀)や『宇治拾遺物語』(1220頃)に記されているほか、徳島県の「お亀千軒」伝説や大分県の「瓜生島」伝説、そして五島列島の「高麗(こうらい)島」伝説などが知られている。地形的な理由からか、中国や朝鮮半島では町が湖底に沈むというパターンが多いのに対し、日本では島が海中に沈むというパターンが多いようである。
(*) マックス・カルタンマルク「中国における水没した町の伝説」『東方宗教』第59号(1982年5月)、小南一郎「水底の都市――罪の伝承をめぐって」『世界口承文芸研究』第6号(1985年3月)、伊藤清司『中国の神話・伝説』(東方書店、1996)等。
(**) 孫晋泰『朝鮮民譚集』(郷土研究社、1930)、崔仁鶴『朝鮮伝説集』(日本放送出版協会、1977)。
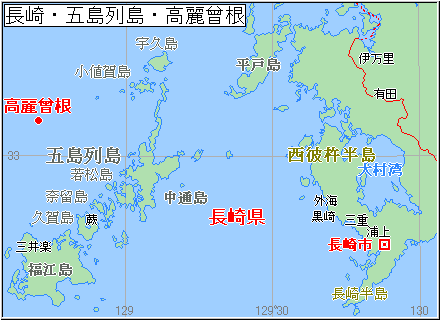
このうち「高麗島」伝説は、柳田國男が「高麗島の伝説」(1933年発表、のち『島の人生』(1951)に収録)で紹介したことでよく知られている。五島列島の小値賀(おぢか)島の西方海上、より正確に言えば北緯33度6分9秒・東経128度42度7分の地点に、「高麗曾根」(こうらいそね)または「高麗瀬」という浅瀬が実在する。最も浅い地点の水深は4mという。伝説によれば、この浅瀬はかつて高麗島という島のあった痕跡なのだという。
なお、高麗は朝鮮半島の統一王朝(918-1392)の名であるが、これと「高麗島」ないし「高麗曾根」との関係ははっきりしない。
柳田は、この伝説を以下のように紹介している。
高麗島は世に稀なる富裕の島であつたといふ話である。島の人たちは、此荒海のとなかに於て、優れたる陶器を製して生計を立てゝ居た。それが世上に伝はつて高麗焼と称せらるゝ、と思つて居た人が附近の島々には多かつた。[…]島の沈んだ跡の高麗瀬に往つて見ると、今でも数限り無い昔の陶器の破片がぐわらくと底波にゆられる音が、手に取るやうに聞えると謂ふのみか、稀には又漁夫の延縄[はへなは]にかゝつて、引上げたといふ話さへ残つて居る。
なお、「高麗焼」というのは、正しくは朝鮮半島産の陶磁器のことである。
昔高麗島には霊験の至つてあらたかな、一体の石の地蔵菩薩がおはしました。信心深い人々の夢枕に立つて、我顔が赤くなつたらば大難の前兆と心得て、早速に遁[のが]れて命を全うせよといふ御告げがあつた。邪慳の輩[ともがら]のみは却つて之を嘲り、戯[たわむ]れに絵具を以て地蔵の御顔を塗つて、驚き慌てゝ遁[に]げて行く者の魯[おろ]かさを見て笑の種にしようとしたのであつたが、前兆は尚まさしく、島は一朝に海の底に落ち沈んで、残つた者の限りは悉[ことごと]く死んでしまつたといふのである。
この石地蔵は、久賀(ひさか)島(長崎県五島市)の蕨地区に「どうして渡つて来られたかちやんと渡つて来て」、現存している。「外では見られぬ位に御頸の長い」異様な地蔵である。なお、この伝説に関しては、赤くなったものは恵比寿像の顔だとするヴァリエーションも存在する。
なお、この島の名は「高麗島」ではなく「蓬莱島」だとするヴァリエーションも存在する。おそらくは「コーライ」と「ホーライ」との発音の類似から混用が生じたのだろうが、高麗と蓬莱とでは意味がだいぶ異なる。周知の通り、「蓬莱島」とは、中国の神仙思想でいうところの東方海上の神仙の島の名であり、そこでは時間の流れ方が人間世界とは異なるとされている。先述したようにこの「蓬莱」伝承は、日本の「常世国(とこよのくに)」伝承や、また浦島子(浦島太郎)の伝説、それにニライ・カナイなどともつながりを持つ。
ちなみに、高麗曾根については、1977年(昭和52)8月に長崎県生物学会による潜水調査が行われている。しかし、このとき人工遺物は一切発見されなかった。高麗曾根には石垣らしきものが沈んでいるといわれてきたが、このときの調査では、これは自然現象によるもの(砂岩性柱状節理)であることが確認されている。つまり、高麗島が実在し、それが海底に沈んだ、という根拠は何一つ確認されなかったことになる(坂田邦洋「「高麗島の伝説」の考古学的検討」、山本愛三「沈降伝説の島・高麗曽根調査の想い出」)。
五島列島は潜伏キリシタンの多かった地域である。彼らは、寛政年間(1789-1801)に、福江藩(五島藩)による開拓移民の募集に応じて、迫害の厳しかった大村藩領の外海地方から移住してきた人々の子孫である。そのため、長崎や外海の潜伏キリシタンとはもともと関係が深く、先述したように『天地始之事』も伝わってきている。したがって、「ぱつぱ丸じ」の物語はこの伝説に影響を受けたのではないか、とする説もある。
しかし、西九州にはもう一つ、この「高麗島」伝説と極めて良く似た「万里ヶ島」の伝説も伝わっているのである。二つの伝説は、同じ話が別々の名前で伝わったのではないかと思われるくらいそっくりである。ただし、高麗島が高麗曾根というはっきりとした実体を伴っているのに対し、万里ヶ島がどこにあったか、ということは極めて曖昧模糊としている。
先に見たように、『天地始之事』の一異本には「万里が島」という地名が登場する。もっとも、同書では海に沈んだのが「万里が島」なのか、たどりついた先が「万里が島」なのかはっきりせず、いささか混乱させられるのであるが、いずれにせよ、この書物は「万里ヶ島」伝説のヴァエーションと見ることができる。
というわけで――前置きが随分と長くなってしまったが、この「万里ヶ島」伝説について見てゆくことにしよう。
万里ヶ島伝説についてはっきり口碑として残っているものとしては、鹿児島県の甑島(こしきじま)列島(*)の事例が知られている。
(*) 薩摩半島西方海上の東シナ海に浮かぶ、上甑島・中甑島(平良島)・下甑島の三島からなる島々。かつては薩摩郡里村・上甑村・鹿島村・下甑村の4ヶ村があったが、2004年10月の市町村合併により薩摩川内市の一部となった。
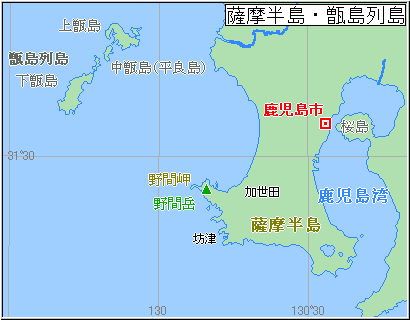
民俗学者の櫻田勝徳(1903-77)は、1933年(昭和8)1月に甑島列島を訪れた際にこの伝説を聞いている。
この島[上甑島]の近くに昔万里が島という小島があつたが、何時の頃かこれが海中に沈んでしまつた。今でも万里焼という陶器が残つているが、これは昔この島で造つたものだと言われている。(櫻田「甑島遊記」(四))
柳田國男は「高麗島の伝説」の中で、この話を櫻田からの伝聞として紹介し、さらに
現に下甑の瀬々の浦[瀬々野浦。下甑島西岸の港]の某家に、その万里が島焼の茶碗といふものが秘蔵せられて居る。内側に細かな文字が書いてある外に、その糸底には万里寉[「寉」(カク)は「高く上がる」の意、また「鶴」の俗字]の三文字が有るといふから、其道の人に尋ねたら産地もわかり、同時に伝説の年代も知れることゝ思つて居る。
と付け加えている。なお、柳田の監修した『日本伝説名彙』にもほぼ同様の記事があるが、そこでは「万里寉」ではなく「万里窪」となっている。いずれが正しいかは不明である。ちなみに柳田は「万里」を漢音で「ばんり」と読んでいるが、後でも見るように、他の文献では呉音で「まんり」と読んでいることの方が多い。
この茶碗は現在所在不明のようであるが、これとは別に、薩摩川内市立下甑郷土館(旧・下甑村立歴史民俗資料館)には万里ヶ島から将来したとされる言い伝えを持つという陶器(万里ヶ島焼)がいくつか収蔵されているという。中には底面に「成化年製」(「成化」は明の年号、1465-87)と書かれた鉢もある。
なお、一説に、近世に甑島では密貿易が行われており、その密貿易を示す隠語として「万里ヶ島に行って来る」という言葉が使われていたという(徳留秋輝「網代」)。
ただし、この「万里ヶ島焼」を実見した山本節(たかし)氏(浜松学院大学教授、元静岡大学教授、伝承学。1939-)が、柴垣勇夫氏(静岡大学教授、陶磁史)に写真鑑定してもらったところによれば、これらはいずれも18世紀後半から19世紀前半にかけて製作された伊万里焼(有田焼)だったという(山本「島嶼陥没の伝承」、同「万里島焼のはなし」)。なお「成化年製」という銘文は、実際の製造年代とは無関係に、中国製陶磁器を模倣してつけられることがよくあった。
いずれにせよ、海に沈んだ島というだけでなく、陶磁器を造っていた島という点でも、高麗島伝説と万里ヶ島伝説は酷似している。
また、これとは別に、下甑島北部の藺落(いおとし)浦付近には、「茶碗島」の伝説が伝わっている。この茶碗島はべつに海に沈んだわけではなく、甑島列島の西方海上にあって、天気のよい日には見えるとされている。そして、その名の通り、やはり陶磁器を産した島だとされているのである。もとより、現実にはそのような島は存在しない。
文献記録をたどってゆくと、万里ヶ島に関する伝承は、すでに17世紀後半には成立していたことがわかる。
まず、元禄2年(1689)に江戸と大坂で刊行された著者不明の奇談集『本朝故事因縁集』に、以下のような記事がある。
薩州野間御崎の明神
唐土万里島[まんりのしま]に仁王の像を立てて、末世に至り仁王の面赤く成る時島滅ぶと言伝ふ。時に悪人あつて仁王の面を朱にて染めければ、島過半沈んで人皆溺れ死す。此の時明神舟二艘両手に持ちて、薩州野間庄に飛び来り給い、松尾[まつのを]明神と現じ、舟の守護神と成り給ふ。異国本朝の舟、難風に逢ひ漂波の時は立願祈誓すと、云々。
(『本朝故事因縁集』巻5・120。『京都大学蔵大惣本希書集成』第8巻, pp. 77-78 より引用。ただし、カタカナをひらがなに直し、また送り仮名を直すなど表記を改めた。[……]内は引用者註。)
ここでは「万里島」は「唐土」すなわち中国にあった島だとされており、仁王の面を赤く塗ったために沈んだことになっている。そして、そこから飛んできた「明神」が「薩州野間御崎」に祀られ、航海の守護神となったとされている。神像が沈んだ島からやってくる、という点では、高麗地蔵の話も想起される。もっとも、この文章からは、島の沈没と明神との関係がいまひとつ明らかでない。
薩州(薩摩国)野間御崎というのは、薩摩半島の西端にある野間岬(鹿児島県川辺郡笠沙町、市町村合併により2005年11月から南さつま市となる予定)のことである。ただし現在、この地にはこのような伝承はまったく伝わっていないという(『笠沙町郷土誌』上、山本「島嶼陥没の伝承」)。また、「野間御崎の明神」とは、野間岬にほど近い野間岳(標高 591.1m)の山腹にある野間神社のことと思われる。この神社の創建年代ははっきりしていないが、戦国時代には島津忠良(1492-1568。日新斎。島津氏中興の祖とされる)の篤い崇敬を受けたという。
一方、「松尾(まつのお)明神」とは、酒造りの神として知られる京都の松尾(まつのお)大社のことである。松尾神社の祭神は大山咋神(オオヤマクイノカミ)と中津島姫命(ナカツシマヒメノミコト)(市杵島姫命(イチキシマヒメノミコト))だが、単に「松尾明神」といった場合はふつう大山咋神を指す。もっとも、宗像(むなかた)三女神(*)の一柱である市杵島姫命のほうが、「舟の守護神」にはふさわしい。
(*) 宗像大社(福岡県)の祭神である三人の女神、田心姫(たごりひめ)神・湍津姫(たぎつひめ)神・市杵島姫神のこと。古くから航海の神として信仰されてきた。
ところが――実は、野間神社の祭神は「松尾明神」とは何の関係もないのである。
野間神社の現在の祭神は、瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)と鹿葦津姫(カシツヒメ)(木花開耶姫(コノハナサクヤビメ))の夫婦神、それにその三柱の子、火闌降命(ホノスソリノミコト)(火照命(ホデリノミコト)=海幸彦)・彦火火出見尊(ヒコホホデミノミコト)(山幸彦)・火明命(ホノアカリノミコト)である。『古事記』や『日本書紀』の所伝によれば、高千穂に降り立ったニニギノミコトは、「笠沙之御前(かささのみさき)」(『古事記』。『日本書紀』では「笠狭之碕」)で妻となるコノハナサクヤビメと出会ったとされている。この「笠沙之御前」は一説に現在の野間岬だとされているが、実のところ明確な根拠があるわけではない。なお、現在の「笠沙」という町名は1923年(大正12)につけられたもので、古代の地名と直接のつながりはない。
ところが、薩摩藩が幕末に編纂した『三国名勝図会』(五代秀堯+橋口兼柄〔編〕、天保14年=1843序)巻之27によれば、この神社はかつては「野間嶽権現社」と呼ばれ、野間岳の山頂にあって東西二宮に分かれており、東宮には瓊瓊杵尊と鹿葦津姫が、そして西宮には「娘媽神女」とその従神である「千里眼」「順風耳」が祀られていたという。本来、西宮の祭神は火闌降命・彦火火出見尊・火明命の三柱だったのだが、後から合祀された娘媽神女に取って代わられてしまったらしい。それが、明治初年の廃仏毀釈の際に娘媽神女が追い出されてしまい、元に戻されたのである。
同書が現地の伝承として記すところによれば、娘媽神女というのは中国・福建の林家の娘で、生まれつき不思議な力を持っていた。あるとき、機(はた)の上で目をつぶっていた彼女は、急に顔色を変えた。母親が怪しんで呼び覚ましたところ、彼女は「父さんは助かったけれど、兄さんは溺れ死んだ」と泣き叫んだ。果たして、海に出ていた父と兄は嵐に襲われ、父は助かったが兄は溺死していた。彼女は自ら航海の守護神とならんとして海に身を投じた。その遺体は生けるがごときありさまで加世田(鹿児島県加世田市、2005年11月より南さつま市となる予定)の海岸に流れ着き、この地に祀られたのだという。この話は西川如見(1648-1724)の『長崎夜話草』(享保5年=1720)(一之巻・「野麻権現并日御崎観音之事」)にも紹介されており、当時は広く知られていたようである。
(*) なお、「娘媽」の読み方であるが、実ははっきりしない。西川如見は、『増補華夷通商考』(宝永5年=1708)巻二では「姥媽」(ノフマ)、『長崎夜話草』では「老媽」(らうま)と書いており、このことからすると「ノウマ」または「ロウマ」と読まれていたらしい。また、『笠沙町郷土誌』上巻によれば、現地ではこの女神を「ロバさん」と呼んでいるという。
「娘媽神女」というのは「媽祖」(まそ)の別名である。媽祖は「天妃」「天后」「天后娘娘」「天上聖母」などとも呼ばれ、中国の中南部で広く信仰されている航海守護神である。
広く信じられているところによれば、媽祖はもともと北宋(960-1127)初期に福建にいた、林黙娘(960?-87?)という女性であったという。彼女が女神となったいきさつについては様々な説があってはっきりしないが、上述の話はそのヴァリエーションの一つである。
野間権現に娘媽神女が祀られるようになった時期ははっきりしないが、永禄年間(1558-70)かそれ以後に、中国船の安全を祈るため、航海目標として知られていた野間岳に祀られるようになったらしい。ちなみに野間岬のすぐ南にある坊津(ぼうのつ)(川辺郡坊津町、2005年11月から南さつま市となる予定)は、中世には筑前博多津(福岡県福岡市)・伊勢安濃津(三重県津市)とともに「日本三津」の一つに数えられた国際貿易港で、中国船や琉球船などが盛んに入港し、のちには南蛮貿易の基地の一つともなった港である。また、寛永12年(1635)に中国船の来航が長崎のみに制限されるようになった後も(もっとも、薩摩藩ではその後も坊津を基地とする密貿易が続けられていたらしいが)、華南方面から来航する中国船にとっては、野間岳は優れた航海目標であり続けた。そのため、この信仰は長崎に来航する中国商人らによって維持されてきたのである。
なお『長崎夜話草』などに、「野間」という地名は「娘媽」に由来する、という説が見えるが、これはこじつけである。「野間」という地名は、娘媽神女が祀られるずっと以前、14世紀後半の史料にすでに見えるからである。
それでは、この特異な祭神と、『本朝故事因縁集』の記事とは何か関係があるのだろうか。
金澤兼光という船大工が明和3年(1766)に刊行した、船に関する一種の百科事典『和漢船用集』では、「舟玉神」(船の守護神)について論じた中で、野間権現の祭神が媽祖であることを紹介し、さらに『本朝故事因縁集』の記事を引用している(巻第二)。しかし、媽祖と松尾明神の関係は特に説明されていない。
媽祖伝承の詳細な研究を行った歴史家の李獻璋(1914-99)は、この『本朝故事因縁集』の記事を取り上げ、「媽祖」は閩南(びんなん)語(福建省南部で話される中国語の方言、独立の言語とすべきとする意見もある)で「マーツォ」と発音するところから、これが「松尾」と混同されたのではないか、としている(李『媽祖信仰の研究』)。また、「神舟二艘両手に持ち」というくだりも、媽祖と類似しているという。松尾明神が海から飛び来った、という話も、媽祖の遺体が流れ着いた話と似ている。なお李は、遺体の話は、もともとは媽祖の木像が流れ着いた話だったのではないか、と推測している。
確かに、「媽祖」を当て字で「松尾」と書いたものを、酒造りの神として知られる松尾明神と混同した、ということはありそうなことではある。ただ、松尾明神の「松尾」は「まつお」ではなく「まつのお」と読むことや、現地では「媽祖」ではなくもっぱら「娘媽」と呼ばれていることなどを考えると、この説明には疑問が残る。とはいえ、そうとでも考えないと、祭神と全く無関係なはずの神の名が唐突に出てくる理由の説明がうまくつかないのではあるが。
いずれにせよこの記事は、野間権現を実際に見知った者が書いたものとはまず考えられない。とはいえ、全くの創作ということも考えにくい。おそらくは伝聞に基づく記事であろう。
また、厚誉春鶯廓玄という僧侶が正徳6年(享保元年、1716)に京都で刊行した奇談集『本朝怪談故事』には、以下のような記事がある。
野摩御崎[のまのみさき]面[おもて]を変ず
薩州野間の御崎の神は、往古、唐土万里の嶋にありける金剛力士の二王の像也。然るに、此二王の面[をもて]、赤く変じたる時は此嶋滅[ほろぶ]と皆人云へり。夫れ故にや、其色皆白し。然るに人ありて、彼二王の面に朱を塗ければ忽ち嶋動出て、海に沈没す。人皆溺死す。此時、明神舟に乗(て)薩州へ来り、野間の庄にて明神と現じ舟を守の神と崇む。今も異国本朝共に舟の難風に逢ふ時は、此明神に祷れば霊験新たに、其難を免[まぬか]る。今に至て面変ずれば凶事也とて諸人恐懼[をそれ]、敬ふ。又は松尾明神共号す。『因縁故事』に出たり。
(『本朝怪談故事』巻第二・第十二。高田衛+阿部真司〔校註〕『本朝怪談故事――校注索引』, p. 100 より引用。ただしカタカナをひらがなに改めた。)
この記事が『本朝故事因縁集』からの引き写しであることは、「『因縁故事』に出たり」とあることからも明らかである。ところが、よく見てみると、仁王像が野間岬の神そのものであったり、仁王像の色が白いとしたり、今でも仁王像の顔の色が変わるのが恐れられているとしたりするなど、余計なディティールが付け加わっている。おそらく春鶯が勝手に話を膨らませたのだろう。
児童文学者の巖谷小波(いわや・さざなみ)(1870-1933)は、『東洋口碑大全』上巻(博文館、1913)の中で、この伝説を「野摩の御崎」(第53話)として紹介している(なお、小波は「万里島」を「万重島」と誤っている)。出典は「因縁故事」とのみ記されているが、内容からみて、明らかに『本朝怪談故事』を引き写したものである(なお、巖谷〔編〕『大語園』第7巻(平凡社、1935)「の」の部・第30話「野摩の御崎」もほぼ同内容)。
ところで、先述したように、長崎の伝統行事のひとつに、ペーロンという一種のボートレースがある。
ペーロンは、もともとは旧暦五月五日の端午の節句に行われていたもので、「ペーロン」と呼ばれる漕ぎボートに数十名が乗り込み、太鼓や銅鑼をかき鳴らしつつ、「ペーロン、ペーロン、エッ」と叫びながら漕いで、その順位を競うというものである。
この行事自体は、もともと中国の長江流域以南で広く行われている「龍舟競渡」(ドラゴン・ボート・レース)が日本に輸入されたもので、沖縄にもこれとほぼ同じ「ハーリー」という競技が伝わっている。なお、「ペーロン」の「ロン」が「龍」の唐音であることは間違いないが、「ペー」が何に由来するものかについては説が分かれており、はっきりしていない。
長崎のペーロンは、明暦元年(1655)に中国船が持ち込んだものだとされている。しかし、ペーロンが日本に持ち込まれたのはもっと早かったらしい。平戸イギリス商館長リチャード・コックス(Richard Cocks, ?-1624. 在任1613-23)は、1617年5月28日(グレゴリオ暦6月7日、元和3年五月四日)付の公務日記の中で、平戸で「ピロ」(Piro または Pilo)という祭りを見たことを書き記している。これは「海中に標的をひとつ立てておき片側八ないし九挺の櫂の附いた小舟に乘って漕ぎ進み、最初にそこへ到逹した舟が勝つ」というものであったという。
ペーロン(ないし龍舟競渡)の由来や意味づけは必ずしもはっきりしているわけではないが、一般には、入水自殺した古代中国の詩人・屈原(前343?-前277?)と結びつけられて説明されることが多い。『史記』の「屈原賈生列伝」によれば、屈原は戦国七雄の一国である楚の重臣であったが、西方の大国・秦の脅威を説いて受け入れられず、讒言にあって放逐され、ついに楚の将来に絶望し、自ら石を抱いて汨羅(べきら)(川の名。湖南省北東部)に入ったという。伝説によればこの日は五月五日で、その屈原の霊を弔うために始められたのが端午の節句であり、ペーロンであるというのである。もっともこの話自体は、後世、屈原が神格化されてゆく過程でこじつけられたものと考えられている。また、屈原以外にも、伍子胥(ごししょ)(*)や曹娥(そうが)(**)など、水にまつわる非業の死を遂げた人物を祀ったものとされることも多い。
(*) ?-前484。春秋時代の楚の人。名は員(うん)、子胥は字(あざな)。『史記』「伍子胥列伝」によれば、楚の平王に父と兄を殺され、復讐を誓い亡命。流浪の末に呉王闔閭(こうりょ)(在位前515-前496)に仕え、兵法家の孫武とともに呉軍を率いて楚を打ち破り、滅亡寸前にまで追い詰める。のち、闔閭の後を継いだ夫差(在位前496-前473)と対立し、自害に追い込まれる。遺骸は長江に投げ捨てられたという。
(**) 『後漢書』「列女伝」が「孝女」として伝える女性。会稽(現在の浙江省紹興)の人。漢安2年(143)五月五日、彼女が14歳のとき、父が川で溺れ死んだ。彼女は嘆き悲しみ、自ら川に身を投じたという。
ところがコックスは、それとは全く異なる伝承を書き残しているのである。
コックスによれば、中国人の伝承では、ある王が賢者たちに「人間生活を支えるため地上で最善でしかも最も必要なもの」を挙げさせたところ、「ピロ」という賢者は塩を持ってきた。王が怒ってピロを海に投げ捨てさせたところ、荒天が続いて海から塩を取ることができなくなってしまった。そのため王は、ピロの霊をなぐさめるためにこの祭を始めたのだという。さらにコックスは、日本人は中国人とはまた別の話を伝えている、としてこう述べている。
日本人たちはこういっている。すなわち、彼[ピロ]は賢者であり、また偉大な天文学者であって、シナから離れた、カンボジャの海岸近くの或る嶋に住んでいた。そして彼の知識によって彼は彼の住んでいる嶋がやがて海中に沈下してしまうことを前以て知り、そしてそのことを住民に教えて、彼等に彼等を連れ去るための(ちょうど良い時)小舟や大船の準備をして欲しいと望んだ。しかし彼等は彼の言葉を嘲り笑った。しかしそれにも拘らず彼はちょうど良い時に自分自身のために準備を整えて他の土地の陸上に逃げて来たが、残りの住民は総べて嶋の沈んだ時死に絶えてしまった、と。
ここでは、沈んだ島の名前までは特に記されていない。
元禄3年(1690)から5年(1692)までオランダ商館付医師として日本に滞在したドイツ人博物学者エンゲルベルト・ケンプファー(Engelbert Kaempfer, 1651-1716. オランダ語読みでケンペル)は、著書『廻国奇観』(Amoenitatum Exoticarum Politico-Physico-Medicarum, 1712)の中で、このペーロンと沈没した島についての伝説をさらに詳しく書き記している。やや長くなるが、まとめて引用することにしよう。
日本人は一般に普通の茶を保有するのには,大きな陶器の茶壺を用いる。この壺の口は非常に小さい。もっぱら将軍や大名が用いるような上等の茶は,大抵磁器の茶壺に容れて貯蔵し,とくに通人になると真壺(まつぼ Maatsubo)と呼ばれている高価な有名な時代ものの茶壺を用いる。[…]
真壺とは本当の壺という意味で,この表現によっても,この壺が高価な逸品であることが窺われる。この壺は,今を去る古い昔,真瓜島(まうりがしま Maurigasima)で上等な陶土によって作られていた。言い伝えによると,この島の島民の道義が乱れたので,神様はこの島を海底へ沈めてしまい,現在ではそそり立った岩礁が若干海上に頭を出している以外跡形もないという。島の位置は台湾(たいわん Tejovaan, Formosa)の近くで、われわれの海図には,海が浅くて暗礁がある危険な場所として,点で記されている。この島の由来について,シナ人は次のように語っている。
真瓜島は,昔はその土地がすこぶる豊穣なことでよく知られた島であった。この島の陶土は飛切り質がよく,島の特産物の1つになっており,この陶土によって陶器の壺(vasa myrrhina)が作られていた。この製造によって得る島民の儲けは非常に大きく,かれらは贅沢の限りを尽し,尊大になった。人間は贅沢をし続けると,とかく悪習に染まり勝ちなものだが,ここでも御多分に洩れず,道義は地に墜ち,とくに神を蔑視するようになった。かれらは,神を畏れず貶すようになったので,神々はついに全島を海底に沈める決議を行なった。しかし島の王様扒竜(ペイロン Peiruun)は,敬神の念篤き高徳の士であった。ある日夢枕に神が現われ,伽藍の山門に安置されている二つの巨像の顔が赤くなったことを認めたら,直ちに小舟に乗って島を脱出し,命を失わないようにせよとのお告げを下した。
この巨像は仁王(におう Niwo)と呼ばれている仏法守護神を象った木像で,陰陽(いんよう Injo)の相を表し,阿吽(あうん Awun)の呼吸を示している。[…]この仁王の像は,(今でもそうだが)伽藍の前方の山門の両側に安置されていて,この島がやがて海底に陥没する合図を与えることになっていた。
扒竜王は,夢のお告げに従って,神罰を受けてやがて島は陥没の運命にあることを島民に報せたが,一般の嘲笑を買い,迷信家として島民から軽蔑されるようになった。島民の中の悪戯者がある夜ひそかに,誰にも気付かれないように仁王の像の所へ忍び寄り,その顔に赤い色を塗った。これを見た扒竜王は,人間の悪戯とは気がつかず,仁王の顔の色が変ったのは,てっきり神のお告げの合図であると思い込み,震え上って家族を引連れて島を去り,近くの南シナの福州(ふくしゅう Foksju)へ逃れた。
神を侮る悪戯者やその仲間は,これによって凶事が起るとは夢にも考えなかったが,やがてこの神を信じない全島民は,島と共に豊かな高価な陶土もろとも,波に呑まれ,海の藻屑となったのであった。毎年由縁の祭りを催し,この日にはかれらは,湾内に船を浮べ,居なくなった扒竜(ペイロン)の名を呼びながら,あちらへこちらへと船を漕ぎ回し,難民の姿を髣髴させる行事を行なう。かれらはこの祭行事を西日本へも導入した。
この高価な真壺は,今では干潮時に,島が陥没した附近の海底から掘り出されることがあるが,岩に附着してしまった真壺を壊れないように引き離すことはなかなか難しい。真壺には貝殻がへばり付いており,大抵形が非常に崩れてしまっている。真壺が見つかれば,この貝殻を取除かなければならないが,本物であることを立証するために,全部を取除かず,若干残して置くこともある。
(『廻国奇観』第3巻第13章第8節。エンゲルベルト・ケンペル/今井正〔編訳〕『日本誌(改訂・増補)――日本の歴史と紀行』(下), pp. 505-507.)
訳者の今井正氏は「マウリガシマ」(Maurigasima)を「真瓜島」と解釈しているが、これは明らかに「マンリガシマ」(万里ヶ島)の誤りである。あるいは誤植かもしれない。ケンプファーはこの話を「シナ人」から聞いたと述べているが、出てくる語彙のほとんどが日本語読みであることから考えて、おそらくは長崎で、日本人か中国人から、「中国の話」として日本語で聞いたのだろう(ちなみに長崎では、中国人はもともと日本人と混住していたが、ケンプファーが来日する直前、元禄2(1689)年に「唐人屋敷」に隔離されている)。
なお、ケンプファーはなにやらえらくもったいぶった説明をつけているが、「真壺」というのは中国製の茶壺のことである。この種の壺はもともと中国南部で作られたもので、本来は茶壺として作られたものではなかったのだが、14世紀初めごろから葉茶を貯蔵しておく容器として用いられるようになり、やがては美術品としても珍重され、日本製の模倣品も作られるようになった。そのため、模倣品と区別するために、輸入茶壺を「真壺」と呼ぶようになったのである。
ケンプファーは、遺著『日本誌』(Geschichte und Beschreibung von Japan, 1727刊)の中でも同じ話を記しているが、そこでは赤くなるものは仁王ではなく「木彫りの仏像」だとされている。また異伝として、
他の言伝えによると,この話が神社の前に据えられている唐獅子に繋っている。これによると王様ペーロンは夢のお告げによってではなく,縁起書(きがき Kigaki)によって唐獅子の眼が黄色くなったら,島が海中に没する寸前であることを示すものであることを識ったことになっている。これによると王宮の家老(かろう Karo)が,この予言の出鱈目を暴露しようとして,獅子像の眼を黄色く塗ったところ,王様は逃走したが,その島国は海中に沈んでしまったということになっている。
(『日本誌』第3巻第3章。今井正〔編訳〕『日本誌』上, p. 306.)
という話も載せている。
海に沈んだ陶器、という話は甑島や五島列島の伝承と一致するし、ペーロンの起源については『天地始之事』の一写本(松尾久市本)と一致する(*)。さらに赤くなるものについては、ご丁寧にも仁王像と唐獅子の二パターンを記している。ケンプファーの滞日は、『本朝故事因縁集』が刊行されたのとほぼ同時期である。当時の長崎では、すでに万里ヶ島の伝説がまことしやかに語り伝えられていたことがうかがえる。
(*) ただし、ケンプファーのこの記述は、1925年(大正14)に刊行された『長崎市史風俗編』にすでに紹介されている。松尾久市本の筆写はその翌年なので、ケンプファーの影響を受けた可能性も完全には否定できない。
それにしても、真壺は万里ヶ島で作られたものである、という奇妙な話はいったい何を意味するものなのだろうか。
安土桃山時代には茶壺の鑑賞が流行し、茶人や大名がこぞって茶壺を買い求めるようになった。そのため、文禄年間(1592-96)になると、中国製の壺が東南アジア方面、とりわけフィリピンのルソン島から輸入されはじめ、「呂宋(ルソン)壺」と呼ばれて珍重されるようになる。ルソン島から持ち帰った真壺を豊臣秀吉に献上し、数日のうちに大富豪となったという納屋(呂宋)助左衛門の伝説は、NHK大河ドラマ『黄金の日日』(1978)などでも有名である。
しかし、日本で「真壺」と呼ばれていた壺は、そもそも当の中国や東南アジアではたいした価値のあるものではなかったという。それが、海外からの輸入品であったために、ことさらに珍重されて高値で取り引きされたのである。
あるいは、真壺の出自をことさらに神秘化するために、このような「海に沈んだ真壺の島」の話が作られたのかもしれない。
ところで、ケンプファーによれば、万里ヶ島のあった場所は台湾の近くで、「われわれの海図には,海が浅くて暗礁がある危険な場所として,点で記されている」という。またコックスは、島は「カンボジャの海岸近く」にあったと述べている。これはいったいどこのことなのか。
1670年、アムステルダムで、オルフェルト・ダップル(Olfert Dapper, 1639-89)の『オランダ東インド会社遣清使節紀行』(Gedenkwaerdig bedryf der Nederlandsche Oost-Indische maetschappye, op de Kuste en in het Keizerrijk van Taising of Sina)という書物が刊行された。同書は1665-66年にオランダ東インド会社が中国(清)に派遣した使節団の記録である。この書物は翌1671年にジョン・オギルビー(John Ogilby, 1600-76)によって英訳され、『中国誌』(Atlas Chinensis)という題名で刊行されている(なお、この英訳版では、誤って原著者をアルノルドゥス・モンタヌス(Arnoldus Montanus, 1625?-83)としている)。
この書物には、福建地方で「ペールー」(peelou)という祭が行われていたことが記録されている。このことは、龍舟競渡は17世紀半ばの中国でも「ペーロン」かそれに似た音で呼ばれていたことを示している。同書によれば、この祭は「パラセル諸島の元知事」(formerly governor of the paracelles)が始めたものだという。「パラセル」はかつては非常に豊かで、金銀に富んでいたが、海に沈むと予言されていた。そこで、元知事とその友人たち、それに彼を信じた者たちは、島が沈むとされた数日前に島から中国本土へと逃れてきた。彼らが逃げ出した後で、島はすぐに沈んだという(李『媽祖信仰の研究』, pp. 134-135)。話自体はコックスやケンプファーの伝えているものと同じだが、重要なのは、これが日本ではなく中国において記録された話であることと、そして、島のあった場所がはっきり「パラセル諸島」だとされていることである。
パラセル諸島(Paracel Islands)は、南シナ海、海南島の南東海上、ヴェトナムの東方海上に浮かぶ、珊瑚礁からなる小島嶼群で、中国では「西沙群島」、またヴェトナムでは「ホアンサ(黄沙)群島」と呼ばれている(以下、混乱を避けるため、ここでは原則として英語名を用いる)。この島々は、大別して南西側のクレセント群島(Crescent Group; 永楽群島)と北東側のアンフィトリテ群島(Amphitrite Group; 宣徳群島)の2グループに分かれ、前者には珊瑚島(パットル島 Pattle Island)・甘泉島(ロバート島 Robert I.)、後者には永興島(ウッディ島 Woody I.)・趙述島(ツリー島 Tree I.)などの島々が含まれる。このうち永興島が最大の島だが、それでもその面積はわずか 2km2 ほどにすぎない。また、ほとんどの島がリン酸質グアノ(リン鉱石。海鳥の糞の堆積物)で厚く覆われている。
この島々の帰属をめぐっては、周辺諸国間の対立が20世紀初頭から延々と続いている。現在、パラセル諸島は全域が中国(中華人民共和国)の実効支配下にあり、海南省の管轄下に置かれている。しかし、台湾の中華民国政府とヴェトナム社会主義共和国も、現在もなお領有権を主張し続けている。
 |
| リンスホーテン『東方案内記』所載「東アジア図」の南シナ海の部分(神戸市立博物館蔵、『ナショナル ジオグラフィック日本版』2005年4月号附録より)。中央部に "I. de Pracel" が描かれている |
「パラセル」という地名の起源ははっきりしないが、オランダの旅行家ヤン・ホイフェン・ファン・リンスホーテン(Jan Huyghen van Linschoten, 1563-1611)の『東方案内記』(Itinerario, voyage ofte schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien, 1596)に収録された「東アジア図」には、すでに「プラセル島」(I. de Pracel)が南北に長い浅瀬として描かれている。したがって、16世紀末にはすでに、この島々はヨーロッパ人にも知られていたことになる。これがケンプファーのいう「暗礁」であることは間違いない。
ところで、パラセル諸島の古い呼び名のひとつに「万里石塘」がある。
パラセル諸島は、中国ではすでに後漢代(25-220)には、航海上の危険として認識されていたらしい。後漢末の楊孚の『異物志』という書物(現存せず)には、「漲海崎頭」(「漲海」は南シナ海の古名、ただし異説あり)は水深が浅く、しかも「磁石」が多いため、航海中の船はそれに吸い寄せられて遭難してしまう、という、いささか奇異な記述がある。
南宋代(1127-1279)になると、この島々やその周辺海域は「七洲洋」「長沙・石塘」「千里長沙・万里石塘」「万里石牀」などと呼ばれはじめる。さらに後代には、これが入れ替わって「万里長沙・千里石塘」とされたりもする。なお、「塘」(とう)とは、字義的には堤防のことである。浅瀬や岩礁が果てしなく広がっている様子を描写した呼び名であろう。
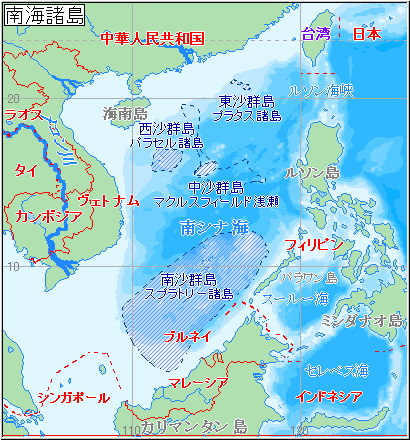
もっとも、この島々については、単にパラセル諸島だけでなく、その東にある暗礁群・マクルスフィールド浅瀬(MacClesfield Bank; 中沙群島)や、さらに、そのはるか南方海上にあって、現在、複雑怪奇な国際領有権紛争の舞台となっているスプラトリー諸島(Spratly Islands; 南沙群島、チュオンサ(長沙)群島、カラヤーン諸島、新南群島)なども含む、といった説もある(浦野起央『南海諸島国際紛争史』)。「パラセル諸島」の範囲自体も時代や状況によって変化しており(現在でも、パラセル諸島にはマクルスフィールド浅瀬を含めることもある)、また、現在の領有権問題とも絡んでくることもあって、このあたりの判断は難しい。なお、これらにプラタス諸島(Pratas Islands; 東沙群島)を加えた四群島を、総称して「南海諸島」ないし「南シナ海諸島」(South China Sea Islands)という。
江戸中期の儒学者・政治家、新井白石(君美、1657-1725)の世界地理書『采覧異言』(さいらんいげん)(正徳3年=1713序、その後加筆)には、この「万里石塘」が以下のように記載されている。
イラステフラモル 別名マンリ 万里石塘
岩礁、瓊州(海南島)南海の中にある。東西二、三百里。南北七、八百里。考えるに、むかしこの場所に国があった。大地はすでに陥没して、現在ではその山岳の頂が見えるだけである。 正徳甲子(正徳4年=1714)春、私はこの説をオランダ・カピタン(商館長)より得た。この年の秋の末、彼は帰国しようとしてこの岩礁を通り過ぎた。たちまち暴風に遭遇し、船団は粉々になった。ああ悼むべきかな。カピタンの姓名はコルネレス・ラルテン(コルネリス・ラルダイン Cornelis Lardijn, 1690-1714. 在任1711-12, 13-14)といった。(巻第三、現代語訳)
「万里石塘」は当時、陸地が沈んだ痕跡であると考えられていたこと、白石はその説をオランダ商館長のコルネリス・ラルダインから得たことがわかる。なお1714年11月13日、ラルダインを乗せて日本を出航したオランダ東インド会社のフライト船アリオン号(Arion)が、パラセル諸島付近で暴風雨のため遭難したことが記録されている(VOC Shipwrecks / Arion)。
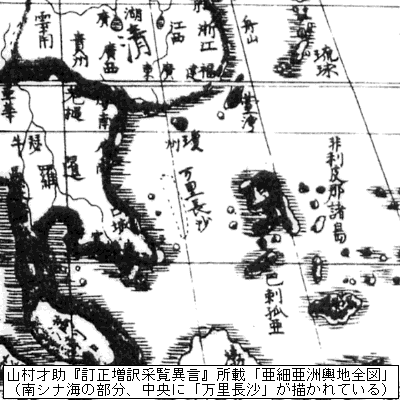
『采覧異言』の増補版で、近世最高の世界地理書とされる『訂正増訳采覧異言』(享和2年=1802成立)を著わした山村昌永(才助、1770-1807)は、この「万里石塘」はパラセル諸島だとし、また「イラステフラモル」はスペイン語の「インスラ、デ、プラッセル」(プラセル島)ではないか、としている。
「万里ヶ島」と「万里石塘」は、その名前も位置も、そして「沈んだ」という話も一致する。要するに、「万里ヶ島」とは「万里石塘」のことであり、そしてその「万里石塘」とはパラセル諸島(西沙群島)のことなのである。
(*) 「万里ヶ島」と「万里石塘」が同一であることについては、田北耕也がつとに指摘している(田北『昭和時代の潜伏キリシタン』, p. 109)。
泉州・福州や広州などの中国南部の港や、あるいは台湾海峡方面から、南シナ海を横断してまっすぐタイ湾やマラッカ海峡方面に向かおうとすれば、パラセル諸島のある海域を通過することになる。おそらく、珊瑚礁の岩礁や浅瀬、それに砂洲などがそこかしこに点在する危険海域を通過した船乗りたちが、これは海底に沈んだ陸地の痕跡に違いない、と想像をめぐらせたのだろう。
ついでながら、パラセル諸島は一時期日本の領土になりかけたことがある。
長い間、単なる航海上の危険としてのみ認識されてきた南海諸島の島々は、20世紀初頭になって、初めて国際領土紛争の舞台となった。当時、この島々にリン酸質グアノが堆積していることが着目され、中国と、ヴェトナムを植民地としていたフランス、それに台湾を植民地としていた日本の三者が、それぞれ自らの権利を主張し始めたのである。
そのさきがけとなったのが、1909年(明治42)のプラタス諸島紛争である。1907年(明治40)に日本人の西澤吉治がプラタス諸島を占領し、「西澤島」と名づけてリン鉱石の開発を始めた。これに対し当時の清朝(1616-1912)は日本政府に公式に抗議し、日本はこれを受け入れて1909年11月にプラタス諸島の領有権を放棄した。以来、この島々は中国領となっており、現在は台湾が実効支配している。
このように日本の場合、どちらかといえば民間資本が率先して探検・開拓を行い、政府がその後それを追認する、というパターンが多い。スプラトリー諸島についても、沖大東島(ラサ島)のリン鉱開発を行っていたラサ島燐砿株式会社(現・ラサ工業)が、1917年(大正6)から1921年(大正10)にかけて2度にわたる現地調査を行い、「新南群島」と命名して開発に取り組んでいる。しかし、同社は不況のため、1929年(昭和4)4月にこの海域から撤退した。
またパラセル諸島に関しては、日本政府は1909年に中国が行った領有宣言を尊重する立場をとっていた。1921年(大正10)から25年(大正14)にかけて日中合弁企業が諸島の開発を試みたが、失敗に終わっている。その後、中国(中華民国)はあらためて1927年(昭和2)にパラセル諸島を占領し、調査と開発に着手した。
その後、1930年代に入り、アジア情勢の緊張が高まる中で、フランスは1933年(昭和8)にスプラトリー諸島、1935年(昭和10)にパラセル諸島の領有を一方的に宣言した。日本はこれに対抗して、1939年(昭和14)、スプラトリー諸島の領有を一方的に宣言し、「新南群島」として台湾の高雄市に編入した。なお、このとき同時にパラセル諸島の領有も閣議決定しているのだが、こちらは公式には宣言されなかったようである。
しかし、日本は第二次世界大戦の敗北とともに植民地を失い、この海域からも撤退することになる。対日平和条約(サンフランシスコ講和条約、1951調印・52発効)第2条f項では、「日本国は、新南群島(Spratly Islands)及び西沙群島(Paracel Islands)に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」と規定されている。
しかし、中国が代表権問題(*)からこの条約の調印に招待されなかったこともあり、この両群島のその後の帰属については、この条約では取り決めがなされなかった。そのため、中国とフランスの対立は、その後も中国とヴェトナム(**)との対立として引き継がれることになる。
(*) 中国では国民党と共産党との内戦(国共内戦、1946-49)の末、1949年に共産党が中華人民共和国を樹立した。しかし、敗れた中華民国の国民党政権は台湾に逃れ、自らこそが中国の正統政府であると主張し続けた。このため、どちらの政権を中国の正統政府と見なすかが問題となった。
(**) ヴェトナムは1940年以来日本軍の占領下に置かれ、1945年3月には「ヴェトナム帝国」の「独立」が宣言された。しかし、これは日本軍の傀儡政権にすぎず、日本の敗北とともに崩壊した。同年9月、ヴェトナム共産党を中心とする勢力が「ヴェトナム民主共和国」の樹立を宣言し、フランスに対する独立戦争(インドシナ戦争、1946-54)に突入した。フランスはこれに対抗するため、1949年傀儡国家「ヴェトナム国」を発足させる。1954年のジュネーヴ協定により、ヴェトナムは北緯17度線を境に、北のヴェトナム民主共和国と南のヴェトナム国(1955年以後はヴェトナム共和国)に分割された。その後、ヴェトナム戦争(1960-75)を経て、両国は1976年に統一され「ヴェトナム社会主義共和国」となった。
また、1946年(昭和21)にアメリカから独立したフィリピンも、新たにスプラトリー諸島の領有権を主張し始める。さらに1970年代になると、各国は水産・海底資源の確保のために、排他的経済水域(いわゆる200海里水域)の設置に乗り出す。1974年(昭和49)10月にはスプラトリー諸島の海域で実際に海底ガス田が発見され、以後、各国の領有権争いはますます激しさを増し、1970年代後半には新たにマレーシアもスプラトリー諸島の領有権争いに参入する。
こうした中、1974年1月、中国・南ヴェトナム(ヴェトナム共和国)両国の海軍がパラセル諸島で交戦する事件が起こった。パラセル諸島は1956年(昭和31)以来両国の分割占領下に置かれていたのだが、この事件以来、今日に至るまでその全域が中国の占領下に置かれている。中国とヴェトナムとの対立はヴェトナム統一後も続き、1982年(昭和57)には再びパラセル諸島で、また1988年(昭和63)にはスプラトリー諸島で両国海軍が交戦する事件が起こっている。もとより、各国間のごく小規模なこぜりあいはこれにとどまるものではない。
なお現在、スプラトリー諸島は、中華人民共和国・台湾・ヴェトナムがその全域、フィリピン・マレーシアがその一部の領有権をそれぞれ主張しており、またブルネイもこの海域に漁業専管水域を設置している。
ちなみにマクルスフィールド浅瀬(中沙群島)は中国が領有権を主張しているが、この「群島」はそのほとんどが海面下にあるため、国際法的にはこの主張には根拠はない。ただし、ルソン島の西方海上にあって、中国が中沙群島の一部だと主張しているスカーバラ礁(黄岩島、民主礁)については、フィリピンも領有権を主張して争っている。
閑話休題。
整理しよう。
万里ヶ島伝説は、鹿児島県の甑島列島(口承)と野間岬(『本朝因縁故事集』)、それに長崎(ケンプファー『廻国奇観』『日本誌』、『天地始之事』)に伝わっていたらしく、また長崎県五島列島の「高麗島」伝説もほぼ同様のものとみなすことができる。
この分布状況は一見するとばらばらのようにも見えるが、いずれも東シナ海に面する港もしくは島やその近辺、という点では共通している。
この伝説がもともと中国南部に起源を持つことは、伝説の中の様々な要素から考えてほぼ間違いないところであろう。先述したように歴陽湖伝説は比較的早くに日本にも伝わっているが、万里ヶ島伝説に関して言えば、歴陽湖伝説が日本国内で変化したと考えるよりも、中国南部で歴陽湖伝説から派生した万里石塘の陥没伝説が直接伝わった、と考えたほうが妥当そうである。おそらくこの伝説は、16世紀末か17世紀の初頭くらいに、中国商人によって西九州に持ち込まれ、土着化したのだろう。
もっとも、この推測が正しいとすれば、中国にもほぼ同内容の伝承が残っている可能性があるが、いまのところその事実は確認できていない。この点も含め、この伝説の成立や流布の過程には、いまなお未解明の点が多く残されている。
また、沈んだ島から生存者やモノが別の土地に移ってくる、という話は、本来の歴陽湖伝説とは異なっている(先述したように、歴陽湖伝説では生存者は老婆一人だけで、しかも本来は石化してしまうらしい)。
中国南部から東南アジアにかけての各地には、大洪水の際に兄妹二人だけが生き残り、二人は夫婦となって全人類、あるいはある一族の先祖となった、という話(兄妹始祖型洪水神話)が広く分布している。この型の伝説は日本でも南西諸島に見られ、また八丈島にはこれに類似した(兄妹ではなく母子相姦であるが)「丹那婆」の伝説が伝わっている。万里ヶ島から生存者がやってきた話は、あるいは、このような古い神話を反映したものなのかもしれない。
高麗島・万里ヶ島双方について
甑島の万里ヶ島伝承について
茶碗島伝承について
野間岬の万里ヶ島伝承について
万里石塘について
ペーロンについて
『天地始之事』について
南海諸島について
野間神社について
潜伏キリシタンについて
高麗島について
なお、地図の作成にあたっては、世界地図描画ソフト PTOLEMY を使用しました。