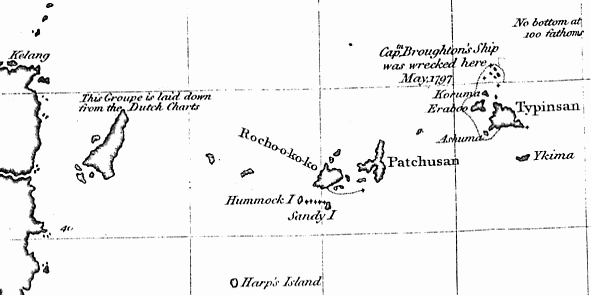
Ykima Island
18世紀末から19世紀初頭にかけて、東アジアに進出してきた欧米諸国の船が、次第に琉球に接近し始め、さらには入港するようになる。その最初の事例となったのが、イギリス海軍のウィリアム・ロバート・ブロートン(William Robert Broughton, 1762-1821)であった。
ブロートン率いるスループ艦プロヴィデンス号(HMS Providence; 摂理、神意の意)は、1795年2月にイギリスのプリマスを出航した。彼の使命は、ジョージ・ヴァンクーヴァー(George Vancouver, 1757-98)とともに北アメリカ大陸西海岸の調査を行うことであった。ところが、翌1796年にカリフォルニア(当時スペイン領)のモンテレーに着いたときには、ヴァンクーヴァー隊はとうに出発した後であった。そこでブロートンは予定を変更し、当時、ヨーロッパ人がいまだ不十分な知識しか持っていなかった、日本近海の調査に向かうことにしたのである。
1796年(寛政8)9月、ブロートンは蝦夷地(現在の北海道)の虻田(アブタ)(現在の虻田郡洞爺湖町)に到着し、さらに絵鞆(エトモ)(現在の室蘭)に入港して松前藩の役人と接触した。このとき彼は、内浦湾岸に有珠山をはじめとしていくつもの火山が並んでいるのを見て、この湾を「噴火湾」(火山湾 Volcano Bay)と名付けている。その後、彼はいったん千島列島の調査に向かったが、冬が迫ってきたために調査を中止し、12月にマカオに入港した(このとき宮古島南方を通過している)。この地でブロートンは、スクーナー船を1隻、プロヴィデンス号の伴走船として購入している。
ついで翌1797年4月、ブロートンは再び蝦夷地へと向かった。彼は5月16日に石垣島に接近、上陸調査をしたのち、宮古島へと向かった。ところが翌17日夜、プロヴィデンス号は八重干瀬で座礁し、航行不能となってしまう。一行はやむなくプロヴィデンス号を放棄してスクーナー船に乗り移り、宮古島民に救助を求めた。
島民の暖かい援助を受けた一行は、その後、6月にマカオに引き返した。しかしブロートンは、スクーナー船による調査の続行を決意して再出航し、7月に那覇に入港、ついで8月に再び絵鞆を訪れ、津軽海峡を通過して日本海に入り、サハリン西岸、朝鮮半島南岸を調査している。1799年2月、ブロートンはイギリスに帰国した。
ブロートンの航海記『北太平洋発見航海記』(A Voyage of Discovery to the North Pacific Ocean, 1804)には、イキマ島について特に調査した、という記述は無い。ただし、彼は脚註の中でゴービルの「覚書」を要約引用しており、その中でイキマ島の名も挙げられてはいる。
なお、どういうわけか彼は、「太平山」の北西の島(池間島?)を「コルマ」(Corumah; 来間?)、また、「太平山」の南西の島(来間島?)を「アシュマ」(Ashumah)と呼んでいる。伊良部島のことは正しく「エラブー」(Eraboo)と呼んでいるだけに、いささか奇妙である。
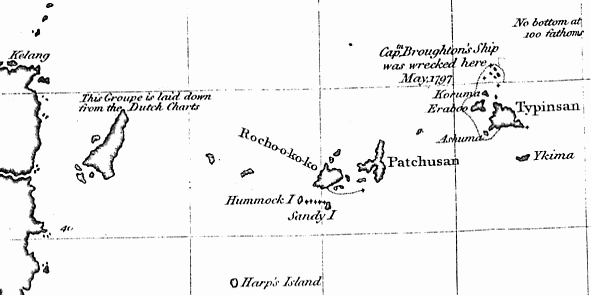 |
| ジェイムズ・バーニー「中国沿岸および広東河東方から日本列島南部に至る海域の海図」より、先島諸島周辺。八重干瀬の位置に「キャプテン・ブロートンの船は1797年5月にここで座礁した」という註記があり、また、その北東には「100 尋(約183m)の深さでも海底に到達せず」とある。なお、与那国島と思われる島が2つ描かれており、また、その南方には架空の「ハープ島」、西方、台湾との間には、「このグループはオランダの海図に記載されている」と註記された架空の陸地が描かれている。 |
1810年、イギリス海軍のジェイムズ・バーニー(James Burney, 1750-1821)は「中国沿岸および広東河(*)東方から日本列島南部に至る海域の海図」("Chart of the Coast of China and of the Sea Eastward From the River of Canton to the Southern Islands of Japan." バーニー『南海・太平洋航海発見年代記』第3巻 A Chronological History of Voyages and Discoveries in the South Sea or Pacific Ocean, Part III, 1813 所収)を作成した。この地図にはブロートンの探検成果も取り込まれており、また、「イキマ」(Ykima)もはっきりと描かれている。
(*) 「広東河」は珠江(しゅこう)のこと。香港とマカオの間で南シナ海に注ぐ大河。
1837年7月4日、広東(広東省広州市)のアメリカ貿易商社オリファント商会(Olyphant & Co.)所属のシップ型快速帆船、モリソン号(Morrison. 564トン)がマカオを出航し、日本へと向かった。日本史上に残る「モリソン号事件」の原因となった船である。
この船は、オリファント商会の共同経営者であるチャールズ・ウィリアム・キング(Charles William King, 1809-45)が派遣したもので、日本人漂流民の送還を兼ね、日本に対し通商交渉を行うことを目的とした非武装の商船だった。そのため、この船にはキング本人のほか、天保3年(1832年)に遭難し北アメリカ(現在のワシントン州フラッタリー岬附近。当時はイギリスとアメリカの係争地だった)に漂着した尾張船宝順丸の乗組員3名と、天保6年(1835)に遭難しフィリピン(当時スペイン領)のルソン島に漂着した肥後船(船名不詳)の乗組員4名、計7名の日本人が乗っていた。
モリソン号は台湾南方のバシー海峡を通過し、宮古列島に接近した。キングは、その著書『モリソン号の広東から日本への航海についての覚書』(Notes of the Voyage of the Morrison from Canton to Japan, 1839)の7月11日の項に、次のように記している。
 |
| キング『覚書』附録の海図より、マジコ・シマ(Madjico sima; 先島諸島)周辺。点線はモリソン号の航路。 |
午前九時北方に陸地を認め、それをウキマ島だと考えたが、間もなく船が夜の間に強い北東に流れる潮流に影響されてゐて、前方の陸地は太平山であることが明らかになつた。〔相原良一『天保八年米船モリソン号渡来の研究』, p. 36.〕
本文では「ウキマ」(Ukima)となっているが、附録の海図では「イキマ」(Ykima)になっている。おそらく本文の誤植であろう。
一行は太平山(宮古島)への上陸を試みたが、風向きが悪く接近することができず、翌7月12日、那覇に入港した。ついで7月15日、一行は那覇を出航し、江戸湾へと向かった。
これ以降に引き起こされる一連の出来事は、本題とは直接関係ないのだが、話の行きがかり上、ひととおり述べておくことにしたい。
キングは、当初から江戸への直接入港を目標としていた。江戸幕府が唯一の公式な貿易港として認めていた長崎を選ばなかったのは、長崎オランダ商館のオランダ人たちが屈辱的な扱いを強いられていることや、1804年に通商交渉のため長崎に来航したロシア使節ニコライ・レザーノフ(Nikolai Petrovich Rezanov, 1764-1807)が、半年も待たされた末にすげなく追い返される、という冷淡な扱いを受けたことを知っていたからである。
だが、これは結果的には最悪の判断となった。
1820年頃に日本東方海上でマッコウクジラの漁場が発見されて以後、日本近海にはイギリスやアメリカなどの捕鯨船が殺到しはじめる。彼らの中には、日本沿岸に接近するのみならず、上陸を試みる者まで現れたため、幕府は危機感をいだきはじめた。そのような中、文政7年(1824)、イギリスの捕鯨船の乗組員が、薩摩藩領であるトカラ列島の宝島(鹿児島県鹿児島郡十島村)で住民や役人と紛争を起こし、イギリス側に死者1名を出すという事件が起こった。この事件を重視した幕府は、翌文政8年(1825)、日本に接近する異国船を理由の如何を問わず無差別砲撃する、という「異国船(無二念)打払令」を発する。モリソン号は、この格好の標的となってしまったのである。
7月30日(天保8年六月二八日)、浦賀水道に接近したモリソン号は、浦賀奉行からの無警告砲撃を受ける。モリソン号はその場で停船し、日本側との交渉を行おうとした。だが、砲撃は翌日も続いたため、モリソン号はやむなく、別の入港地を求めて日本沿岸を西へと向かった。
8月10日(七月十日)、モリソン号は鹿児島に現れた。西日本有数の大名であり、密貿易を行っているとも噂される薩摩藩が相手ならば、交渉も期待できるのではないか、という判断に基づくものであった。だが、漂流民送還が目的であることを薩摩藩当局の役人に伝えたにもかかわらず、8月12日(七月十二日)、モリソン号は再び砲撃を受け、ほうほうの体で鹿児島から逃げ出すことになる。この期におよんでキングは長崎への入港を考えるが、祖国からの思わぬ攻撃におびえきった漂流民たちが反対したため、結局、マカオへと引き返すことになった。
一連の事態の責任が江戸幕府にあることはいうまでもないが、モリソン号側にも問題があったことは否めない。もし、最初から長崎を選んでさえすれば、少なくとも漂流民送還だけなら成功していたはずなのである。江戸時代の漂流民の数は決して少なくないが、祖国から受け取り拒否という仕打ちを受けたのは、このモリソン号事件だけである。
翌天保9年(1838)六月、オランダ商館がモリソン号来航のいきさつを幕府に報告してきた(ただし、この報告では、モリソン号を誤ってイギリス船としていた)。モリソン号の再来航がありうると判断した老中の水野忠邦(1794-1851, 在任1828-43, 44-45)は、幕府内での討議の結果、再来航があれば同船を打払令の対象から除外し、漂流民はオランダ船に託して帰国させる、という決定を下す。実際には、このときすでに漂流民たちは帰国をあきらめていたのだが、幕府側はそのことを知るよしもなかった。
ところが、この討議の過程で、評定所(最高裁判所にあたる機関)が、たとえ再来航があったとしても打払令を適用すべきである、という強硬意見を主張した。この意見が、田原藩(現在の愛知県田原市を中心とした藩)家老の渡辺崋山(1793-1841)や蘭学者の高野長英(1804-50)らに洩らされる。このとき崋山らは、この意見を幕府全体の意見と誤解した上、「モリソン」を船の名前ではなく、イギリス人プロテスタント宣教師で、高名な中国学者でもあったロバート・モリソン(Robert Morrison, 1782-1834)のことだと思い込んでいた(じつのところ、「モリソン号」の船名はこのロバート・モリソンにちなんで付けられたものなので、全くの的外れというわけでもないのだが)。それはともかく、長英は『夢物語』を執筆し、いたずらな打ち払いはかえって国防上の危機を招くことになる、として幕府の政策批判を始めた。だが、このことは、かねてから洋学を嫌い、崋山らに敵意をいだいていた目付の鳥居耀蔵(1796-1874)によって、彼らを陥れるための材料にされてしまう。
天保10年(1839)、崋山・長英らは鳥居の陰謀により、無人島(小笠原群島)渡航を計画した容疑で摘発される。これは全くの濡れ衣であることがすぐに判明するが、その捜査の過程で崋山・長英らの幕政批判が問題となり、彼らは処罰されることになった。いわゆる「蛮社の獄」である。
ところが同年(清道光19年)、清国がイギリス商人によるアヘン密輸に対する取り締まりを強化しようとしたことから、イギリスとの戦争(アヘン戦争、1840-42)が勃発した。この戦争に清国があっさりと敗北したことは、当の清国のみならず、東アジア世界全域に大きな衝撃を与えることになった。天保19年(1842)、アヘン戦争の終結とほぼ同時期に、幕府は異国船打払令を撤回する。以後の東アジア世界は、ヨーロッパを中心とする近代化の渦へと巻き込まれてゆくことになる。
イギリスの海軍軍人サー・エドワード・ベルチャー(Sir Edward Belcher, 1799-1877)は、1843年から1847年にかけ、サマラン号(HMS Samarang)(艦名はジャワ島の港町スマラン Semarang にちなむ)による東・東南アジア島嶼の測量航海を行った。彼はもともとアヘン戦争の結果を受け、中国沿岸の測量のために派遣されたのだが、新たにイギリス領となった香港のイギリス側当局者たちが、清国側を必要以上に刺激することを恐れて測量許可をおろさなかったため、東南アジア各地の測量に目的を切り替えたのである。
1843年11月27日、台湾とフィリピン(当時スペイン領)のルソン島の間にあるバタン島を出航したベルチャーは、宮古島へと向かった。彼は、その著書『サマラン号航海記・1843~46年』(Narrative of the Voyage of H.M.S. Samarang, During the Years 1843-46, 1848)の中で、次のように書いている。
[1843年]十一月三十日[清道光23年十月九日]ハンモック島とサンド島[Hummock and Sand Islands. ハンモック島は西表島南西沖の中御神島(なかのうがんじま)、サンド島は波照間島]を認め、サンド島の南側リーフに接近し、タイピンサン(宮古島)に到着するか、少なくとも海図上のイキマ[Ykima]が見えるだろうと、航行を続けた。
しかし予定の位置には見当らないし、悪天候で風に逆らって航行できないので、もよりの停泊地を求めることにして、活動を始めた。それからどうにかパーチュンサン(八重山)の西南角にたどりついたが、そこはリーフのはかには何もなかった。ところがいつものように幸運に見舞われ、間もなく「サマラン」号が進入できるだけのリーフの裂け目が発見できて、日没までに、船を回せるはどの余地はないにしても、安全に停泊できたのであった。〔第1巻第3章。安積鋭二〔訳〕「サマラン号の八重山来航記」, p. 23.〕
ベルチャーは翌1844年1月まで石垣島に滞在し、八重山諸島の測量を行った。ベルチャー自身は現地当局者の許可を得て測量を行ったように述べているが、『球陽』など琉球側の記録を見る限りでは、現地側の抗議を無視して測量を強行したというのが真相のようである。その後、彼は、1月から2月にかけてあらためて宮古島を訪れ、ここでも測量を強行したのち、2月にバタン島に引き返した。
なお、この際の調査で、彼は池間島の正しい位置を把握しており、「われわれは一七九六年宮古島の北の池間島[Y-ki-ma]で、ブロウトン艦長の「プロヴィデンス」号が難破し、人々の助けを得て船を建造して[これは誤解か?]中国に到達した、というはっきりした証拠をもっている」〔同, p. 29. 強調は引用者による〕と書いている。
ついで翌1845年6月、サマラン号は与那国島に現われ、さらに石垣島、尖閣諸島を調査したのち、6月19日(清道光25年五月十五日)、那覇に入港した。ベルチャーはかつて1827年、フレデリック・ウィリアム・ビーチー(Frederick William Beechey, 1796-1852)艦長のブロッサム号(HMS Blossom)に測量助手として乗り込み、那覇に入港したことがあり、彼にとっては18年ぶりの再来であった。ベルチャーは、さらに済州島と朝鮮半島南岸を調査したのち、1845年8月6日(弘化2年七月四日)、長崎に入港し、日本側の抗議を振り切って測量を強行した。その後、ベルチャーは再び那覇に寄港し、琉球での測量を終えている。
1852年11月24日、第13代アメリカ大統領ミラード・フィルモア(在任1850-53)から日本遠征の指令を受けたアメリカ東インド艦隊司令長官(代将)マシュー・カルブレイス・ペリー(Matthew Calbraith Perry, 1794-1858)は、東海岸のヴァージニア州ノーフォークを出航した。
余談ながら、フィルモア大統領はこのときすでに事実上失脚していた。前大統領ザッカリー・テイラー(在任1849-50)の急死によって副大統領から昇任した彼は、1852年の大統領選挙に際して与党であるホイッグ党(共和党の間接的な前身)の指名を受けることができず、しかも、選挙で当選したのは、野党・民主党のフランクリン・ピアース(在任1853-57)だったからである。
なお、日本遠征艦隊は蒸気艦3隻・帆走艦4隻・輸送帆船3隻の計10隻から構成されており、各艦それぞれの行動を逐一記していると大変なことになってしまうので、ここでは、基本的にはペリー本人の動きのみを追うことにする。
大西洋を東へ横断し、アフリカ南端を回航したペリー艦隊は、翌1853年4月に香港に到着、ついで5月、太平天国の大動乱(1850-64)のさなかにあった上海に入港した。そして、5月26日(清咸豊3年四月十九日)に那覇に来航し、アメリカとの通交を要求した。ペリーは6月にいったん小笠原群島に寄ったのち、再び那覇に入港、ついで、7月8日(嘉永6年六月三日)に浦賀へと現われることになる。
幕府に対して開国を求める大統領親書を手渡し、1年後の再来航を予告したのち、ペリーは那覇を経由して香港へと引き揚げた。彼は翌1854年1月20日に4たび那覇に来航、ついで2月に江戸湾に現われ、3月31日(嘉永7年三月三日)、神奈川(横浜市神奈川区)で日米和親条約の締結に成功する。同条約で開港地に指定された下田(静岡県下田市)と箱館(函館市)の調査を行ったのち、ペリーは7月に5度目の那覇入港を行い、7月11日(咸豊4年六月一七日)に琉米修好条約を締結した。
一連の航海の過程で、ペリー艦隊の艦船は宮古島南方海上を数度にわたり通過しており、その過程で水路調査も行われている。日本遠征の公式報告書『ペリー艦隊日本遠征記』(Narrative of the Expedition of an American Squadron to China Seas and Japan, 1856)の第2巻には、次のような記述がある。
いくつかの海図にはタイピンサン[宮古島]の南にイキマ島[The island Ykima]が描かれているがこの島は存在しない。〔オフィス宮崎〔訳〕「水路誌と航海上の所見」, p. 374.〕
これだけ大規模な調査が行われており、このようにはっきりと断言されているのだから、この段階でイキマ島は海図から抹殺されていてもよさそうなものである。しかし、そうならなかったのは、最初に述べた通りである。