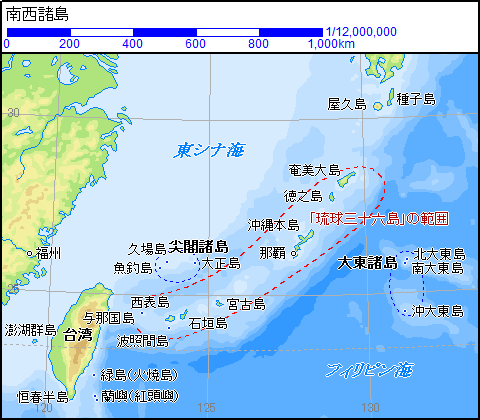
Ykima Island
慶応3年(1867)の大政奉還により江戸幕府は解体され、ついで王政復古クーデタ、戊辰戦争(1868-69)を経て、日本では明治政府が成立する。その明治政府にとって、近代国家の確立のために急務のひとつとされたのが、自国の領域の確定であった。
近代国際法においては、主権国家は明確な領域(領土・領海・領空)を持ち、その領域は国境線によって隣国とはっきり区分されるものとされている。同じ地域が複数の国家に属するようなことは、原則としてない。だが、こうした意味での「領土」や「国境線」といった概念は、歴史的には新しいものである。これらは、ヴェストファーレン条約(1648年)以後、近代国際法が成立する過程においてはじめて確立したものであり、それが東アジア世界に持ち込まれたのは、19世紀半ば、アヘン戦争以後のことであった。言いかえれば、それ以前における「国境」の概念は、現在とは大きく異なるものだったのである。国境はしばしば漠然とした曖昧なものであり、境界領域は、なかば自国に属し、なかば他国に属するボーダー・ゾーンとして認識されていた。
薩摩藩に服属しつつも独自の王を持ち、なおかつ清国にも朝貢していた琉球は、そういった曖昧な領域のひとつであった。そして、近代国際法体制の中での近代化をめざした日本にとっては、そのような領域を解消し、国境線を確定することが、重大な課題とされたのである。
まず、明治4年(1871)の廃藩置県により鹿児島藩(薩摩藩)が廃止され、代わって鹿児島県が設置されると、琉球はひとまず鹿児島県の管轄下におかれた。さらに翌明治5年(1872)、日本政府は最後の琉球国王尚泰(1843-1901, 在位1847-79)を「琉球藩王」とした。
いっぽう、たまたま清同治10年十一月(1871年12月)、那覇から宮古島に向かった船が遭難して台湾南部の恒春半島に漂着し、その乗組員54名が現地のパイワン族に殺害される、という事件が起こった。
台湾は、清康熙22年(1683)に漢族系の鄭氏政権(1662-83)が清国に降伏し、翌康熙23年(1684)に福建省台湾府が設置されて以来、清国の統治下に置かれていた。台湾の住民は、大陸から移り住んできた漢族系の住民と、南方系(オーストロネシア語族)の言語を話す先住民(台湾原住民)とに分かれる。清側では、後者のうち、台湾府の統治に服属している集団を「熟番」(じゅくばん)、それ以外の集団を「生番」(せいばん)と呼んでいた(*)。パイワン族はこのうち「生番」に属する集団であった。
(*) 日本の植民地時代(1895-1945)には「番」に代わり「蕃」の字が用いられるようになるが、1935年(昭和10)に「熟蕃」は「平埔(へいほ)族」、「生蕃」は「高砂(たかさご)族」と改称された。戦後、「高砂族」は「高山族」と改称される。1984年に先住民自身が「台湾原住民(族)」という呼称を自称として用い始め、1994年の中華民国憲法改正で公式な呼称として採用された。
1873年(明治6)6月21日の日清会談の際、日本側がこの一件を持ちだしたのに対し、清側は、琉球国は清国の「藩属」なのだから、この一件に関して日本は無関係であり、また、パイワン族は「王化」に服していない「生蕃」であるから「化外」に置いているのであって、清側が何らかの処分を下すことはできない、と返答してきた。
清国側の認識では、確かに台湾府を置いているとはいえ、台湾はいまだ服属せざる民の住むフロンティアであった。そして、東アジア世界での伝統的な論理では、皇帝の教化を受け入れた民のみが、その統治という“恩恵”を受けることができる、とされ、それ以外、すなわち「化外」の民は、統治から除外するものとされていた。だが、これは近代国際法体制とは相容れない論理であり、それどころか、領土喪失につながりかねない危険な解釈を生む恐れすらあった。
すなわち、日本側は、この「化外」発言を、台湾の「生蕃」居住地域は清の実効支配下にない、すなわち、近代国際法でいう「無主地」である、という意味に解釈したのである。国際法でいう「無主地」は、どの国家の領有にも属していない土地のことである。近代国際法においては、無主地に対しては、ある国が領有宣言を行って実効支配を確立すれば、その国の領有となる、ということが認められている。これを「先占」という。
台湾の「生蕃」居住地域が無主地なのであれば、「生蕃」を日本側が勝手に処罰してしまってもよい。いな、それどころか「生蕃」居住地域を日本のものにしてしまってもかまわないはずだ。――という理屈に基づき、1874年(明治7)2月、日本政府は台湾出兵を決定する。しかし、これに対して米英両国の駐日公使が反対の立場を明らかにしたため、同年4月、あわてた日本政府は出兵を一時中止することにした。ところが、征討軍司令官(台湾蕃地事務都督)に任命されていた陸軍中将西郷従道が独断で台湾に攻め込んでしまったため、日清関係は一触即発の危機に陥ってしまう。同年10月、事件解決のため「日清両国間互換条款」が結ばれ、日本側は、清国の台湾領有権を認めるとともに、この出兵は、「日本国属民等」に与えられた危害に対する「保民義挙」である、という言質を清国側から得ることになった。じつは、この条約自体には「琉球」という文言は無い(*)のだが、日本側はこれをもって、清国が琉球を日本に属するものと認めた、と解釈した。
(*) 1873年3月に小田県浅口郡柏島村(現在の岡山県倉敷市)の住民が台湾に漂着して略奪を受けるという事件が起こっており、この事件も出兵の口実のひとつとされていた。そのため、「日本国属民等」は彼等のことを指すとする解釈も可能である、という指摘もある(茂木敏夫『変容する近代東アジアの国際秩序』)。
ついで翌1875年(明治8)7月、日本政府は琉球藩に対し、清国への朝貢を立つことを強要した。最後に1879年(明治12)3月、日本政府は軍隊・警官隊を沖縄本島に派遣し、琉球側の抵抗を抑え、琉球藩の廃止と沖縄県の設置を強行した。ここに琉球王国は消滅する。この一連の過程を、日本側は「琉球処分」と呼んだ。
とはいえ当然のことながら、この処置はただちにすんなりと受け入れられたわけではなかった。以後、しばらくの間、沖縄県政に対する不服従運動が各地で続くことになる。1879年7月には、宮古島で、沖縄県が新設した派出所に雇用された青年が、裏切り者としてリンチを受け惨殺されるという事件(*)が起こっている。
(*) これを「サンシイ事件」という。「サンシイ」は被害者(本名は下地利社)の通称で、彼が沖縄県政への「賛成」(サンシイ)派であったことを意味するという。
また、清国に亡命し、清国の力を借りて王国を復活させようとする運動を展開した者も少なくなかった。さらに、朝貢国を一方的に吸収合併された形になった清国にとっても、この事態は決して静観できるものではなかった。
たまたま1879年、世界一周旅行中の前アメリカ大統領ユリシーズ・グラント(第18代、在任1869-77)が清国を訪れたのを機に、その仲介によって日清間の交渉が始まった。この結果、1880年(明治13)10月、先島諸島を清国に割譲し、その代わりに日本は清国から欧米諸国並みの通商権を得る、という、通称「琉球分島条約案」がいったん妥結される。しかし、これに対しては亡命琉球人の側から、これでは王国の再建は不可能だ、とする激しい反発の声があがった。そのせいもあり、清国側は土壇場になって正式な調印を中止し、この条約はそのまま立ち消えとなってしまった。これがもし調印されていたとすれば、宮古島以西の島々は日本領でなくなっていたはずである。以後、日清戦争までの15年間、琉球の帰属問題は、日清間の重大な外交問題としてくすぶり続けることになる。
琉球藩時代の1873年(明治6)7月9日、福州(福建省福州市)から南オーストラリア(当時イギリス領)のアデレードへ向けて航行中だったドイツのスクーナー商船R・J・ロベルトソン号(R. J. Robertson)が、東シナ海で台風に巻きこまれた。航行不能になったロベルトソン号は、7月11日(清同治12年六月十七日)夜に宮古島の南で座礁し、翌朝、宮古島民により救助された。
翌1874年(明治7)3月、ドイツ皇帝ヴィルヘルム1世(在位1871-88)は、島民の救助行為を讃え、現地に記念碑を建設するため、軍艦ツィクロープ号(SMS Cyclop, 艦長フォン・ライヒェ von Reiche)を宮古島に派遣した。ツィクロープ号は横浜、那覇を経由して、3月16日(清同治14年二月二一日)に宮古島に到着、翌日よりただちに記念碑の建設作業に取り掛かり、3月22日(ヴィルヘルム1世の誕生日)に除幕式を執り行った。現在、「ドイツ皇帝博愛記念碑」と呼ばれている碑である(*)。ツィクロープ号は3月24日、厦門(アモイ)に向け出航した。
(*) この事件はその後半世紀以上にわたって忘れ去られていたが、1930年代になって、日本とナチス・ドイツとが接近を深める過程で“再発見”され、“美談”として喧伝されることになった。1936年(昭和11)11月14日(日独防共協定調印の11日前)には、建碑60周年を記念して新たに「独逸商船遭難之地」碑が建てられている。また1937年(昭和12)から1945年(昭和20)まで用いられた尋常小学校(のち国民学校)4年生用の国定修身教科書にも、この事件に題材をとった教材が載せられている。もとの碑は1956年(昭和31)2月22日付で「ドイツ皇帝博愛記念碑」として沖縄県指定史跡となった。1996年(平成8)にはテーマパーク「うえのドイツ文化村」が開園した。2000年(平成12)7月21日には、九州・沖縄サミットに参加中のドイツ首相ゲアハルト・シュレーダー(在任1998-2005)が宮古島を訪問している。
このときフォン・ライヒェは、宮古島民から、周辺海域の状況についての聞き取りを行ったようである。英国海軍水路部が1884年に発行した『シナ海水路誌』第2版第4巻(The China Sea Directory, 2nd ed., Vol. IV, London: Hydrographic Office, Admiralty, 1884.)の「イキマ島」(Ykimah island)の項には、次のような記述がある。
【訳文】 ドイツ軍艦ツィクロープ号のフォン・ライヒェ艦長の報告によれば、現地住民のいうところによると、彼等が「オウミ・アカ・シマ」(Oumi Aka sima)と呼ぶこの島は実在しており、いくつかの島々からなるグループで、その最大のものは高さおよそ300フィート[約91m]だという。
【原文】 Captain Von Reiche H.M. (German) S. Cyclop reports that the natives say this island, which they name Oumi Aka sima, does exist, and that it is a group of islands, the largest of which is about 300 feet high. [p. 218.]
奇妙な記事である。そもそも、宮古島民が池間島ならぬイキマ島の存在を知っているはずがない。そのような島が欧米の海図に載っている、といった知識すらあったかどうか疑わしい。いったい「オウミ・アカ島」という名前はどこから出てきたのだろうか。
ひとつの可能性であるが、フォン・ライヒェは徐葆光同様、方角を間違えたのではないだろうか。すなわち、この記事に書かれているのは、じつは宮古島の北西にある尖閣諸島のことではないだろうか。
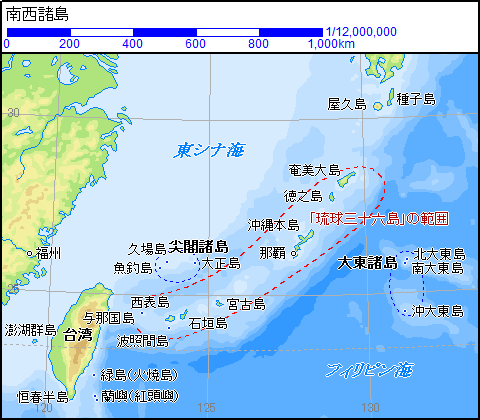
尖閣諸島は八重山列島の北方約 150~160km の地点に位置する島々で、最大の島である魚釣島(釣魚台(ちょうぎょだい))のほか、北小島・南小島・久場島(黄尾嶼(こうびしょ))・大正島(赤尾嶼(せきびしょ))の各島、それに沖ノ北岩・沖ノ南岩・飛瀬などの岩礁などから構成されている。この島々は現在、日本政府が実効支配下においているが、これに対して中国(中華人民共和国)と台湾(中華民国)(*)もそれぞれ領有権を主張している。そもそも諸島の呼称からしてからが問題で、日本側が沖縄県石垣市に属する「尖閣諸島」だと主張しているのに対し、中国側は台湾省宜蘭(ぎらん)県頭城鎮(とうじょうちん)に属する「釣魚島及其附属島嶼」(釣魚島および附属の島嶼)(**)だと主張しているのである。台湾側の主張でも、台湾省の所属とする点は同じだが、呼称は「釣魚台列嶼」となっている。なお、「尖閣」は「ピナクル」(Pinnacle; 小尖塔、また山頂、頂点の意)という英語名の訳語である(***)。
(*) 台湾は1945年(昭和20)、日本の敗戦とともに中華民国の占領下に置かれ、1947年(昭和22)5月に台湾省が設置された。ところが、中国本土で内戦(国共内戦、1946-49)に勝利した共産党が1949年(昭和24)10月に中華人民共和国を樹立し、敗れた中華民国国民党政府が台湾に逃れたため、台湾省は中華民国政府の支配する事実上の独立国となった(厳密には、中華民国政府は台湾省全域のほか福建省の馬祖島・金門島なども実効支配下に置いている)。中華人民共和国と中華民国(台湾)は現在に至るまで公式には互いにその存在を承認しておらず、中華人民共和国は台湾省全域、中華民国は中国本土全域の領有権を主張し続けている。
(**) 「釣魚」は中国語で魚釣りのこと。なお、中国語では「魚釣」は「魚が(何かを)釣る」という意味になってしまう。
(***) 「尖閣諸島」という呼称の成立事情はいささか複雑である。ベルチャーは、北小島・南小島を "Pinnacle Island(s)" ないし "Pinnacle Rocks", "Pinnacle Group" などと呼んでおり、その後のイギリス製水路誌もこれにならっている。日本の海軍水路寮(水路部の前身)がイギリス海軍の水路誌をもとに作成した『台湾水路誌』(1873年)は、この「ピナクル・アイランド」を訳して「尖閣島」としており、また『寰瀛(かんえい)水路誌 第一巻下』(海軍水路局、1886年)は、「ピナクル・グループ」を訳して「尖閣群島」としている。ところが、これがその後、次第に、その周囲の魚釣島や久場島なども含めた呼称として用いられるようになっていったのである。沖縄県師範学校教諭の黒岩恒は、「尖閣群島」(『地質学雑誌』第5巻第60号、1898年9月)で「魚鉤島」(原文のママ)・「久場島」などを指して「尖閣群島」の呼称を用いており、その2年後の「尖閣列島探検記事」(『地学雑誌』第12輯第140巻、1900年8月)では、「釣魚嶼」(魚釣島)・「尖閣諸嶼」(北小島・南小島)・「黄尾嶼」(久場島)をまとめて「尖閣列島」と呼び、「此(この)列島には、未(いま)た一括せる名称なく、地理学上不便少なからさるを以て、余は窃(ひそ)かに尖閣列島なる名称を新設することとなせり」とわざわざ断りをつけている。
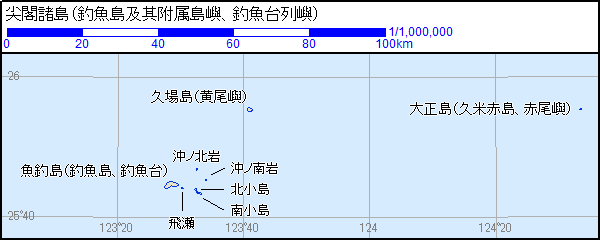
このうち大正島は、一島だけ大きく東に離れた位置(魚釣島の東方約 110km、久場島の東方約 88km)にある。この島は、琉球では古くは「クミアカシマ」(久米赤島)と呼ばれていた(ついでながら、国土地理院の2万5000分1地形図によれば、この島の最高地点は標高 75m である。ちなみに魚釣島は 362m、久場島は 117m)。「クミアカシマ」を「オウミアカシマ」と聞き違えた、というのはありうることである。フォン・ライヒェは、この「クミアカシマ」のことを、なにか誤解したのではないだろうか。
尖閣諸島の存在自体は、琉球と中国とを往復する船の航海上の目標として、古くから知られていた。現存最古の琉球冊封使録である陳侃(ちん・かん)の『使琉球録』(1534年)には、すでに「釣魚嶼」「黄毛嶼」「赤嶼」という島名が見え、その後の『中山伝信録』などにも、「魚釣台」「黄尾嶼」「赤尾嶼」という島名がしばしば現れる。
また琉球側では、この島々を古くは「ユクン・クバシマ」ないし「イーグン・クバシマ」と呼んでいたようである。1900年(明治33)に尖閣列島を訪れた沖縄県師範学校教諭の黒岩恒(1858-1930)によれば、もとは釣魚嶼(魚釣島)を「ヨコン」、黄尾嶼(久場島)を「クバ島」と呼んでいたのだが、いつの間にか両島の呼称が入れ替わってしまい、1900年頃には釣魚嶼が「クバ島」、黄尾嶼が「ヨコン」と呼ばれていたという(黒岩「尖閣列島探検記事」)。「ユクン」「ヨコン」ないし「イーグン」の語義については諸説あってはっきりしないが、「クバ島」の「クバ」はヤシ科のビロウ(蒲葵)という常緑樹のことで、沖縄本島西方の慶良間列島にも同名の「久場島」がある。「久場島」「久米赤島」の島名は、最後の冊封使録である趙新の『続琉球国志略』(1867年成立・1882年刊)に見えるので、少なくとも19世紀半ばにはこの呼称が存在したことはわかるのだが、「ユクン」のほうはどのくらい古くからあるのかはっきりしない。
ただし、この島々がどこの国の所属だと認識されていたか、ということになると、話はとたんに面倒なことになってくる。現在の領有権問題が直接からんでくるからである。おおざっぱに整理すれば、中国・台湾側が、この島々は古くから台湾に、したがって中国(清)に属する島々として認識されていた、と主張しているのに対し、日本側は、この島々は19世紀末まで中国(清)・琉球いずれの所属とも認識されていなかった、と主張している。
日本側の主張によれば、この島々はもともと無主地だったのであり、日本は後述する1895年(明治28)の閣議決定によって尖閣諸島の領有権を確立したのだから、尖閣諸島は日本領だ、ということになる。しかし、中国・台湾側の主張では、もともとこの島々は中国(清)領だったのだから、日本政府の主張は無効だ、ということになる。
領有権問題について論じるのがここでの本筋ではないので、ここではこれ以上の深入りは避ける。ひとつ確実なのは、この島々は1870年代まではまったくの無人島であり、特に開拓が試みられた形跡はない、ということである。
1885年(明治18)、沖縄県令(*)の西村捨三(在任1883-86)は、内務卿(**)の山縣有朋(在任1883-85)から、沖縄県近海の無人島を調査すべし、という内命を受けた。当時、南西諸島周辺の海図には、大東諸島や尖閣諸島のような所属の定まっていない無人島や、はたまたイキマ島のような、そもそも実在するかどうかもあやふやな島々が少なからず描かれており、これらの島々の領有権を確定することが問題となっていたのである。
(*) 県の長官。1886年に「県知事」と改称された。
(**) 内務省の長官。「卿」は明治初期の太政官制における省の長官の呼称で、1885年の内閣制度導入にともない「大臣」と改称された。
なお、大東諸島は沖縄本島東方海上約 340km の地点にある島々で、北大東島・南大東島・沖大東島の3島から構成される。この島々の存在はヨーロッパでは16世紀半ばから知られていたが、その正確な位置が知られるようになったのは19世紀初頭のことである。1815年、スペイン船サン・フェルナンド・デ・マガリャネス号(San Fernando de Magallanes)は、沖大東島を目視して「ラサ島」(Isla Rasa; Rasa island. スペイン語で「平地」の意)と命名した(*)。また1820年、ロシア軍艦ボロディノ号は南北大東島を目視し、艦長ザハール・ポナフィディン(Zakhar Ivanovich Ponafidin, 1786-1830)は、艦名をとって「ボロディノ諸島」(Ostrova Borodino; Borodino islands)と命名した。
(*) なお、『南大東村誌』など多くの文献が、1807年にフランスの軍艦カノニエル号 La Cannonière が命名したとするのは誤り。カノニエル号はこの島の測量を行っているが、「ラサ島」の命名者ではない。 Alexander George Findlay, A Directory for the Navigation of the Pacific Ocean, part II, London: R. H. Laurie, 1851, p. 1158, 等を参照。
いっぽう、沖縄には「ウフアガリジマ」という島についての伝説が伝わっていた。「ウフ」は琉球語で「大」、「アガリ」は「東」という意味であり、したがって「ウフアガリジマ」は漢字で表記すると「大東島」になる。この島は文字通り沖縄のはるか東方にあるものとされ、ニライ・カナイと同一視されることもあった。実在のボロディノ諸島に関する知識が伝説化してウフアガリジマになったのか、それとも、想像上のウフアガリジマと同じ方角にたまたまボロディノ諸島が実在したのか、そのあたりははっきりしないのだが、ともかく、今日の「大東島」という島名は、この伝説上の島の名に由来する。
西村県令はまず、同年8月に沖縄県五等属の石澤兵吾(1853-1919)に命じ、日本郵船の汽船「出雲丸」(720トン、林鶴松船長)をチャーターして、南北大東島に領有権を示す「国標」を設置させた。石澤らは8月29日に南大東島に上陸して「沖縄県管轄南大東島」の「国標」を設置し、ついで2日後には北大東島にも同様の「国標」を設置している。
ついで同年10月、西村県令は再び石澤に命じ、出雲丸で「魚釣島」「久場島」「久米赤島」の調査を行わせた。ただし、このときは「国標」の建設は行われていない。というのも、そもそもこの時点では、これらの島々が『中山伝信録』にある「魚釣台」「黄尾嶼」「赤尾嶼」と同じものなのかどうか、ということすら確定できておらず、もし同じだとすれば、清国側が領有権を主張してくる、という可能性が懸念されたからである。
その石澤は、同年11月4日付の調査報告書「魚釣島外二島巡視取調概略」の中で、次のようなことを述べている。
【訳文】 […]海軍水路局第17号の海図によれば、宮古島の南方およそ20海里[約 37km]をへだてて、イキマ島と称し、長さおよそ5海里[約 9.3km]、幅2海里[約 3.7km]くらいにして、八重山列島の小浜島[こはまじま][西表島と石垣島の間にある島。八重山郡竹富町。面積 7.84km²]に近いものを載せていわく、「『イビ』氏はこの島の探索に力を尽したが遂に発見できなかったという」とあり、また、英国出版の日本・台湾の海図にも Ikima イキマ (Doubtful) ダブトフル と記し、その有無を疑いの間に置いています。それから、今回八重山列島に行ったときに、土地の者の言うところによれば、昔、波照間島の一つの村の村民が、残らずその南方のある島に移転したそうです。その有無ははっきりしませんが、今でもこの島を南波照間島と称して、その子孫が連綿と続いている事を信じて疑わないということです。以上の2つの島は、他日、探求すべきではないかと考える次第です。
【原文】 […]海軍水路局第十七号ノ海図ニ拠レハ宮古島ノ南方大凡廿海里ヲ隔テゝイキマ島ト称シ長サ凡五海里幅二海里位ニシテ八重山ノ小浜島ニ近キモノヲ載セテ曰ク「イビ」氏ハ此島ノ探索ニ力ヲ尽セシガ遂ニ見得サリシト云フトアリ又英国出版ノ日本台湾間ノ海図ニモ Ikima イキマ (Doubtful) ダブトフル ト記シ以テ其有無疑ノ間ニ置ケリ而シテ今回八重山島ニ到リ土人ノ言フ所ニ拠レハ往昔波照間島ノ一村民挙テ其南方ノ一島嶼ニ移転セリト其有無判然セサレトモ今ニ之ヲ南波照間島卜称シテ其子孫ノ連綿タル事ヲ信シテ疑ハスト云フ以上ノ二島ハ他日御探求可相成可然哉ニ奉存候〔《帝国版図関係雑件》〕
「イビ」が何のことかわからないが、あるいは「E. B.」すなわちエドワード・ベルチャーのことであろうか。ともかく石澤は、イキマ島とパイパティローマがもし実在するとすれば、これを発見して領有すべきである、と考えていたわけである。
西村県令は、この報告書を受け、翌11月5日付で、山縣内務卿に対し「魚釣島外二島実地取調ノ義ニ付上申」を提出した。西村はその文末で次のように述べている。
【訳文】 […]宮古島の南方にある「イキマ」島、および八重山島に属する波照間島の南にある南波照間島の有無とも、雇汽船出雲丸の先島への航海のついでに探究すべきかどうか、[…]
【原文】 […]宮古島ノ南方ニ有之「イキマ」島及八重山島属波照間島ノ南ニ有之南波照間島ノ有無共雇汽船出雲丸ノ先島航ノ序ヲ以テ探究致可然哉[…]〔《帝国版図関係雑件》〕
少なくとも、西村県令がイキマ島とパイパティローマの捜索を本気で検討していたことは間違いない。
なお、魚釣島等への国標建設問題については、外務卿の井上馨(在任1879-85)が延期を主張した。その理由は、清国の新聞が、台湾近傍の清国領の島々を日本が占領した、という風説を載せており、そのような状況下で公然と国標を建設したりすれば、清国の疑惑を招きかねない、というものであった。また井上はこのとき、一連の探検は『官報』や新聞各紙などで公表しないように求めている。このため、12月5日付で、「目下建設ヲ要セサル」という、井上外務卿・山縣内務卿連名の指令が出された。
ちなみに、石澤はのちに沖縄県農商課長となり、福原實知事(在任1887-88)の命を受け『琉球漆器考』(1889年)の編纂を行ったことで知られている。しかし、彼は1888年(明治21)に沖縄を離れており、その後については、福島県耶麻郡長(郡の長官。1926年廃止)、新潟県刈羽郡長などをつとめたことが知られている程度である(野々村孝男「石澤兵吾」)。
ところで、なぜ井上外務卿は清国の出方を警戒したのか。これには当時の東アジア情勢がからんでいる。このころ、日清両国は朝鮮をめぐって対立を深めつつあった。
もともと朝鮮(李朝、1392-1910)は、琉球と同様に清の冊封を受けた朝貢国であった。ただし、冊封関係とは本来、中華皇帝と冊封された君主との間の儀礼的な関係であり、原則として、中華皇帝が朝貢国の内政や外交に口出しするようなことはなかった。
ところが、19世紀後半に欧米列強、そして、その影響を受けた日本が近代国際法の論理を東アジア世界に持ち込んだことによって、事態が変化する。1876年(明治9)2月、日本は朝鮮に軍事的圧力をかけて日朝修好条規(江華条約)を締結した。この条約で日本は、朝鮮を「自主ノ邦」、すなわち独立国と見なし、そのことによって清国の影響力を断ち切るとともに日本の影響力を高めようとした。いっぽう、日本による琉球の併合に衝撃を受け、危機感をいだいた清国側は、それまでの朝貢関係を、近代国際法でいう宗主国と従属国(従属国は宗主国から主権の制限を受ける)との関係として再解釈し、朝鮮に対する内政介入を始めるようになる。
1882年(明治15)7月、朝鮮の首都・漢城(現在のソウル)で兵士が叛乱を起こし、日本公使館などを襲撃する事件が起こった(壬午軍乱)。この背景には内政の混乱に加え、日朝貿易による経済的混乱と、それにともなう反日感情の拡大があった。これに対して日清両国が朝鮮に派兵、さらに清国は優勢な軍事力を背景として朝鮮に対する内政介入を始める。これに衝撃を受けた日本側は、清国を仮想敵国視するようになる。
1884年(明治17)6月、ヴェトナムの植民地化を進めようとするフランスと、朝貢国ヴェトナムに対する宗主権を主張する清国が軍事衝突を引き起こした(清仏戦争、~1885年6月)。このために朝鮮駐留の清国軍が手薄になった隙をついて、朝鮮で金玉均(キム・オッキュン)らが、駐朝日本公使竹添進一郎の支援のもとにクーデタを起こした(甲申政変)。ところが、清国軍が即座に行動を起こしたためにクーデタは失敗に終わり、かえって清国の影響力を強める結果を招いてしまった。翌1885年4月、日清両国は天津条約を締結し、日清両軍が同時に朝鮮から撤退すること、今後に朝鮮に出兵する場合は相互に事前通告することなどを取り決め、事態の収拾を図る。
この後、朝鮮では、清国と対抗するためにロシアと手を組もうとする動きが生じ、さらに、それに対抗してイギリスが朝鮮半島南方沖の巨文(コムン)島を占領する事件(1885年4月~87年2月)が引き起こされている。
また、台湾事件を機に台湾支配を確立しようとしていた清国は、1885年10月、福建省から台湾省を分離独立させた。
こうした複雑な国際的緊張関係が進行している中で、井上は、あえて清国を刺激し、新たな紛争の火種を作るのを避けようとしたのである。
1890年(明治23)1月13日、沖縄県知事の丸岡莞爾(在任1888-92)は、「魚釣島外二島」で漁業活動が活発になってきたため、取り締まりの都合上管轄権を確定する必要がある、という上申書を山縣有朋内相(在任1885-90、1889-90首相兼任)に提出した。しかし、この上申は立ち消えになってしまう。なお、同年11月29日、大日本帝国憲法(1889年2月11日発布)が施行されている。
1892年(明治25)1月、丸岡知事は、それまで調査の手がつけられていなかったラサ島(沖大東島)と「南波照間島」の調査を海軍省に要請した。これを受けて同年7月、海軍はスループ艦「海門」(かいもん)(芝山矢八艦長)を沖縄に派遣する。ただし、その派遣直前に県知事は丸岡から奈良原繁(在任1892-1908)に交替している。ところが、海門が8月に実際に調査を行ったのは南大東島とラサ島であった(『南大東村誌』、笹森儀助『南嶋探験』)。1893年(明治26)に沖縄各地を踏査した笹森儀助(1845-1915)によれば、「南波照間島」については、芝山艦長が「所在モ不明ノ島嶼ヲ探験スルノ道ナシ、且、本省ヨリソノ命ナシ」(所在も不明の島を探検する手段などないし、それに本省(海軍省)からもそんな命令は受けていない)として探検を断ったのだという。笹森はよほど腹に据えかねたのか、その旅行記『南嶋探験』(1894年刊)の草稿の中で、「元ヨリ所在不明ニ付キ探検ヲ要請シタルニ、如斯[かくのごとき]トハ何等ノ冷淡ゾ」(もとより所在不明だからこそ探検を要請したのに、こんなこととは、なんと冷淡なことか)と、憤慨の言葉を書き連ねている(刊本では削除)。もっとも、海軍側にしてみれば、海図にも載っていないような島をどうやって探せばいいのか、ということだったのではなかろうか。
1893年(明治26)11月2日、奈良原知事は、「久場島」と「魚釣島」に「本県所轄ノ標杭」(呼称が「国標」から変わっているが、理由は不明)を建設することを、第2次伊藤博文内閣の井上馨内相(在任1892-94)と陸奥宗光外相(在任1892-96)に上申した。ところが、この上申もしばらくの間留保されている。
1894年(明治27)1月、朝鮮南部で大規模な武装蜂起(甲午農民戦争)が始まった。対策に窮した朝鮮政府は、5月31日、清国に対する出兵要請を決定してしまう。しかし、これは朝鮮側にとって致命的な失策となった。このことを聞きつけた日本側が、天津条約を根拠として、公使館・居留民保護を名目に出兵してきたのである。この時点で叛乱はいったん収まってしまい、そもそも出兵の理由がなくなってしまったのだが、日本側は清国と朝鮮に対して朝鮮の内政改革を要求、そして7月23日、日本は朝鮮王宮を攻撃して親日派政権を樹立した。さらに25日には日本艦隊が兵士を輸送中の清国艦隊を攻撃し(豊島沖海戦)、続いて日清両軍は29日に成歓(ソンファン)、30日に牙山(アサン)で衝突、8月1日、日清両国は互いに宣戦布告を発した。ここに日清戦争が始まる。
1895年(明治28)1月14日、第2次伊藤内閣は「久場島」と「魚釣島」を沖縄県の所轄とし、「標杭」を建設することを閣議決定(内甲第2号「標杭建設ニ関スル件」)、1月21日付で奈良原知事に対して指示を発した。奈良原知事の上申から1年2ヶ月後のことである。このとき、日本軍はすでに遼東半島をほぼ制圧し、山東半島の威海衛要塞に対する攻略作戦を展開させており、さらに台湾占領作戦を準備しようとしていた。現在、日本政府は、この閣議決定を尖閣諸島領有の根拠としている(外務省「尖閣諸島の領有権問題について」1972年3月8日付)。
ただし、この閣議決定に基づいた「標杭」建設が行われた、という事実は確認されていない。また、領土編入という重大な決定にもかかわらず、法的根拠に基づく公示がなされた形跡もない(*)。こうした問題に加え、この決定が日清戦争の真っ最中になされたことが、戦争のどさくさにまぎれて領土をかすめ取った、という中国・台湾側の批判の根拠となっている。
(*) たとえば南鳥島(1898年7月24日付東京府告示第58号)、沖大東島(1900年10月17日付沖縄県告示第95号)、竹島(1905年2月22日付島根県告示第40号)などの領土編入は、いずれも府県告示に基づくもので、各府県の公報に掲載されている。
日清両国は1895年4月17日に講和条約(下関条約)を締結する(5月8日発効)。まず、清国は朝鮮を「完全無欠ナル独立自主ノ国」と認めた。もっとも、これは日本側にとっては、朝鮮から清国の影響を排除する、という意味でしかなく、日本は戦争と同時に朝鮮に対して露骨な内政干渉を行っており、かえって朝鮮民衆の反発を招くことになるのであるが。また、清国は日本に遼東半島と台湾・澎湖群島を割譲することになった。もっとも、最後の段階になってロシア・ドイツ・フランス三国が遼東半島割譲の撤回を要求してきた(三国干渉)ため、遼東半島だけは返還することになった。
また、台湾では割譲に反対する住民たちが、5月23日に「台湾民主国」の建国を宣言し、占領のため上陸してきた日本軍との戦争に突入した。台湾にとっては、下関条約は戦争の終わりではなく、むしろ始まりだったのである。日本側は半年後の11月18日に平定宣言を出したが、実際には戦闘はその後も延々と続いており、制圧がほぼ完了するのは1902年(明治35)のことであった。しかも、その後も先住民族との紛争や漢族系住民の散発的な武装蜂起が続いており、それらがほぼ終結するのは、下関条約からじつに20年後の1915年(大正4)のことである。
1896年(明治29)3月5日公布(4月1日施行)の勅令第13号「沖縄県ノ郡編制ニ関スル件」により、沖縄県に島尻・中頭・国頭・宮古・八重山の5郡が設置された。この勅令で、「大東島」は島尻郡に属するとされた。また、沖縄県はこのとき尖閣諸島を八重山郡に所属させた、ということになっているのだが、勅令自体には八重山郡の範囲は「八重山諸島」とあるだけで、尖閣諸島についての記載は無い。たしかにこれ以後、尖閣諸島は法的に八重山郡の一部として扱われているので、沖縄県側で何らかの手続きをしたのは確かなようなのだが、そのことについての文書が残されていないのである。
1900年(明治33)には、尖閣諸島の開拓者として知られる福岡県出身の実業家・古賀辰四郎(1856-1918)が、イキマ島の捜索を行っている。
古賀辰四郎は安政3年(1856)、筑後国上妻郡山内村(現在の福岡県八女市山内)に生まれた。
古賀はのち、尖閣諸島の開拓をはじめとする、実業家としての様々な業績が評価され、1909年(明治42)11月に藍綬褒章を受章している。このとき賞勲局が作成した文書が、国立公文書館所蔵《公文雑纂》に収められており(「古賀辰四郎ヘ藍綬褒章下賜ノ件」)、その中には、古賀の提出した「履歴書」が含まれている。それによれば、彼は1879年(明治12)、「琉球処分」直後の沖縄に渡り、海産物商人として那覇に「古賀商店」を開店したという。ただし、彼の経歴については、矛盾点や曖昧な点が少なくなく、人文地理学者の平岡昭利・下関大学経済学部教授は、特に初期の経歴についてはその大部分が疑わしい、と指摘している(平岡「明治期における尖閣諸島への日本人の進出と古賀辰四郎」)。
古賀は、1887年(明治20)頃から八重山一帯に産するヤコウガイ(夜光貝)に目をつけ、輸出事業を始める。しかし、ヤコウガイはまもなく乱獲のために激減を始め、彼の関心は無人島開拓へと向かうことになる。
1891年(明治24)11月、古賀は丸岡知事の許可を得て大東島の開拓を行おうとした。ところが、この事業は最初の一歩目でつまづいてしまう。翌1892年(明治25)3月、古賀は沖縄開運会社(「開運」は誤記ではない)の汽船「大有丸」(たいゆうまる)をチャーターして大東島に向かったのだが、時化と絶壁に囲まれた地形に阻まれ、どうしても上陸できなかったのである。
続いて1895年(明治28)6月、彼は尖閣諸島で大量に繁殖していたアホウドリに目をつけ、日本政府に対し、アホウドリ捕獲のために久場島を借用することを申し出、野村靖内相(在任1894-96)に対し「官有地拝借御願」を提出した。この「願」によれば、古賀は以前(「履歴書」によれば1894年)にも久場島の拝借を願い出ていたのだが、久場島の領有権が確定していなかったために実現していなかったという。そして、このたび久場島が日本の所属であることが確定したため、あらためて借用を申し出ることにしたのだという。
なお、このとき彼は、1885年に「久場島」に上陸しアホウドリを発見した、と主張している。ただし、この開拓については、古賀の主張以外に傍証となるものが発見されていない上、本人の主張自体にも多くの矛盾があり、実際に行われたとは考え難いことが、平岡昭利氏によって指摘されている。
まず、1895年6月10日付の「官有地拝借御願」では、古賀は
明治十八年沖縄諸島ニ巡航シ舟ヲ八重山島ノ北方九拾海里ノ久場島ニ寄セ上陸致候 〔明治18年[1885]沖縄諸島に巡航し、船を八重山島の北方90海里[約 170km]の久場島に寄せ上陸いたしました〕
と述べている。ところが、1909年の「履歴書」では、
明治拾七年尖閣列島ニ人ヲ派遣シ同島ノ実況ヲ探検セシメ爾来年々労働者ヲ派遣シ海産物採取ヲナサシメタリ 〔明治17年[1884]、尖閣列島に人を派遣し、同島の実況を探検させ、以来、年々労働者を派遣し、海産物採取をさせた〕
となっている。つまり、開拓着手の年次が1年違っているうえ、前者では古賀自身が島に渡ったとしているのに対し、後者では本人は島に渡らず、他人を派遣したことになっているのである。しかも、古賀がこの時期に開拓を始めたのなら、1885年10月の出雲丸探検と時期が重なるはずなのだが、出雲丸に関する沖縄県側の報告書には、古賀に関することは全く記されていない。石澤兵吾などは、「魚釣島」について「人蹟無シ」と書いているが、これも古賀の主張とは矛盾する。さらに、沖縄県による1890年と1893年の領土画定を求める上申は、いずれも漁業関係の取り締まりをその理由としており、古賀の事業に触れるところがない。なお、古賀の遺族は、1885年の時点で古賀が「明治政府に開拓許可を申請」したが受理されなかった、と主張している(古賀善次「毛さん佐藤さん 尖閣列島は私の“所有地”です」)。しかし、「官有地拝借御願」や「履歴書」にはそのような記述はなく、詳細不明である。
ともかく、出願から1年3ヶ月後の1896年(明治29)9月、政府は古賀に対して、尖閣4島(南小島・北小島・魚釣島・久場島)の30年間無償貸与を許可した。翌1897年(明治30)3月、古賀は八重山から出稼ぎ者35名を尖閣諸島に派遣させた。
尖閣諸島でのアホウドリ猟は最初のうちこそ順調だったが、早くも1900年(明治33)には捕獲量が激減しはじめる。あわてた古賀は、東京帝国大学理科大学動物学科(現在の東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻動物科学大講座・理学部生物学科動物学コース)教授の箕作佳吉(みつくり・かきち)(1858-1909)に面会し、助言を求めた。箕作は、実地調査を行わなければわからない、として、その調査員として、動物学教室の講師であった宮島幹之助(1872-1944)を推薦した。宮島自身の専門は腔腸動物で、鳥類ではなかったのだが、箕作の懇請で実地調査を行うことになる。調査隊には宮島と古賀本人のほか、沖縄県師範学校教諭の黒岩恒、八重山島司(八重山列島の長官)の野村道安(在任1895-1903)らが同行することになる。古賀はこの調査のため、大阪商船(商船三井の前身の一つ)所属の汽船・永康丸(390トン、佐藤和一郎船長)をチャーターしている。
永康丸は5月3日に那覇を出港し、尖閣諸島へと向かったのだが、その途中、古賀と宮島は相談の上、5月4日にイキマ島の捜索を行ったという。
宮島は、同年9月11日に東京地学協会例会で行った講演の中で、次のように述べている。
【訳文】 従来、様々な地図の上に、宮古島の南方にイキマ島という一小島を記してありましたが、視察して来た人の報告や、また明治18年[1885]ごろ、沖縄県庁より特にこの方面の無人島を探検のため大有丸を派遣した時にも、この島を発見せずに戻ったとあり、そのため、今回の航海はまた得にくいよい機会でしたので、古賀氏と相談し船をこの島に向けて進めさせ、5月4日の正午、この島の所在地(北緯24度25分・東経125度28分)に到着しました。ところが、この日は天気が良かったにもかかわらず、その附近に一つの島らしきものも発見しませんでした。船員の話によれば、このような天気の良い日には15マイル[海里、約 28km]の遠くにあるものもよく確認できるはずだということです。この島の存否は明らかではありませんが、とにかく位置が違うことは明らかで、海図上に示されてる場所およびその周囲10マイル[海里、約 19km]以内にはこの島は存在しないことを確認しました。
【原文】 従来種々の地図の上には宮古島の南方にイキマ島と云へる一小島を記しあれども、視察し来りたる人の報告、又明治十八年頃沖縄県庁より特に此方面の無人島を探検の為め大有丸を派遣せし時にも此島を発見せずして戻りしとあり、故に今回の航海は又得易からざるの好機会なるを以て、古賀氏と相談し船を此嶋に向け航進せしめ五月四日の正午該嶋所在地(北緯二十四度廿五分 東経百二十五度廿八分)に到着せり、然るに此日は天気晴朗なりしにも係らず、其附近に一の島らしきものを発見せず、船員の話に、此の如き好晴の日には十五哩の遠きにあるも能く認め得べき筈なりと、此島の存否は明ならざれども、兎に角位置の違うは明なる処にして、海図上に示せる場所及其周囲十哩以内には該島の存在せざるを確認せり、〔宮嶋幹之助「沖縄県下無人嶋探検談」, p. 587〕
これによれば、詳細は不明であるが、1885年ごろに沖縄県が大有丸を派遣したことがあったらしい。
また、古賀も「履歴書」において、この点について次のように述べている。
【訳文】 イキマ島の探検 万国地図の示す所によれば、宮古島の南東、すなわち東経125度28分・北緯24度23分の位置にイキマ島がある。明治33年5月、尖閣列島航行の途次、本人はこの探検を試みようと思い、汽船を遠回りさせてこの地点に達した。折柄、天気晴朗、ひとつの雲霧の展望をさえぎるものもなく、探検上有利の一日であったが、地点より約20海里[約 37km]四方以内には一小島影をも認めることができず、よってさらに遠く附近を探ったものの、ついに何も得ることができなかった。
【原文】 イキマ島ノ探検 万国地図ノ示ス所ニヨレハ宮古嶋ノ南東即チ東経百二十五度二十八分北緯二十四度二十三分ニ当リテイキマ島アリ明治三十三年五月尖閣列島航行ノ途次本人ハ之カ探検ヲ試ミント欲シ汽船ヲ迂行セシメ右ノ地点ニ達シタリ折柄天気晴朗一朶ノ雲霧ノ展望ヲ遮キルモノナク探検上有利ノ一日ナリシト雖モ地点ヨリ約二十方浬以内ニハ一小島影ヲモ認ムルヲ能ハサリシヲ以テ更ニ遠ク附近ヲ探リシモ終ニ何等ノ得ル所アラサリキ
古賀自身は、おそらく島が発見できれば自ら開拓するつもりであったのだろう。
永康丸はその後、いったん西表島で石炭を補給したのち、5月10日に尖閣諸島に到着した。宮島は、アホウドリの激減は乱獲によるものだと断定し、「もし従来の如く労働者のなすまゝになし置かば、数年も経ぬ中に信天翁は全く此島に其跡を絶つに至る可し」(もし従来のように労働者のなすがままに放置すれば、何年もたたないうちにアホウドリは全くこの島からその姿を消すに違いありません)と警告している。
ちなみに、宮島は調査中に八重山諸島でマラリアが流行している状況を知り、これを機として、京都帝国大学医学部衛生学教室でマラリアの研究を始めた。その後、彼は国立伝染病研究所所員、慶應義塾大学医学部教授、衆議院議員(在任1924-28)、国際連盟常設阿片中央委員会(国際麻薬統制委員会 INCB の前身)委員(在任1929-35)、北里研究所副所長(在任1938-44)などを歴任している(『北里研究所五十年誌』)。
いっぽう、宮島の警告にもかかわらず、その後もアホウドリの乱獲は続けられた。そのため、当然のことながらアホウドリは絶滅に瀕することになる。その後、古賀は鳥類の剥製作りやカツオ漁業、鳥糞(グアノ)の採取などに転換を図る。事業の多角化にともない尖閣諸島への入植者も増加し、魚釣島には「古賀村」と呼ばれる村落が形成されるに至る。さらに、1906年には中御神島(なかのうがんじま)(西表島の南西約 15km の位置にある島)の捕鳥事業にも着手する。こうした一連の事業が評価され、彼は1909年、先述したように藍綬褒章を受章した。しかし、いずれの事業も、数年のうちにことごとく資源が枯渇し、結局は衰退の道をたどることになった。1918年(大正7)、古賀辰四郎は那覇の病院で死去する。
なお、1902年(明治35)12月、政府は南小島・北小島・魚釣島・久場島を八重山郡大浜間切(*)に編入し、地番を設定した。ただし、大正島(久米赤島)だけは、1922年(大正11)7月25日付ではじめて地籍が設定された。「大正島」という名前が付けられているのはこのためである。また、このような経緯から、大正島は一島だけ古賀家とは無関係で、現在でも国有地となっている。
(*) 「間切」(まぎり)は沖縄特有の行政単位。村の上にあたる。1908年(明治41)廃止。
イキマ島がひっそりと海図から消されたのと同じ1906年(明治39)、沖縄県は、パイパティローマは台湾東南海上の島嶼なのではないか、とする説に基づき、台湾東南海上にある火焼島(かしょうとう)(緑島[りょくとう])(*)と紅頭嶼(こうとうしょ)(蘭嶼[らんしょ])(**)の調査を行ったといわれている(***)。西村・丸岡・奈良原と、歴代の沖縄県令・知事がパイパティローマに執拗にこだわっていたのは、べつに、彼らがまぼろしの島に対するロマンティックなあこがれをいだいていたからではなく、それだけこの島の実在性が高いと見られていたからであろう。
(*) 第二次大戦後に「緑島」と改称された。台湾省台東県緑島郷に属し、漢族系住民が住む。
(**) 第二次大戦後に「蘭嶼」と改称された。台東県蘭嶼郷に属し、タオ族(ヤミ族)が住む。タオ語名「ポンソ・ノ・タオ」(Ponso no Tao)、欧名「ボテル・トバゴ」(Botel Tobago)。波照間島の南西約 320km に位置しており、パイパティローマの有力候補地とされることが多いが、確証があるわけではない。
(***) 又吉盛清『日本植民地下の台湾と沖縄』, pp. 286-288。ただし、その典拠として挙げられている赤嶺江峰「波照間島と紅頭嶼」には、「去る明治三十九年の頃」、「南波照間島[フヘーハテルマじま]は台湾の紅頭嶼と火焼島であらうといふので其[その]探検の為[た]め沖縄県技手某等両名某艦に搭乗して来たが其[その]筋に於[おい]ても未探の土地であつたから上陸出来ず餘儀なく逆戻[ぎやくもどり]を喰つたと派遣員の某が余に語つた」という曖昧な記述があるのみで、詳細は不明である。なお、紅頭嶼については、台湾総督府が1897年3月に佐野友三郎・成田安輝らを派遣して実地調査を行わせた(中京大学社会科学研究所台湾史料研究会〔編〕『日本領有初期の台湾――台湾総督府文書が語る原像』中京大学社会科学研究所、2005年)のをはじめ、同年10~12月には鳥居龍蔵が人類学的調査を行う(『鳥居龍藏全集』第11巻、朝日新聞社、1976年)などしており、「未探の土地」という記述は事実に反する。
古賀辰四郎の死後、その事業は息子の善次に引き継がれた。尖閣4島(南小島・北小島・魚釣島・久場島)の無償貸与期間が1926年(大正15=昭和元)で終了した後、1932年(昭和7)、4島は古賀家に払い下げられている。しかし、このころには古賀家の事業は完全に衰退し、1940年(昭和15)頃には尖閣諸島は無人島に戻ってしまった。
1945年(昭和20)、日本は連合国に降伏し、台湾は中華民国、沖縄はアメリカの占領下に置かれることになった。サンフランシスコ講和条約(対日平和条約。1951年9月8日調印・1952年4月28日発効)により、日本は「台湾及び澎湖諸島」の領有権を放棄し、「北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)」をアメリカの占領下に置くことに合意した。
なかば忘れ去られていた尖閣諸島の存在が再び着目されるようになるのは、1969年(昭和44)に2つの出来事が起こってからのことである。
まず1969年5月、アジア沿海鉱物資源共同探査調整委員会(CCOP)(*)が、前年10~11月に実施した、アメリカ・中華民国(台湾)・韓国・日本4ヶ国の共同による東シナ海海底調査の報告を公表した(**)。この報告では、台湾の北東、すなわち尖閣諸島近海に大規模な海底油田・ガス田が存在する可能性があることが指摘されていた。
(*) 東・東南アジア地球科学計画調整委員会(CCOP)の前身。1966年に国連アジア極東経済委員会(ECAFE. 1974年に国連アジア太平洋経済社会委員会 ESCAP と改称)の附属機関として設立され、1987年に独立した政府間機関となる。
(**) K. O. Emery et al., "Geological Structure and Some Water Characteristics of the East China Sea and the Yellow Sea" (東支那海海底の地質構造と,海水に見られるある種の特徴に就いて), CCOP Technical Bulletin, Vol. 2 (1969), pp. 3-43. しばしば「エカフェ報告」と呼ばれる。産業技術総合研究所地質調査総合センターの出版物案内で全文が公開されている。
さらに、同年11月の日米首脳会談で、アメリカが、1972年(昭和47)年中に沖縄の施政権を日本に「返還」することが取り決められた。アメリカ施政権下の「琉球政府」の範囲には尖閣諸島が含まれており(1952年琉球列島米国民政府布令第68号「琉球政府章典」など)、このときの取り決めでも、尖閣諸島も沖縄の一部として「返還」されるものとされていた。また、このことは同時に、沖縄が中国領になる可能性が消え失せたことを意味していた。
翌1970年(昭和45)7月、中華民国(台湾)当局は、アメリカの石油企業ガルフ・オイル社(「セブン・シスターズ」の一社に数えられた国際石油資本。1984年にスタンダード・オイル・オブ・カリフォルニア社[現在のシェブロン社]に買収された)の日本法人パシフィック・ガルフ社に対し、台湾北東海域の大陸棚における石油資源の試掘権を許可した。ところが、その範囲には尖閣諸島周辺海域が含まれていたのである。これによって、台湾が尖閣諸島の領有権を主張していることが表面化する。さらに12月になると、中華人民共和国の側も、『人民日報』紙を通じて「釣魚島」の領有権を主張しはじめた。
1971年(昭和46)になると紛争はさらにエスカレートし、ワシントン、ニューヨーク、香港、ロンドンなど世界各地で、中国系住民による、日本の「釣魚台侵略」への抗議デモが多発する。6月11日には中華民国外交部(外務省)が「釣魚台列嶼」の領有権を公式に主張する声明を発した。さらに、12月30日には中華人民共和国外交部も公式に「釣魚島」の領有権を主張する。これに対して1972年(昭和47)3月8日、日本国外務省は「尖閣諸島の領有権問題について」を公式見解として発表、あらためて「尖閣諸島」の領有権を再確認した。なお、この間、1971年6月17日に沖縄返還協定が調印され、1972年5月15日、沖縄は再び日本領となった。また、1972年9月29日の日中共同声明により、日本は中華人民共和国政府と国交を樹立、台湾の中華民国政府と断交している。
以後の紛争の経緯をごく簡単にたどっておく。――1978年(昭和53)4月、中国の漁船群が大挙して尖閣諸島周辺海域に押し寄せ、日本側の主張する領海に侵入する。8月12日、日中平和友好条約調印(10月23日発効)。同じく8月12日、日本の右翼団体「日本青年社」が魚釣島に木製の「灯台」を設置。この「灯台」は1988年(昭和63)にアルミ製のものに建て替えられ、2005年(平成17)2月、海上保安庁の管理する正式な灯台(魚釣島灯台)となった。1992年(平成4)2月、中国は「領海及毘連区法」(領海および接続水域法)を制定し、「釣魚島」を自国領だと主張。1996年(平成8)7月、日本青年社が北小島に「灯台」を設置、これが中国・台湾・香港・マカオの活動家を刺激して大規模な「保釣運動」が引き起こされ、10月には香港とマカオの活動家が「釣魚島」に上陸するに至る。2004年(平成16)3月、中国の活動家が「釣魚島」に上陸し、はじめて日本側に逮捕される。最近では2008年(平成20)6月、台湾の遊漁船「聯合号」が、魚釣島付近の日本側の主張する領海内で日本国海上保安庁の巡視船「こしき」と衝突し沈没、この処理をめぐって台湾側が軍艦を派遣しようとする、という騒ぎが引き起こされている。
ちなみに、古賀善次は1978年(昭和53)に死去、また花子未亡人も1988年(昭和63)に死去し、古賀家は断絶した。また、古賀家が持っていた尖閣4島の所有権は、埼玉県のある実業家一家に譲渡されている。したがって日本の国内法の上では、尖閣諸島は、国有地である大正島を除き、2009年(平成21)現在も私有地となっているわけであるが、2002年(平成14)4月からは日本政府が借り上げて管理を行っている。
なお、尖閣諸島のアホウドリは1940年代には完全に姿を消してしまい、一時は絶滅したと思われていた。しかし、1971年(昭和46)4月1日、琉球大学尖閣列島学術調査団(池原貞雄団長)による上陸調査中に、南小島でアホウドリ12羽が発見された(『尖閣列島学術調査報告』琉球大学、1971年)。その後、1988年(昭和63)4月13日に、長谷川博氏(東邦大学理学部講師=当時)が朝日新聞社の小型ジェット機「はやて」で空中からの調査を行ったところ、南小島でアホウドリのヒナが発見され、島内で繁殖活動が行われていることも確認されている(『朝日新聞』1988年4月16日付夕刊)。2009年現在、アホウドリの自然繁殖地は、伊豆諸島の鳥島とこの尖閣諸島だけとなっている。なお、鳥島は噴火の恐れがあり、また尖閣諸島も領有権問題のため保護活動が困難なことから、2008年(平成20)から、山階鳥類研究所が、環境省、アメリカ魚類野生生物局(FWS)と共同で、小笠原諸島の聟島に繁殖地を人為的に造る計画を実施している。
ところでイキマ島であるが、現在でも、なんの間違いか、書籍などの解説図に載ってしまっていることがある(たとえば片野田逸朗『琉球弧・野山の花 From Amami ――太陽の贈り物』南方新社、1999年, p. 9)。ひとつ探してみるのも一興かもしれない。
※附記――「東亜輿地図」に記載されたイキマ島について最初に教示くださった一読者の方に感謝いたします。